- 2020.11.10
ブレーキパッドの交換方法や費用、寿命の判断方法を解説!

車のブレーキをしっかり効かせるために大切なパーツがブレーキパッドです。車のなかでもブレーキは非常に重要な部位なので、ドライバー側も理解を深めておきましょう。
ブレーキパッドを交換する方法や交換にかかる費用、さらに寿命の判断方法について、詳しく解説します。
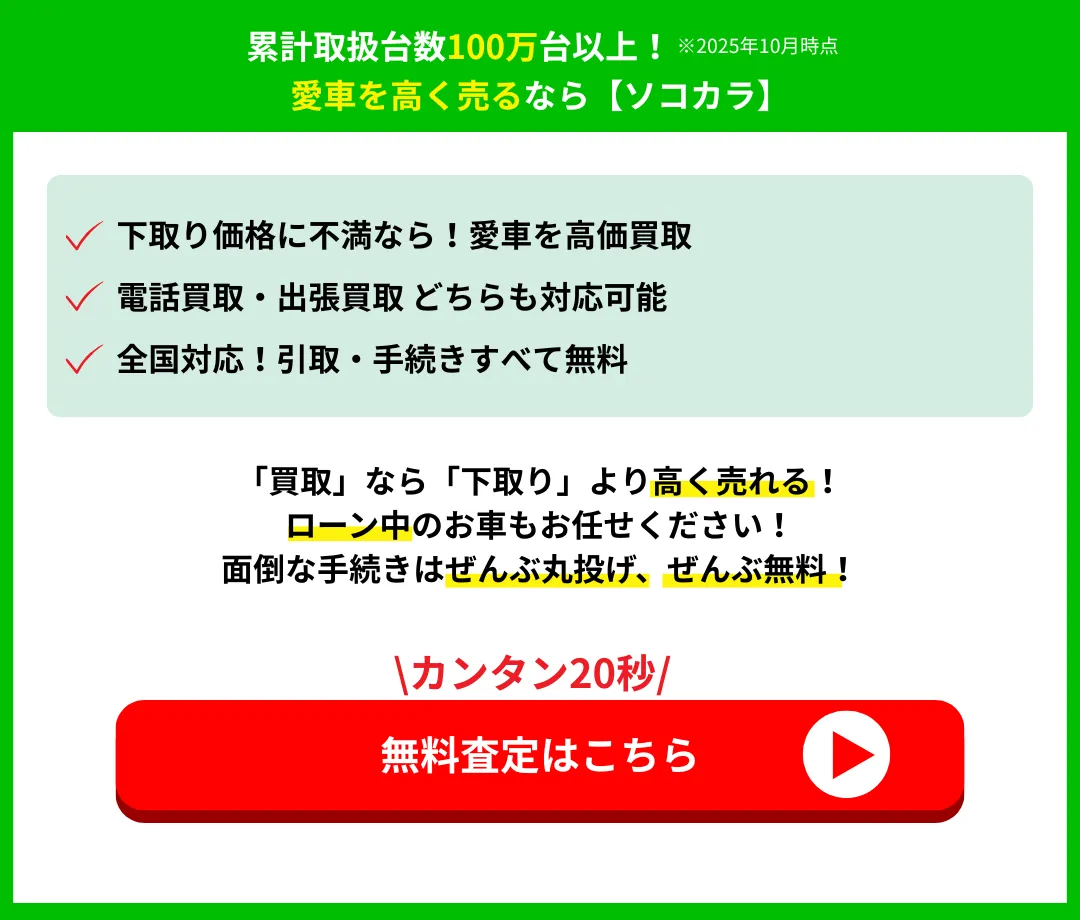
ブレーキパッドの役割
ブレーキパッドは車が安全に停止するために必要なパーツです。
ブレーキパッドはディスクブレーキに使われている部品で、ブレーキローターを挟み込むことで摩擦によって車を止めます。ブレーキローターを両側から挟み込むため、ブレーキパッドは2枚必要です。
ブレーキパッドがすり減ってしまうと、車を停止させることはできません。定期的な点検と交換は非常に重要です。
ブレーキパッドの交換方法
ブレーキパッドの交換方法は、以下のとおりです。
- ジャッキアップしてタイヤを外す
- キャリパーを外し古いブレーキパッドと新しいブレーキパッドを交換する
- ピストンを縮めて、キャリパー、タイヤの順で取り付ける
- ブレーキテストを行う
ブレーキパッドは安全に走行するために非常に重要なので、あまり部品交換に慣れていない方は無理をせず、ディーラーや修理工場などに持っていった方が無難です。
なお、個人が他人の車のブレーキパッドを交換すると、法律に違反する恐れがあります。安易に請け負わないよう注意しましょう。
ブレーキパッドの交換費用
ブレーキパッドの交換方法とともに重要なのが、交換にかかる費用でしょう。
部品代と工賃にわけ、それぞれ紹介します。
本体価格
ブレーキパッドは前輪と後輪で分かれて販売されています。前輪分の4つ、後輪分の4つで販売されているということです。
軽自動車の場合はそれぞれ7,000円ほど、普通乗用車のブレーキパッドはやや高くなり8,000円ほどです。高級車になると、1万円から2万円ほどする場合もあります。
汎用品を使えばさらに安く済ませられる可能性もありますが、安全性能を考慮するとメーカーが販売している純正パーツの方が安心です。
工賃
本体価格とは別に、ディーラーや修理工場で交換する場合には工賃がかかります。
工賃はそれほど高くはなく、前輪だけで1万円前後です。普段から懇意にしている整備工場などであれば、もっと安い工賃で交換してくれるかもしれません。
ブレーキパッドの交換時期の見極め方
ブレーキパッドは一定期間経ったら交換するという単純なものではありません。ブレーキの頻度や走行距離などに依存しているので、交換時期を見極めることが必要です。
ここでは、ブレーキパッドの交換時期を計るためのサインについて見ていきましょう。
1. ブレーキパッドの厚さを見る
ブレーキパッドの残りの厚さを見れば、交換時期を予測することができます。
通常ブレーキパッドは10mmの物が販売されています。
もしブレーキパッドの残りが6mm以上あればしばらく交換の必要はありません。5mm程度であれば、次の車検までには交換した方がよいでしょう。
3mm以下になっている場合には、交換時期になっていると判断できます。2mmもしくは1mm程度になっているのであれば、重大事故につながる恐れがあるため早急に交換が必要です。
2. ブレーキの音を確認する
ブレーキパッドにはパッドウェアインジケーターという部品が付いており、ブレーキパッドがすり減ってくると甲高い音がする設計になっています。ブレーキを踏んで甲高い音がする場合は、ブレーキパッドの寿命かもしれません。
ブレーキから異音が発生した場合には、ブレーキパッド以外にも問題が発生している恐れがあるので、できるだけ早く対処する必要があるでしょう。
3. 走行距離を確認する
一般的に走行距離1万kmでブレーキパッドが1mm減るといわれます。走行距離が5万kmを超えたのであれば、ブレーキパッドの交換時期が迫っている可能性があります。
走行距離とブレーキパッドの消耗が必ずしも比例するわけではありませんが、走行距離が増えてきたならブレーキパッドを目視して消耗具合を確認するとよいでしょう。
4. ブレーキフルードの残量を見る
ブレーキをしっかりかけるために、ブレーキフルードと呼ばれるオイルが使われています。ブレーキフルードの残量が少なくなっているのであれば、ブレーキパッドの交換時期かもしれません。
リザーバータンクを観察して、ブレーキフルードが減っているかどうかを定期的に確認しましょう。
ブレーキパッドの交換で安全なドライブを
ブレーキパッドはあまり目立たないとはいえ、安全に走行するうえで非常に重要な部品です。交換せずに放置しておくと、大事故につながる恐れもあります。
車検以外のときも細かく気を配って、寿命が近づいているサインを見逃さないようにしましょう。定期的な交換を心がけ、安全なドライブにつなげてください。


この記事の監修者
浅野 悠
中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.26
【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.30
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2024.09.10
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 故障車のお役立ちコラム
- 2024.10.17
ウォッシャー液が出ないときのための7つのチェックリスト
-
-

-
- 廃車のお役立ちコラム
- 2024.08.09
トラブル回避!陸運局で使える委任状・譲渡証明書の書き方【記入例付き】
-






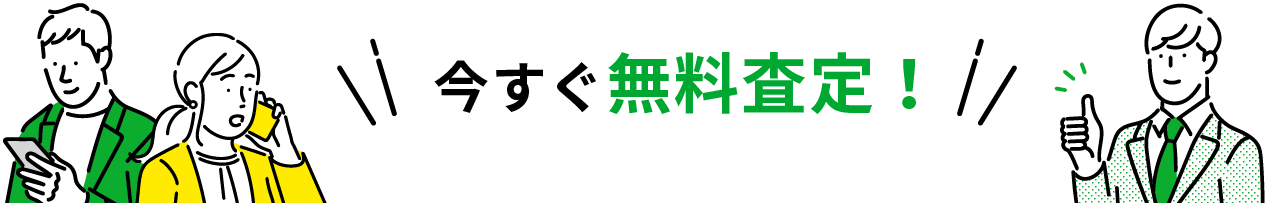




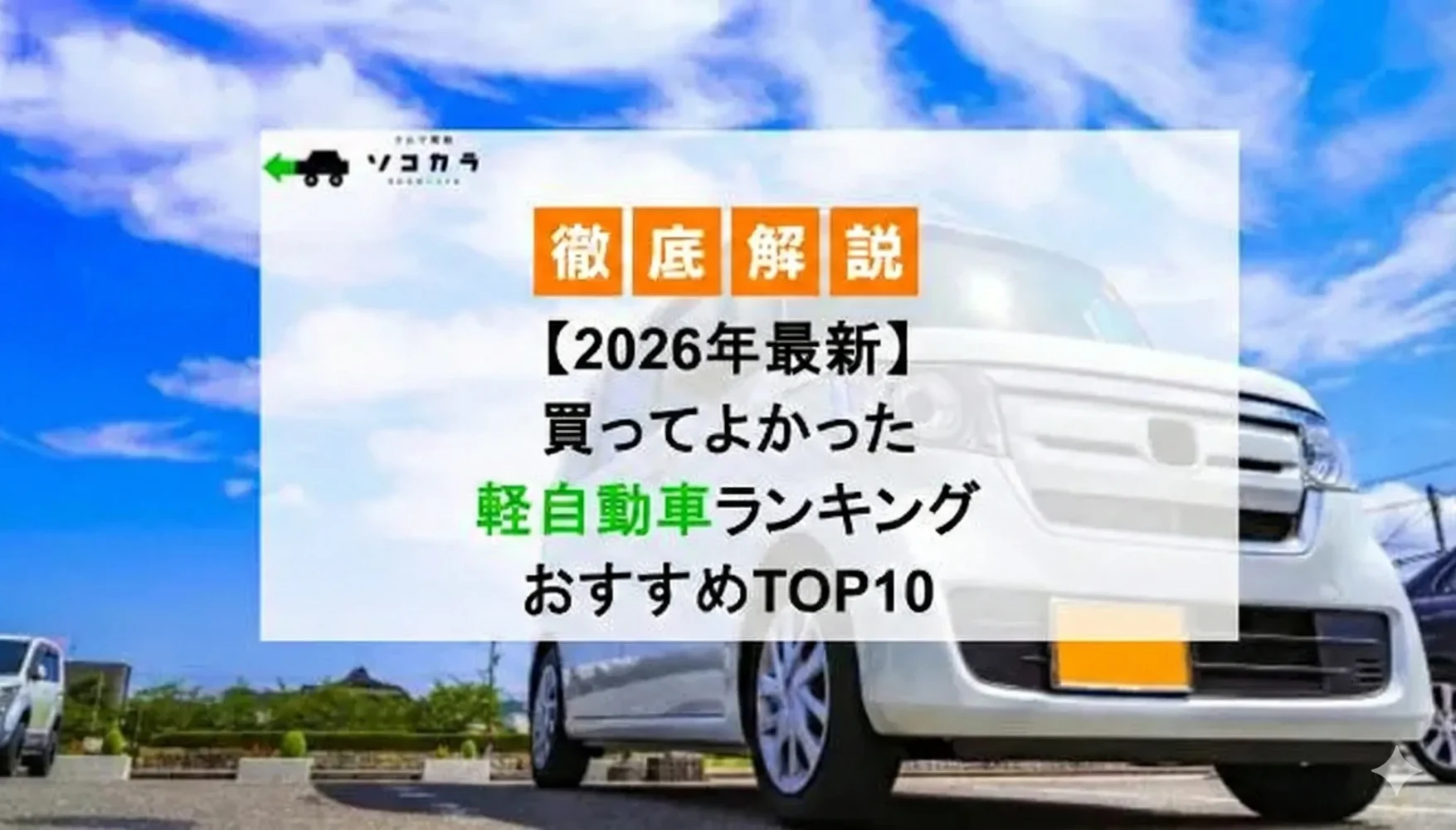


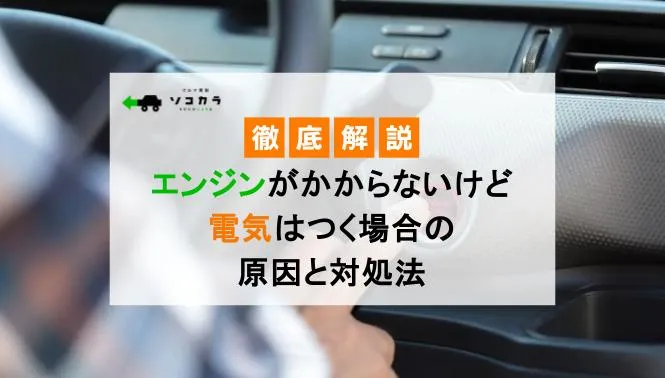
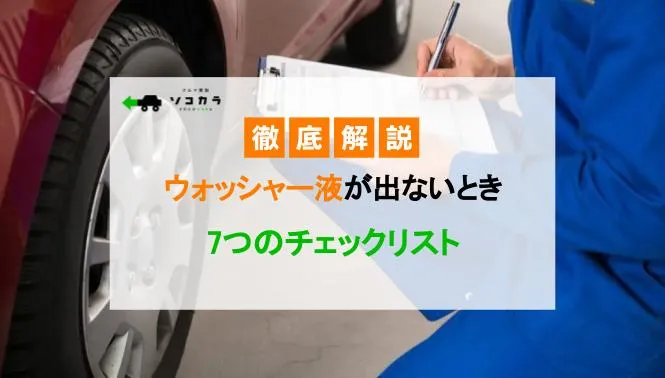
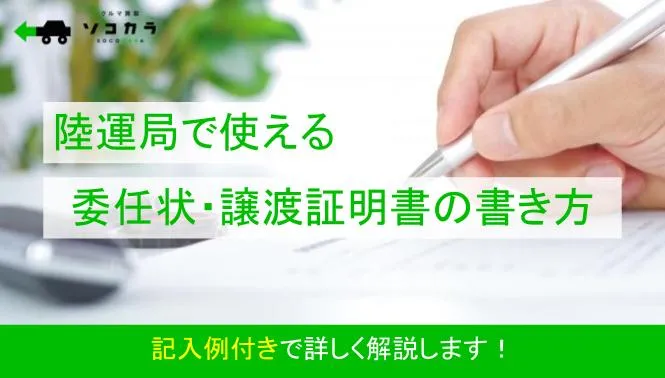

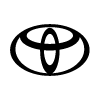
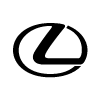
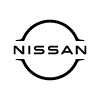

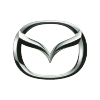


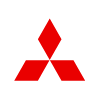









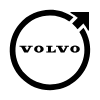

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870