- 2024.09.18
2400ccの自動車は税金が高い?2400ccと税金の関係を解説

「排気量が2,400ccの場合、支払うべき自動車税はいくら?」
「2,400ccの車検時にかかる自動車重量税はいくら?」
「なるべく税金の負担を減らしたいけれど、やるべきことは何だろう?」
2,400ccの自動車に対して、このような疑問をお持ちではありませんか?
2,400ccの自動車には主に2種類の税金が発生します。まず自動車税ですが、これは毎年4月1日時点での車の所有者に課せられる税金です。一方で自動車重量税は、車検を受ける際に、その車の重量に応じて計算されるものです。
さらに、車を持つということは、税金以外の出費も覚悟しなければなりません。具体的には、定期的な車検の費用や、毎月の保険代、ガソリンや駐車場の利用料など多岐にわたります。
今回は、2,400ccのエンジンを持つ車両について、所有する際にかかる具体的な税金について詳しく説明していきます。最後まで読むことによって2,400ccの自動車への理解が深まるため、ぜひご覧ください。
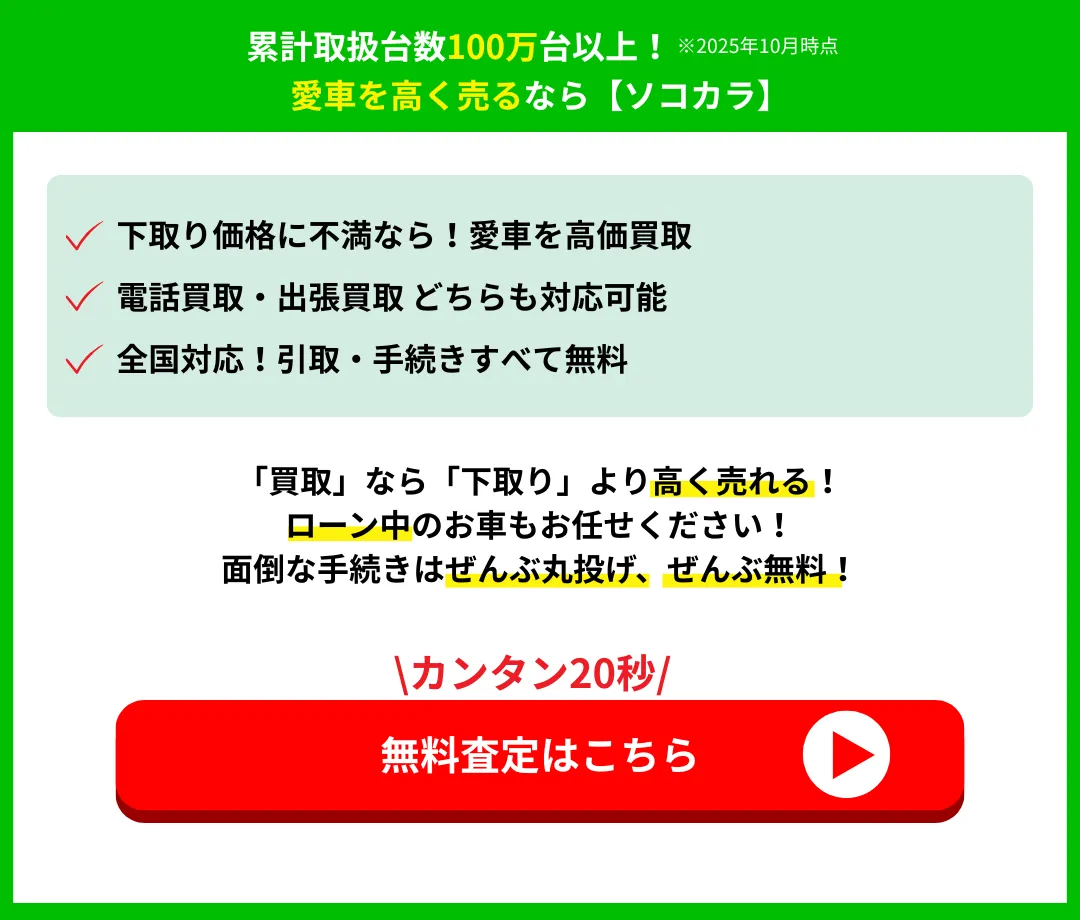
自動車にかかる税金の種類
自動車にかかる税金の種類を説明します。
- 自動車税
- 自動車重量税
- その他(環境性能割、消費税)
一つずつ詳しく見ていきましょう。
自動車税
自動車税の納付は、4月1日時点で自動車を所有していることが条件です。税額は下記によって異なります。
- 自動車の種類
- 自動車の用途
- 自動車の排気量
具体的な年間の税額は4月から翌年3月までの期間で算出されます。この税額は納税通知書を基にして、5月末までに支払うことが必要です。
ただし車を手放したり新しく購入した場合には、年間の税額がそのまま適用されるわけではありません。こういったケースでは、月割で計算された税額を納めることになります。
軽自動車は仕組みが若干異なります。課税されるのは軽自動車税という税金です。この税も4月1日を基準に、軽自動車を所有している人が対象となります。しかし、自動車税とは異なり、軽自動車税には月割という概念が存在しません。
そのため、年度途中で軽自動車を購入したとしても、その年度内に税を支払う義務は生じず、翌年度から課税が始まるという特徴があります。
自動車重量税
車両の重さに基づいて計算される自動車重量税は、自動車検査証を受け取るための手続きや、車両番号の指定を受ける際に必要です。自動車重量税は、郵便局で自動車重量税印紙を購入し、自動車重量税納付書に貼り付け納付します。
しかし、エコカーとして認定された自動車には減税措置があります。低排出ガス車や高い燃費性能を持つ車両に対してはエコカーの環境性能が優秀であることを評価して課税額が軽減されます。
その他(環境性能割、消費税)
そのほかには環境性能割と消費税の2つが挙げられます。
環境性能割
環境性能割は、持続可能な社会を目指して地球環境に配慮した政策として、2019年10月から日本で施行されました。この税制は、従来の自動車取得税が廃止され、その代わりとして導入されています。
環境性能割は、車両の燃費性能に基づいて税率が変動する仕組みを持っており、省エネ性能の高い車ほど税金が少なくなるエコカー優遇の考え方を採用しています。
マイカーに関しては、税率が以下のように設定されています。
- 非課税
- 1%
- 2%
- 3%
燃費基準をクリアした車両は非課税となる可能性があるでしょう。一方、軽自動車については非課税・1%・2%の3つの段階があります。これにより、環境負荷を軽減する努力を奨励し、自動車産業において持続可能な技術革新を促す狙いがあるのです。
税金の計算方法はシンプルで、「自動車の通例の取得価格×税率」により求められます。つまり、燃費効率が高い車を選べば、その分税負担が軽減されるため、新たに車を購入する際の大きなインセンティブとなるでしょう。
消費税
日本における消費税は2024年8月現在で10%です。この税は車両本体だけでなく、カーナビやフロアマットといった自動車の付属品にも適用されます。
車を購入する際には、これらすべての費用に対する消費税が含まれるため、全体の出費に影響を与えます。このため、購入を予定している方は、実際に支払う総額がどの程度になるのかを事前にしっかり把握しておくことが重要です。
2400ccの自動車にかかる税金
2400ccの自動車にかかる税金を解説します。
- 2400ccの自動車税
- 2400ccの自動車重量税
詳しく見ていきましょう。
2400ccの自動車税
自動車税は、毎年4月1日に車を所有している人に対して課される地方税です。この税金が発生するのは、車を「所有している」こと自体が条件となっているため、たとえ車を使用していなくても、また車検が切れている場合でも支払い義務があります。
一方で、カーリースを利用している場合の負担者は異なります。リースカーの場合、所有権はリース会社にあるため、それに応じて発生する自動車税もリース会社が支払う仕組みになっています。つまり、リース利用者は、すでにリース料に自動車税が含まれているため、個別に自動車税を支払う必要はありません。
排気量別の自動車税の金額は下記の通りです。
| 排気量 | 12年まで | 13年経過後 | |
| ~2019/9/30に新車登録 | 2019/10/1~に新車登録 | ||
| 1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | 約33,900円 |
| 1,000cc~1,500cc未満 | 34,500円 | 30,500円 | 約39,600円 |
| 1,500cc~2,000cc未満 | 39,500円 | 30,500円 | 約39,600円 |
| 2,000cc~2,500cc未満 | 45,000円 | 43,500円 | 約51,700円 |
| 2,500cc~3,000cc未満 | 51,000円 | 50,000円 | 約58,600円 |
| 3,000cc~3,500cc未満 | 58,000円 | 57,000円 | 約66,700円 |
2400ccの自動車にかかる自動車税は、通常年間45,000円です。ただし、2019年10月1日以降に新規登録された車両については、税額が軽減されて43,500円になります。これに対し、登録から13年以上経過した古い車の場合、重課の対象となり、税額はおおよそ51,700円に増加します。
古い車の方が自動車税が高額になることを覚えておくと良いでしょう。また、ディーゼル車はガソリン車とは重課の適用が異なるため、注意が必要です。
2400ccの自動車重量税
自動車重量税は、車両の重さに基づいて課される国の税金であり、車検時に支払う必要があります。車の重量を確認するには、車検証に記載された車両重量を参照してください。ただし、車両総重量と混同しないよう注意が必要です。
重さごとの税額は、以下の通りです。
| 重量 | 12年まで | 13年経過後 | 18年経過後 |
| 0.5t | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| 〜1t | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
| 〜1.5t | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| 〜2.0t | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
| 〜2.5t | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
| 〜3.0t | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
| 軽自動車(重さは問わない) | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
参照:国土交通省
上記からも分かるように、自動車重量税は、13年・18年経過すると金額が上がります。
購入から10年以上経過で税金が上がる?
自動車税が増額される時期は、ガソリン車とディーゼル車で異なる基準が設けられています。
ガソリン車の場合、初めて登録されてから13年が経過した時に税金が上がります。一方、ディーゼル車は11年後に増税されます。この違いは、ディーゼル車がガソリン車よりも環境に悪影響を及ぼす窒素酸化物を多く排出することに起因するでしょう。
税金が上がる際のカギとなるのが「新規登録から何年経ったか」です。新車を購入した場合は、その時点からカウントが始まりますが、中古車の場合は前のオーナーが使用していた期間も考慮しなければなりません。つまり、中古車を購入する場合、車自体の初登録年を確認することが重要です。
この新規登録の年度は、車検証(自動車検査証)の左上にある初年度登録年月日を見れば確認可能です。中古車を購入する際には、これをチェックして車両の登録年数を把握し、将来的な税金負担を予測することが大切です。
自動車税の増額がいくらか分かる早見表
自動車税が上昇するタイミングが把握できたところで、その具体的な増額について確認してみましょう。
増税の目安として以下の内容があります。
- 通常の自動車税は約15%の増加
- 軽自動車税はおおよそ20%の増加
ここで注目すべき点としては、車の排気量が大きくなるほど税金の増額も大きくなることです。具体的な例を挙げると、1,000ccを超える1,500cc以下の自動車では、増税額は34,500円から39,600円に上がり、その差額は5,100円です。
一方で、6,000ccを超える車の場合、増税額は111,000円から127,660円に上がり、差額は11,660円となります。このように、排気量の大きな車ほど、税負担が重くなるのが特徴です。
| 総排気量 | 13年未満 | 13年以降 |
| 660cc(軽自動車) | 10,800円 | 12,900円 |
| 1,000cc超1,500cc以下 | 34,500円 | 39,600円 |
| 1,500cc超2,000cc以下 | 39,500円 | 45,400円 |
| 2,000cc超2,500cc以下 | 45,000円 | 51,700円 |
| 2,500cc超3,000cc以下 | 51,000円 | 58,600円 |
| 3,000cc超3,500cc以下 | 58,000円 | 66,700円 |
| 3,500cc超4,000cc以下 | 66,500円 | 76,400円 |
| 4,000cc超4,500cc以下 | 76,500円 | 87,900円 |
| 4,500cc超6,000cc以下 | 88,000円 | 101,200円 |
| 6,000cc超 | 111,000円 | 127,600円 |
※新規登録が2019年9月30日以前
※ディーゼル車の場合13年未満の部分が11年未満・13年以降の部分が11年以降
※用途区分は自家用乗用車
引用元:総務省
自動車重量税は13年・18年超で重課される
自動車の税金には自動車税以外にも、自動車重量税があります。時が経つにつれて税金の負担が増え、特に13年目と18年目で増加します。
購入から13年が経過すると、この税金は約39%増加し、さらに18年が経過すると増加幅は約53%にも達します。これは、車両の使用を長期間継続することにより、環境への負荷や安全性の観点から新しい車両への乗り換えを促進するための措置と捉えることが可能です。
具体的な重量税の金額は下記の表をご参照ください。
| 重量 | 12年まで | 13年経過後 | 18年経過後 | |
自家用車(軽自動車以外) | 0.5t | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| 〜1t | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 | |
| 〜1.5t | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 | |
| 〜2.0t | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 | |
| 〜2.5t | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 | |
| 〜3.0t | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 | |
| 軽自動車 | 660kg | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
参照:国土交通省
自動車の重量については、車検証に記載されている「車両重量」が基準となります(総重量ではありません)。例えば、エンジンの排気量が2000cc超から2500cc以下であり、車両重量が1.5トンの車の場合、課される税金に変化があります。
具体的には、自動車税が45,000円から51,700円に、自動車重量税が24,600円から34,200円への引き上げです。この結果、税金の合計は、前年よりも16,300円増加します。
多くの人が自動車を新規登録から13年目で手放す理由として、このように自動車税と自動車重量税が上昇することが挙げられます。これにより、自動車の維持費が大きな負担となり、一部の車主にとって買い替えを検討する要因となるのです。
2400ccの自動車が向いている人
2400ccの自動車が向いている人について説明します。
- 自動車のパワーが好きな人
- アウトドアやドライブが好きな人
詳しく見ていきましょう。
自動車のパワーが好きな人
特にエンジン出力にこだわる方には、2400ccクラスの自動車がぴったりです。これらの車輌は高いエンジンパワーを備えており、スムーズな加速や力強い走行体験を提供します。そんな性能が、ドライビングを心から楽しむ人々を惹きつける理由です。
さらに、高速道路でも快適に長時間運転できるため、ストレスなくドライブを楽しむには最適です。ドライブを趣味としている方や、週末に家族でちょっとした旅に出かけるのが好きな人々には2400ccクラスの車が理想的でしょう。
アウトドアやドライブが好きな人
アウトドア活動や長いドライブを趣味とする方々にとって、車選びは非常に重要です。特に排気量の大きな自動車を選ぶと、多くのメリットが得られます。高速道路での長距離運転において、これらの自動車は驚くべき性能を発揮します。合流時や追い越しの際に、パワフルな加速が求められますが、排気量が大きい自動車ならではの力強さで簡単にこれをクリアし、運転者に安心感を提供するでしょう。
また、長時間の運転では運転者のストレスが溜まりやすいですが、2400ccクラスの自動車のエンジンは効率的に動作します。特に登り坂ではアクセルを深く踏み込む必要がなくてもスムーズに走行でき、エンジン音が静かなため、心地よいドライブが可能です。
ストレスが軽減されるので、ドライバーは体力に余裕を持って保存でき、目的地でのアウトドア活動や観光をより楽しむことができます。加えて快適な車内環境は乗客にも影響を与えます。静かなエンジン音とともに、広々とした車内スペースは同乗者にとっても快適でしょう。
自動車の税金を負担に感じる場合の対処法
自動車を保有する際には、自動車税が大きな経済的負担となることがあります。そこで、自動車税の負担を軽くするためのいくつかの有効な方法を紹介します。
- 軽自動車・エコカー・ハイブリッドカーに乗り換える
- 売却する方向も検討する
詳しく見ていきましょう。
軽自動車・エコカー・ハイブリッドカーに乗り換える
自動車税を削減したいのであれば、軽自動車やエコカー、そしてハイブリッドカーへの乗り換えが選択肢として挙げられます。これらの車種は環境に優しいことから、税金が低めに設定されています。
軽自動車は、そのコンパクトな設計と優れた燃費が魅力的です。一方、エコカーやハイブリッドカーは先端技術を駆使し、燃料効率を一層高めることで、燃料代の節約にも貢献します。
ただし、乗り換える際の購入費用がかかるデメリットもあります。したがって、将来的な維持費削減と現在の予算のバランスをよく考えて選ぶことが重要です。購入時には燃費だけでなく、保険料や修理費用なども含めて総合的にコストを比較することが必要です。
売却する方向も検討する
車を売却することを検討するのは、賢明なオプションの一つと言えるでしょう。車を持つことで発生する費用には、税金だけでなく、駐車場代・保険料・定期的な点検や修理にかかるコストなど多岐にわたります。
車を売ることで、これらの経済的負担から解放されるだけでなく、売却による収入を得ることができ、さらに税金の悩みからも解放されます。売却に際しては、まず必要な手続きや各ステップをしっかり理解しておくことが大切です。
インターネット経由で複数の業者に査定を依頼し、最も有利な条件を見つけるために交渉することも考慮すべきポイントです。車を手放すと同時に、公共交通機関の利用やカーシェアリングサービスの活用を検討することで、より合理的で新しい生活スタイルを探求するチャンスが生まれます。こうした移動手段の見直しによって、さらなる経費節約にもつながるでしょう。
まとめ
2,400ccの自動車を所有している場合、その自動車税は45,000円です。ただし、自動車重量税は車体の重量に基づいて計算されるため、それぞれの車両によって金額が異なります。具体的な金額については、車両重量に応じた税額表を確認しましょう。
自動車の維持にはさまざまな費用がかかります。車検や保険料、燃料費、さらには駐車場代など、多岐にわたる支出が発生するでしょう。
また、車両が一定の年数以上になると、環境対策として追加の税金が課される制度があります。具体的には、自動車税であれば13年、自動車重量税では13年と18年を超えた場合に増税される仕組みです。
この記事を通じて、「2,400ccの自動車の税金は予想より高い」と驚かれる方もいるでしょう。そこで税金や維持費を抑えたい方は、思い切って車を手放してみてはいかがでしょうか。
車を手放したいと思った際は、ぜひ廃車買取業者にご相談ください。
クルマ買取「ソコカラ」は、10年以上経った古い車でも、10万km以上走った車でも買取しています。廃車の買取事例も多数で、廃車にまつわる手続きも無料代行いたします。
無料査定しているので、ぜひお気軽にご相談ください。


この記事の監修者
浅野 悠
中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.26
【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.30
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.22
【2026年最新】軽自動車を白ナンバーにする全知識!今選べる種類・費用・手続き・デメリットまで徹底解説
-
-

-
- 故障車のお役立ちコラム
- 2024.11.01
ハンドルを切ると異音がする原因と対処法について詳しく解説!
- ハンドル
- 異音
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.02.05
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-






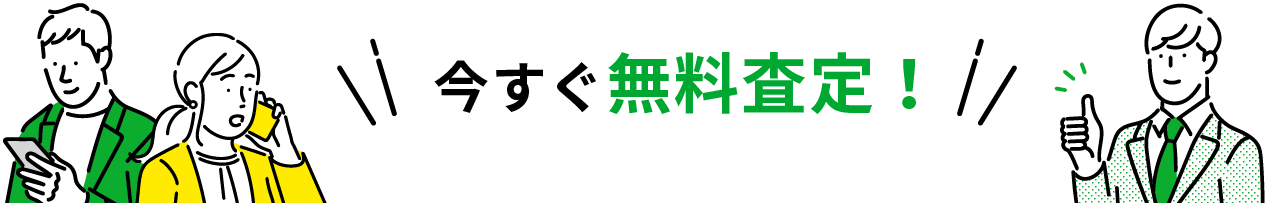




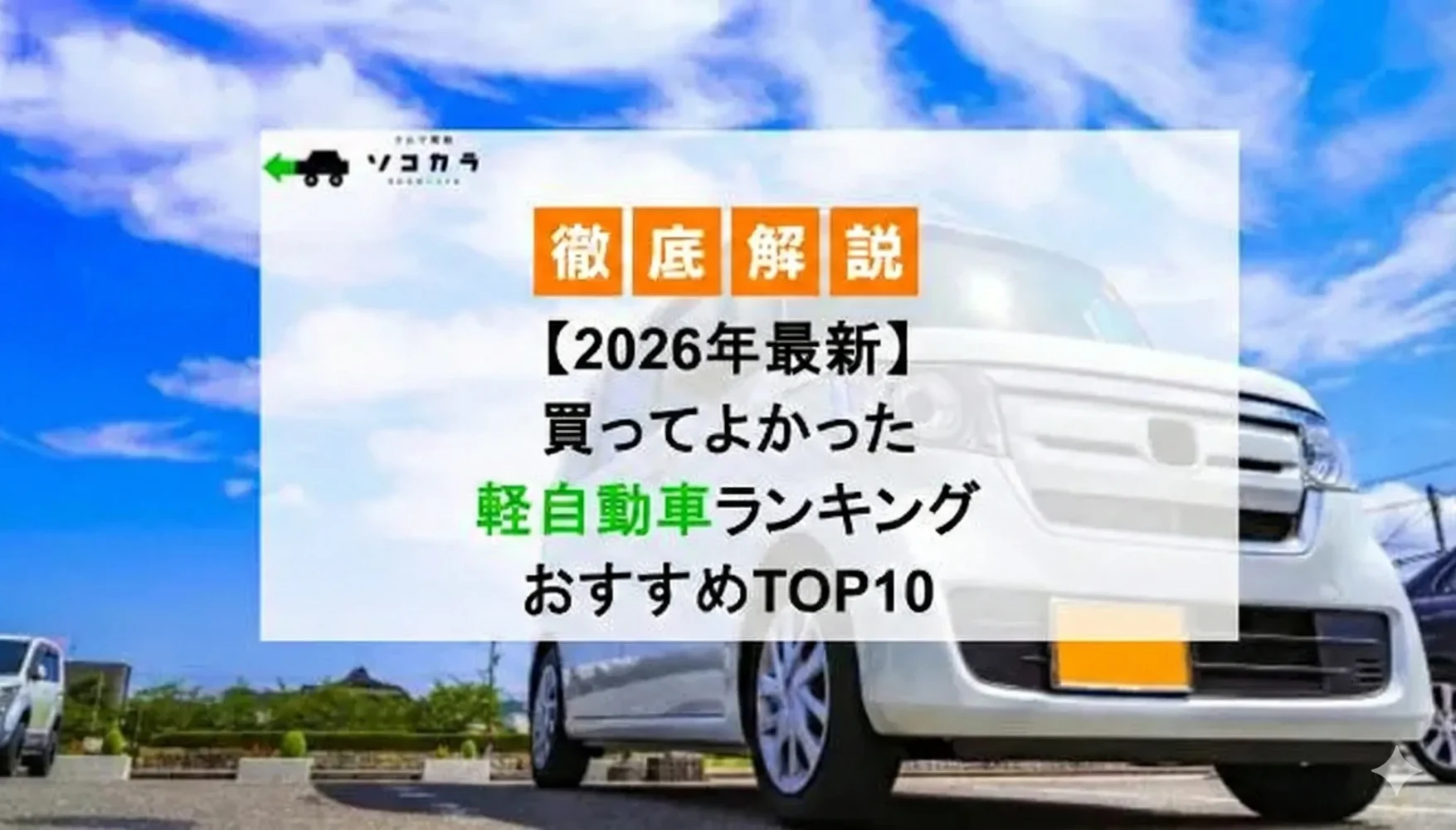


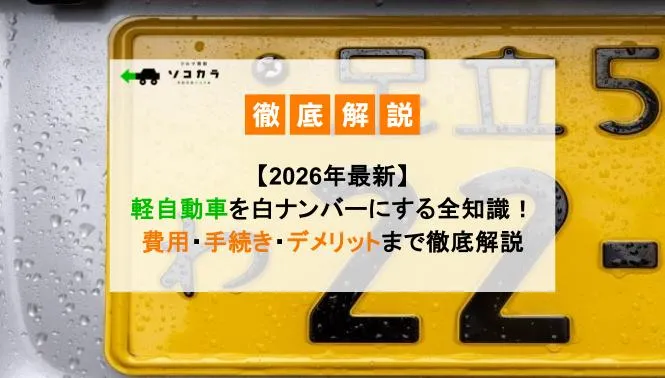

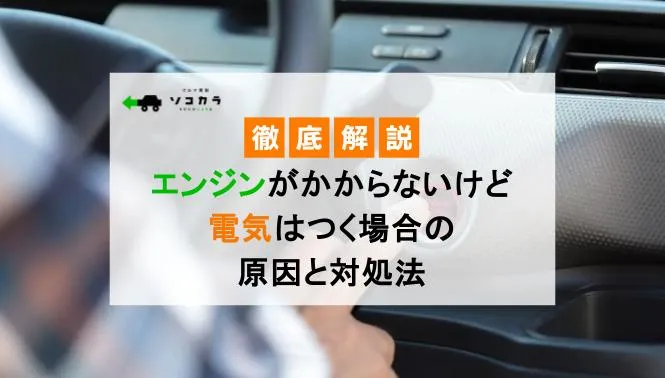

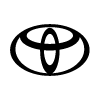
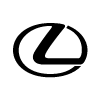
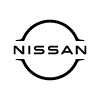

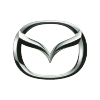


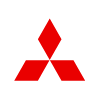









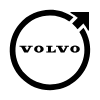

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870