- 2020.11.04
そのハンドルの回し方、正しいですか?運転を変えるハンドルの選び方

自動車教習所で習ったハンドルの持ち方や回し方、覚えていますか?
愛車のハンドルを好みのものにカスタマイズしていますか?
免許を取ってから時間が経過すると意識することもなくなりますが、家族や友人・恋人がヒヤヒヤしながら同乗するか安心して同乗できるかは、ハンドルの握り方や回し方ひとつにかかっていると言えます。
また、車にこだわりがある方は、ハンドルを自分の好みのものにカスタマイズされていますよね。付け替えることで見た目がかっこよくなるだけではなく、操作性の向上も期待できます。今回は、ハンドル操作の基礎とハンドルを交換するメリット・デメリットをご紹介しましょう。
ちなみに「ハンドル」という呼び名は和製英語であり、正式名称は「ステアリングホイール」ですが、今回は分かりやすいように「ハンドル」という呼び方でご説明していきます。
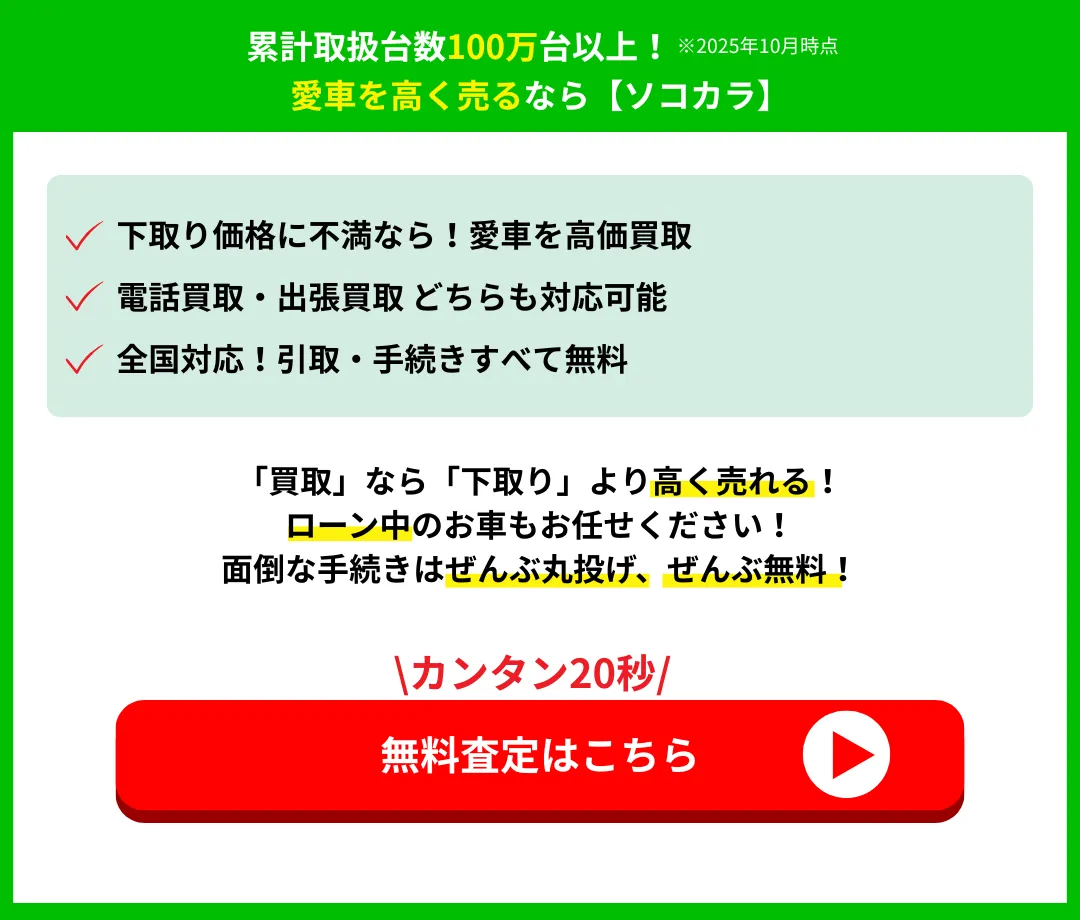
ハンドルの握り方
まずは基礎の基礎、ハンドルの握り方をおさらいしましょう。
上手なハンドル操作のためには、ハンドルをアナログ時計に見立て、【9時15分】の位置を、必ず【両手】で握ることがポイントです!
自動車教習所で「10時10分の位置」と指導された方もいらっしゃるかもしれません。これは、ハンドルの操舵をアシストするパワーステアリングが車に装備されていなかった時代の名残です。当時の車はハンドルが重かったため、最も力が入りやすい10時10分の位置でハンドルを握るのが主流とされていましたが、現在はパワーステアリングが標準で装備されているため、力をいれなくともハンドル操作が可能となりました。また、肘が締まり、手の位置が安定することでキックバック(ハンドルの跳ね返り)があっても対応しやすく、腕や肩もリラックスして運転できることから9時15分の位置で両手で握ることが推奨されているのです。
ただし、ハンドルの形状によっては9時15分のポジションを保持できない場合もありますので、臨機応変な対応が必要です。
ハンドルの回し方
次にハンドルの回し方についてです。正しいハンドル操作は、運転が上手に見えるというだけでなく、危機回避にも極めて役立つ技術です。
一般的にハンドルの回し方には【クロスハンドル】と【送りハンドル】の2種類があります。その違いについてご紹介しましょう。
クロスハンドル
自動車教習所で教えてもらう、最もオーソドックスなハンドル操作がクロスハンドルです。交差点の右左折やUターン、駐車場での切り返しなど、低速で大きくハンドルを回す際に用いられます。
左折の場合だと、9時15分の位置で握っている状態からそのままハンドルを左へ回し、左手が6時から7時くらいの位置に来たところで一旦左手を離します。そして右手とクロスして左手で1時の位置に持ち替え、左に回しながら、右手を離して3時の位置に戻します。
クロスハンドルはオーソドックスな回し方で初心者でも操作しやすいメリットがありますが、一瞬片手運転になる時間がある点と、途中で腕がクロスするため少し窮屈な体勢になる点、また正しい運転姿勢が乱れる点もデメリットと言えます。
送りハンドル
送りハンドルは、ある程度のスピードを維持したまま急なカーブを曲がる際に用いられ、プッシュプルハンドルとも呼ばれます。
左折の場合だと、9時15分の位置で握っている状態から右手でハンドルを回し、左手は滑らせて12時の位置へ迎えに行きます。12時の位置で両手が揃ったら、左手でハンドルを回し、右手は滑らせて6時の位置へ迎えに行きます。6時の位置で両手が揃ったら、右手で回し、左手は滑らせます。
送りハンドルはレースなどで用いられる回し方ですが、大きく曲がりたい時や素早くハンドルを回したい時には不向きであり、運転に慣れていないドライバーには習得が難しいため、自動車教習所では推奨されていません。ただ、常に両手でハンドルが握られている状態であり、腕も大きく動かさずに微調整が可能というメリットがあります。
NGなハンドル回し方
ここで絶対にやってはいけないハンドルの操作もご紹介しておきましょう。
片手ハンドル
その名の通り、片手だけでハンドルを回す運転方法です。
片手ハンドルでは、確実なハンドル操作ができないばかりかキックバックのように車がふいに挙動を乱した場合に素早い操作ができないため危険です。
内かけハンドル
内側から手を掛けて握り、ハンドルを回す運転方法です。
簡単に大きくハンドルを回すことができ、クセになる方も多いようですが、片手ハンドル同様に素早い操作ができない上に、事故に遭った時に手がハンドルに引っ掛かり、大怪我に繋がる恐れもあるため危険です。
何気なくやってしまっている場合もあるかもしれませんが、非常に危険ですのでこれを機に矯正してみてください。
操作性をUPさせるハンドル交換のメリット・デメリット
上手な運転にはハンドル操作が鍵であることはお分かりいただけましたか?
ハンドルは、各メーカーごとにグリップの太さや外径、デザインが異なり、同一メーカーであっても車種ごとに専用の設計があるほど、実はこだわりのパーツなのです。そのため、純正のものでも機能も見た目も十分に満足できるものになっています。
ではなぜ、ハンドルをカスタマイズする方がいるのでしょうか?
ハンドル交換のメリット
ハンドル交換と一言で言っても、どこをどう変えるのかによってメリットは異なります。具体的にどう変えればどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
- 素材を変える
従来のものはビニールやウレタン素材が多いですが、触り心地がイマイチだったり、長時間運転していると汗で滑りやすくなったりします。素材をレザーに交換すると滑りづらくなり、スウェードに交換すると握る力があがるというメリットがあります。
- 大きさを変える
一般的なハンドルは、直径350㎜に設計されています。その基準より外径が大きいハンドルに交換すると軽い力で回すことができるため腕が疲れにくくなり、逆に外径が小さいハンドルに交換すると腕を動かす量が少なくなるため素早いハンドル操作が可能になるというメリットがあります。
- グリップの太さを変える
女性の手と男性の手は大きさが違いますよね。つまり、握りやすいと感じるグリップの太さもそれぞれ違うのです。大きい手の方には太めのグリップの方が握りが安定し、力が入れやすく疲れにくいとされています。ただ、小さい手の方には太いグリップだと手が滑ったり、握りが安定しないため運転しにくいと感じるようです。実際に握ってみてしっくりくる太さのものを選ぶことで操作性が向上するというメリットがあります。
ハンドル交換のデメリット
メリットがあれば必ずデメリットもあるものです。ハンドルを好みのものにカスタマイズする際は、このデメリットもきちんと理解しておく必要があります。
- 安全性の低下
標準装備のハンドルにはエアバックが付いていることが多いですが、社外品にはエアバック付きのハンドルが少なく、選択肢が極端に狭まります。エアバックがないハンドルだと事故に遭った際に衝撃を緩和することができないため、安全性が低下してしまいます。
交換の作業中にエアバックが爆発し、命にかかわることもあるためエアバック付きのハンドルを外す作業はプロに任せることを推奨します。
- 任意保険の保険料UP・特約取り消し
エアバック割引などが適用されている任意保険に加入している場合、エアバックがない社外品ハンドルに交換すると保険料に影響するため、必ず保険会社に届け出なければいけません。特約が取り消しになったり、保険料があがる可能性もあることを理解しましょう。
- 事故発生時の保険料減額
万が一、社外品への交換を保険会社に届け出ずに事故に遭った場合、保険料が減額されたり、保険が下りないという最悪な状況になる可能性もあります。必ず保険証書を見直したり保険会社へ問い合わせを行いましょう。
- 車検に通らない可能性有
ハンドルを交換すること自体は違法ではありませんので、基本的に車検を通すことは可能です。ただ、エアバックが標準で搭載している車のハンドルをエアバックのないものに交換するとインジケーターランプが点灯・点滅したままになるため車検が通りません。特殊な対策をする必要があります。また、外径が小さいハンドルでメーターに被って目視できない場合、運転に支障があると判断され車検に通らないこともあります。また、ハンドル中央のホーンボタンにラッパのマーク(シールでOK)がなければ車検は通りません。せっかくお洒落なハンドルに交換したのにシールを貼るのは気が進みませんが、忘れずに!
- 便利な機能が使用不可
最近の標準装備のハンドルには、オーディオやカーナビ、クルーズコントロール等を制御するボタンが設置されています。これらは、交通事故の回避や被害を小さくするために装備されていますが、社外品に交換するとその便利な機能を使用することができなくなります。安全をわざわざ手放すことになるのです。
- 査定額が減額の可能性有
いつか愛車を手放すことになった時、ハンドルが準製品でなければ査定評価が低くなる可能性も高いです。
まとめ
今回は、正しいハンドル操作についての説明とハンドル交換のメリット・デメリットについての説明でした。
安全安心な運転はハンドルの正しい持ち方や回し方によって生まれます。車の運転は瞬間瞬間で状況が変わり、正確なハンドル操作が重要になります。間違った持ち方は事故やケガに繋がりますのですぐに直した方がいいでしょう。
また、ハンドルの交換は操作性を向上させるうえに、ドライブの楽しさを倍増させてくれるというメリットがありますが、その分リスクもあります。メリット・デメリットをきちんと理解したうえで、愛車とのカーライフを楽しんでください。


この記事の監修者
浅野 悠
中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.26
【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.30
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.22
【2026年最新】軽自動車を白ナンバーにする全知識!今選べる種類・費用・手続き・デメリットまで徹底解説
-
-

-
- 廃車のお役立ちコラム
- 2024.08.09
トラブル回避!陸運局で使える委任状・譲渡証明書の書き方【記入例付き】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.02.05
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-






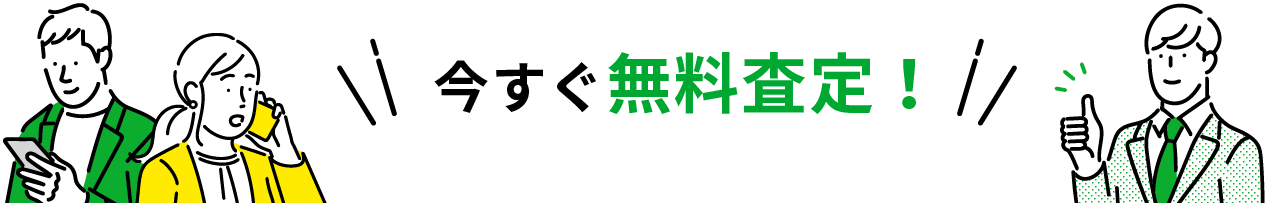




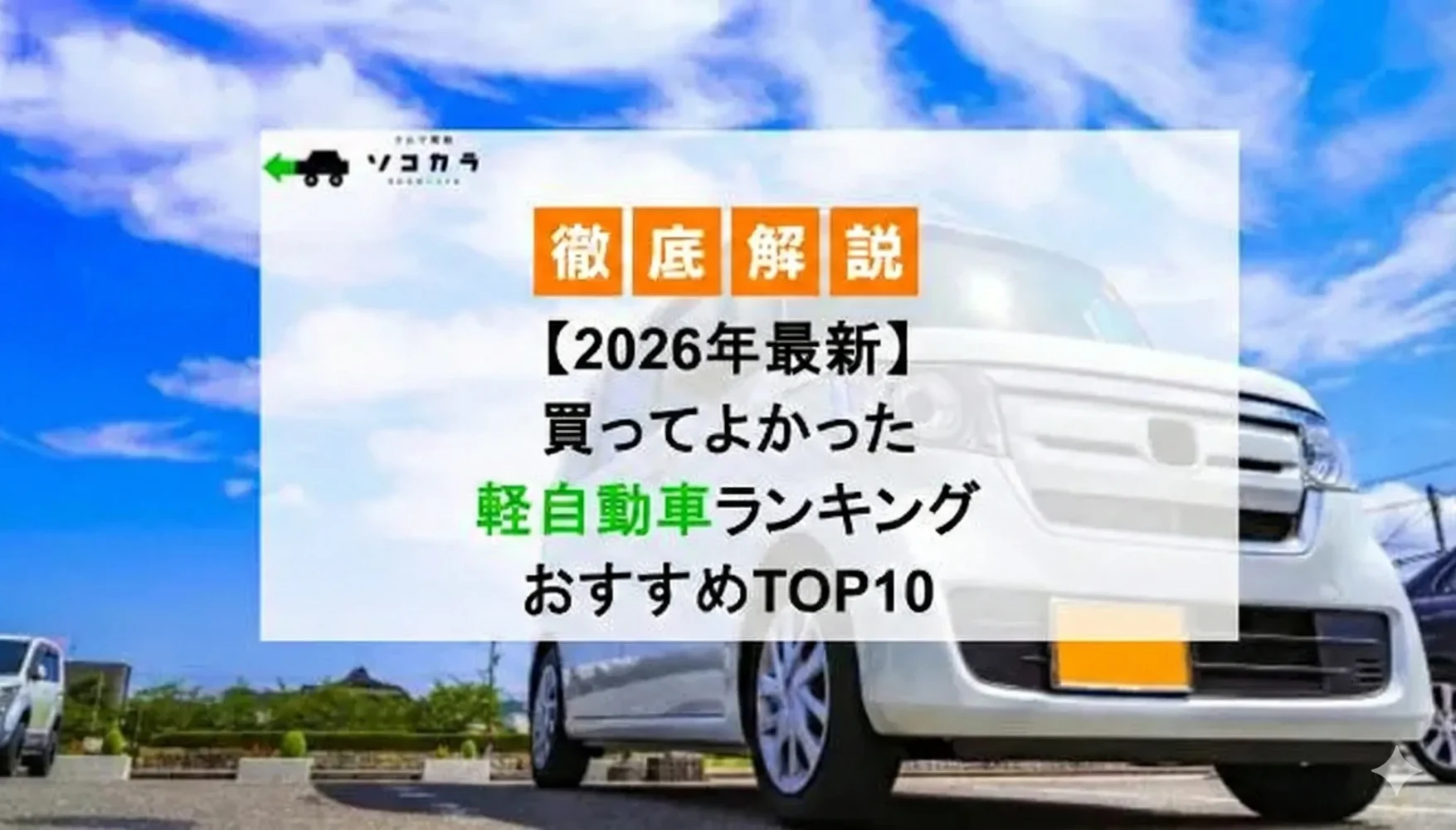

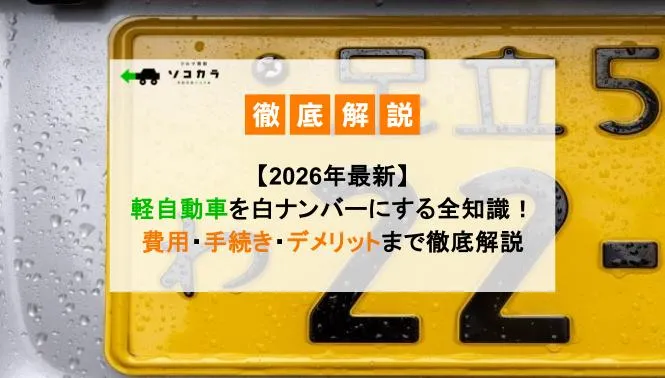
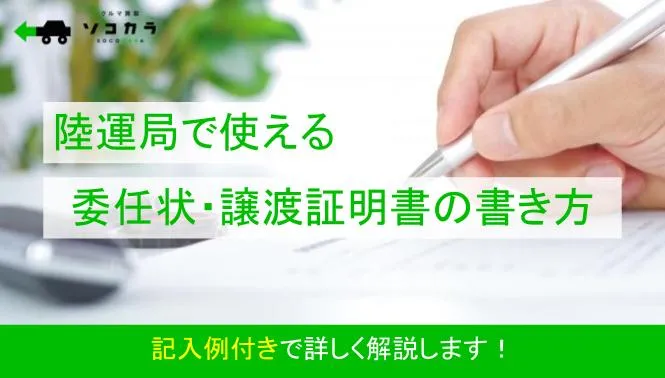

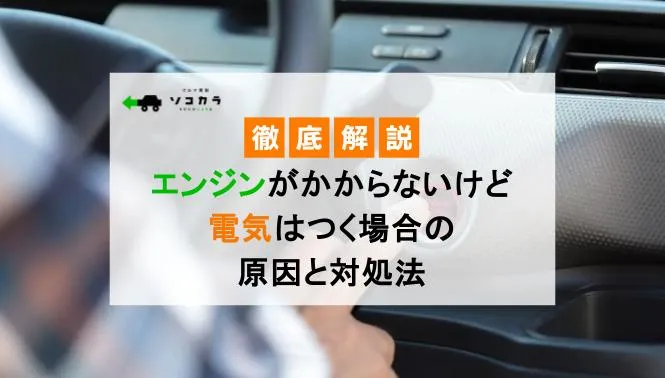

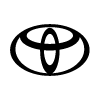
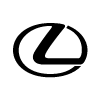
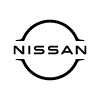

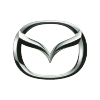


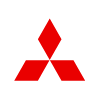









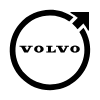





 0120-590-870
0120-590-870