- 2024.09.12
最低地上高が原因で車検が通らない?測定方法や注意点を徹底解説

街を走る車の多くは、地面との間に一定のスペースを確保しています。このスペース、正式には「最低地上高」と呼ばれ、車がスムーズに走行するための重要な要素です。
平坦な道ばかりではない街中では、縁石に乗り上げたり、坂道を駆け上がったりすることも。こうした場面で車体が地面に擦れてしまうと、車検に通らなくなるだけでなく、大切な車体の部品が損傷してしまうリスクもあります。しかし、どこを基準に測ればいいのか、意外と知られていません。
そこで今回は、最低地上高の基礎知識から、適切な測定方法、そして車検に通らない場合の対処法まで、詳しく解説していきます。
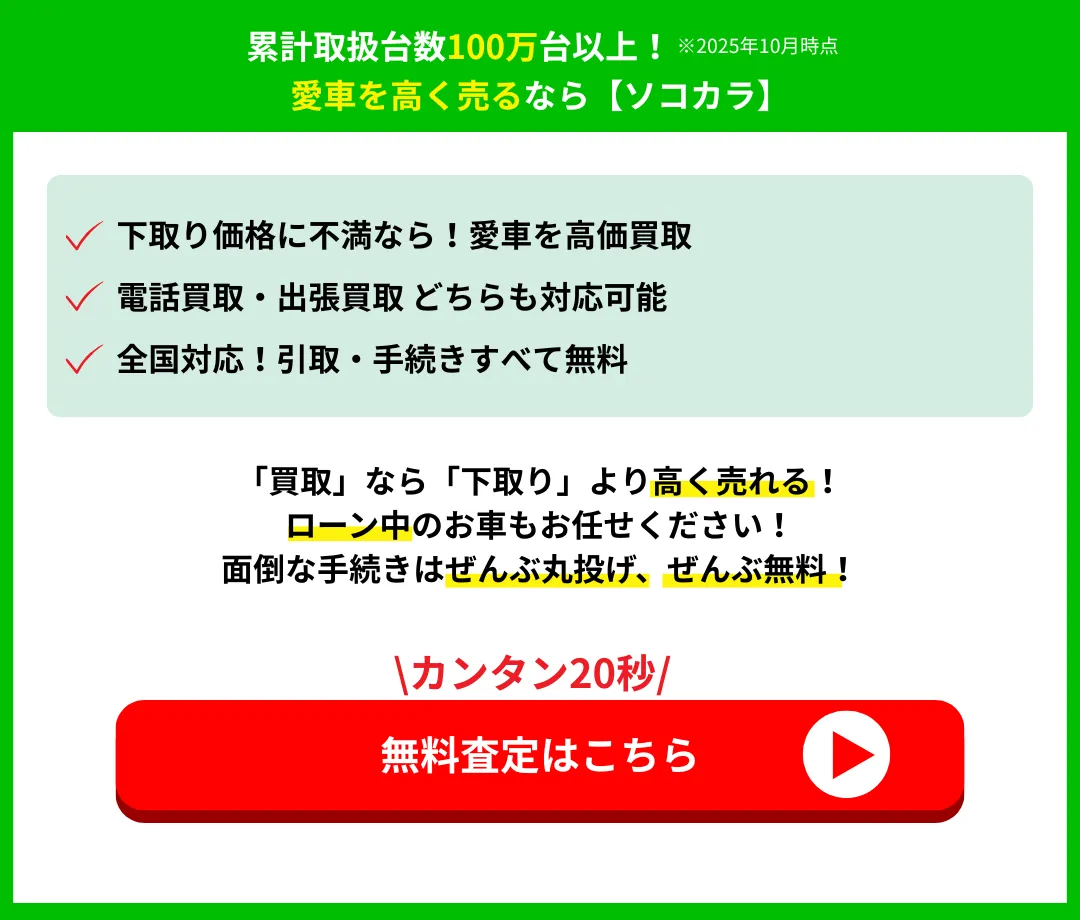
車検に通る最低地上高は何cm?
最低地上高とは、法律で決められた守るべき車高のことです。日本では、道路運送車両保安基準という法律の第3条、細目告示第2節85条によって、車の最低地上高が9cmと定められています[注1]。最低地上高が9cmになっている理由は、縁石等に乗り上げたときに、車を傷つけないようにするためです。
基準を下回る車高の車は、運転中に何度も車体の底をこすったり打ち付けたりすることになるため、場合によっては運転途中に車が壊れて交通安全を阻害してしまいます。しかし、道路や縁石のほうを変更するわけにはいかないので、最低地上高を設けることで安全な運転に配慮されています。
なお、最低地上高の基準は、「普通自動車、小型自動車、軽自動車」すべてのおいて共通なので、「普通自動車だから車高を下げられる」「軽自動車だから車高を下げられない」といった違いはありません。
[注1]:国土交通省:(最低地上高) 保安基準第3条の告示で定める基準は
最低地上高より低いと車検に通らない
車の車高が最低地上高の基準よりも低いと車検に通りません。そして車検に通らない車は、公道を走ることができません。
公道で安全に運転できる基準のひとつとして最低地上高が利用されているため、車を整備するときは必ず最低地上高を守りましょう。
最低地上高のポイントは「動かない部分」が地上から9cm以上離れていること
最低地上高を考えるうえで大きな疑問のひとつが、「どこからどこまでを9cm確保すれば良いのか」という問題です。
重要なのが、最低地上高は、「動かない部分」の高さが制限されていることです。タイヤに付属しているロアアームやスイングアーム、ゴム製のパーツにサスペンションといった「足回り」に関しては、車高制限の対象にはなりません。また、ライトが埋め込まれていない樹脂製のエアロパーツも、仮に壊れても車の走行能力に影響は出ないため、地上高が5cm以上あれば良いという扱いになっています。
しかし、マフラーやサスペンションメンバーのボルトといった「動かない部分」は、最低地上高の対象です。その他、フォグライトや反射板、ウインカーにも「ライトの下縁が地上から25cm以上」といった制限があります。車軸部分では最低地上高をクリアしていても、場合によっては最低地上高違反になるので、所有している車を実際に見て最低地上高を調整しましょう。
最低地上高の計測時の条件とは?
保安基準では、最低地上高の計測に関する明確な条件が定められています。以下の通りです。順番に解説していきます。
- 測定する自動車は、空車状態とする。
- 測定する自動車のタイヤ空気圧は、規定された値とする。
- 車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準(中立)の位置とする。ただし、車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車高が最低となる位置と車高が最高となる一の中間の位置とする。
- 測定する自動車を舗装された平面に置き、地上高を巻き尺等を用いて測定する。
- 測定値は、1cm未満は切り捨てcm単位とする。
(最低地上高) 保安基準第3条の告示で定める基準は
上記からわかるように、車両を凹凸のある場所に駐車したり、タイヤに空気を追加したりしても、実際よりも車高が高く計測されることはありません。
測定時に車両を空車にする
正確な最低地上高を測定するには、車両に荷重がかかっていない状態で行う必要があります。乗車している人や積載物によって車体が沈み込み、実際の最低地上高が測定できなくなってしまうためです。ただし、走行に必要な装備、燃料、潤滑油、冷却水などの基本的な負荷は搭載した状態で測定する必要があります。
車のタイヤの空気圧を規定された値にする
車検では、最低地上高の測定時にタイヤの空気圧が重要となるため、規定値が設けられています。時間の経過と共に空気は自然に抜けてしまい、空気圧が低下すると車体が下がり、正しい最低地上高を測定することができません。
さらに、空気圧の低下はタイヤの形状を崩し、本来の性能を発揮できなくなり、摩耗を促進するだけでなく、パンクのリスクも高めてしまいます。そのため、定期的な空気圧チェックを行い、規定値に調整することが大切です。ちなみに、車高を高くするために空気圧を規定値より高く設定しても、実際の車検では規定値に戻されるため、意味がありません。
舗装された平らな場所で計測する
最低地上高を測定する際は、正確な数値を得るために適切な測定環境が求められます。規定では、「自動車を舗装された平面な場所で計測する」とされています。これは、凹凸や段差、坂道などでは測定値に誤差が生じる可能性があるためです。正確な測定を行うためには、舗装された平らな場所で、車体と地面が水平になるように自動車を配置し、測定を実施しましょう。
車高調整装置がある車の測定
車高調整装置、通称「車高調」が装着されている場合は、標準位置(中立)で測定を行います。ただし、車高を自由に調整できる車高調の場合、最低となる車高と最高となる車高の中間位置で測定する必要があります。つまり、車検時のみ車高を高く調整しても、必ずしも合格とは限りません。安全な走行を確保するためには、普段から最低地上高を厳守することが重要です。
測定値が1cm未満の場合は切り捨てる
最低地上高の測定で、小数点以下の数値が出た場合は、1cm未満は切り捨てられます。例えば、9.3cmの場合は9cm、8.8cmの場合は8cmとなります。
事前に測定した際にぴったり9cmだったとしても、実際の測定で8.8cmと判定された場合は、端数を切って8cmとなり、基準を満たさず不合格となります。四捨五入と勘違いしてしまうと、8.5cmや8.6cmでも問題ないと考えてしまいそうですが、実際には不合格です。
最低地上高の測定では、必ず「1cm未満は切り捨て」というルールを覚えておきましょう。
最低地上高に関する注意点
標準的な最低地上高は9cmですが、状況によっては例外が生じる場合があります。具体的な例を以下に示します。
最低地上高は車のサイズによって変化する
車の最低地上高は、車種によって異なる場合があります。基本的には9cmですが、ホイールベースやオーバーハングの長さによって変更されることがあります。
ホイールベースとは、前輪と後輪の車軸間の長さのことです。ホイールベースが300cm以上の車は、最低地上高が10cmとなります。アルファード、ヴェルファイア、センチュリーなど、大型のミニバンやセダンはこの基準に当てはまります。さらに、ホイールベースが350cmを超える場合は、最低地上高は11cm以上に設定されます。
オーバーハングとは、タイヤの中心から車体の最前部もしくは最後部までの長さのことです。前輪から前は「フロントオーバーハング」、後輪から後ろは「リアオーバーハング」と呼ばれます。オーバーハングの長さが73cm以上なら最低地上高は10cm以上、82cm以上なら最低地上高は11cmとなります。
ホイールベースとオーバーハングの長さは、車のカタログやメーカーのホームページなどで、個々の車種のを確認することができます。
リフトアップをした車は要注意
リフトアップしている車を車検に通すためには、いくつか注意点があります。車検証に記載されている車高から4cmまでのリフトアップであれば、構造変更の届け出は不要です。つまり、特別な手続きなしに車検を通すことができます。しかし、4.1cm以上リフトアップする場合は、構造変更の申請が必要となります。
構造変更とは、車のサイズを大幅に変えたり、エンジン交換や、排気量をアップさせる場合に行う手続きです。運輸支局で審査を受け、違反がないことを確認する必要があります。
とはいえ、指定された部品を使用すれば、4.1cm以上リフトアップしても構造変更は不要なケースもあります。ただし、実際には大きくリフトアップするには、指定外部品を使用することになるため、一般的には「4cmを超えた場合は構造変更が必要」とされています。
車検ではフォグランプやウィンカーランプの高さも確認される
車の最低地上高は、車体だけでなく、フォグランプやウィンカーランプにも基準が設けられています。霧や雨天時でも、光が乱反射せず足元をしっかりと照らすフォグランプは、最低地上高25cm以上が求められます。標準装備のフォグランプは、出荷時にメーカーによる検査が行われているため、車検の際に問題となることはまずありません。しかし、後付けの場合は、最低地上高を意識して取り付けを行う必要があります。
ウィンカーランプに関しても、下縁の高さが35cm以上という基準が定められています。大幅なカスタマイズを行わない限り、この基準を下回ることはほとんどありません。ただし、車検時には、ウィンカーのヒビや色などにも基準が設けられているため注意が必要です。これらの基準を満たすことで、安全な走行と車検の合格に繋がります。
最低地上高をカーリースの車両で下げることはできるか?
近年、自動車業界において注目を集めているのが、カーリースという新しい車の利用方法です。従来のような車の購入とは異なり、カーリースでは好きな車を選び、カーリース会社がその車を所有し、契約者は月々の定額料金を支払うことで、まるでマイカーのように自由に利用することができます。
この料金には、車両代金や登録費用に加えて、車検代金、自動車税、自賠責保険料といった、車に関する様々な費用が含まれている場合が多く、経済的な負担を軽減できる点が大きな魅力です。
リース車の車高を低くするなどの改造は原則的に不可
リース車では、車検に通るかどうかに関わらず、車の最低地上高を下げるなどの改造は原則禁止されています。リース車では、車両の所有者はカーリース会社であり、契約期間が終了した際には、契約当初と同じ状態での返却が義務付けられます。そのため、改造やカスタマイズによって車両の原状回復が困難になる可能性があるため、多くのカーリース会社は改造を禁止しています。
ただし、積雪地域におけるノーマルタイヤからスタッドレスタイヤへの交換など、必要不可欠な変更や、脱着可能なカップホルダーやシートカバーなどの設置は、一般的に問題視されることはありません。
最終的に車が手に入るリースではカスタマイズが可能なことも
近年、個人向けのカーリースはますます人気が高まっており、様々な業者が魅力的なプランを提供しています。その中でも注目すべきは、契約満了時に車がもらえるプランです。このタイプのプランでは、車の返却義務がなく、車検に通る範囲内であればカスタマイズも認められる場合もあります。まるで自分の車のように、自由にカスタマイズを楽しむことができる点は大きな魅力と言えるでしょう。
ただし、リース車の改造やカスタムは、カーリース会社によって許容範囲が異なりますので、契約前に必ず確認が必要です。万が一、リース期間中にカスタマイズが認められなくても、契約満了後に車の所有権が移れば、自由にカスタマイズを楽しむことができます。
最低地上高が原因で車検が不合格になった場合の対処法
車検を受ける際に、最低地上高が基準を満たしていないために不合格になるケースは決して珍しくありません。せっかく車検に出したのに、思わぬところで不合格となると、がっかりですよね。そこで今回は、車検で最低地上高が原因で不合格になった場合の対処法について詳しく解説していきます。
部品を取り替えて車高を調整する
車の車高が低すぎて車検に通らなかった…そんな時は、まず車高を調整して合格ラインに近づけることが重要です。一般的で効果的な方法は、車高調整式サスペンションを取り付けることです。ただし、取り付けには専門的な知識と工具が必要となるため、カー用品店や大手中古車販売店などに依頼することをおすすめします。
すでに車高調整可能なサスペンションが装着されている場合は、調整だけで車検に通る可能性も高いでしょう。しかし、車高調整を行うと、ホイールバランスやアライメントの調整も必要になる場合があるので注意が必要です。
新しい車に買い替える
車の車高を調整しようと考えている方は、思わぬ出費に備えておきましょう。部品代や調整代に加え、予想外の費用が発生することもあります。車検前に高額な費用がかかることが予想される場合は、思い切って車を買い替えるという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
最低地上高とは、車の車体が低くなりすぎないように制限するルールで、日本では9cm以上が義務付けられています。車検では、動かない部分の最低地上高が9cm以上あるかをチェックされ、基準を満たさないと車検に通らないため、公道での走行ができません。車高が低い場合は、車高調整や買い替えを検討しましょう。
私たちクルマ買取「ソコカラ」では、故障車はもちろん、不動車、事故車、水没車など、さまざまな車両の買取を行っています。レッカー代や廃車手続き費用も無料なので、お客様は余計な費用を負担する必要はありません。廃車をお考えなら、全国どこでも買取受付しているので、ぜひご相談ください。


この記事の監修者
浅野 悠
中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.26
【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.30
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 廃車のお役立ちコラム
- 2024.08.09
トラブル回避!陸運局で使える委任状・譲渡証明書の書き方【記入例付き】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.07.03
車検証の住所変更はオンラインで完結!手続き方法を徹底解説
- 住所変更
- 車検証
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2024.09.10
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-






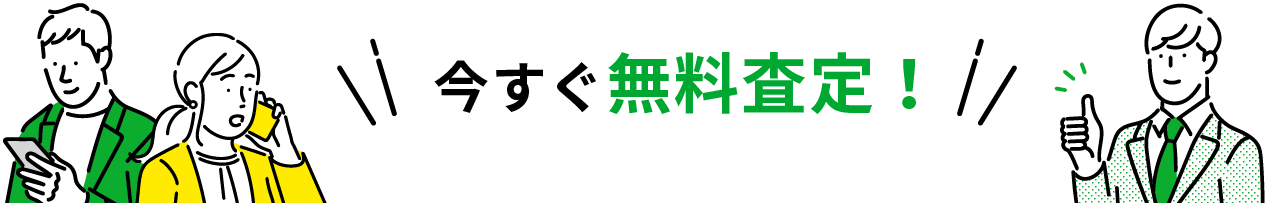




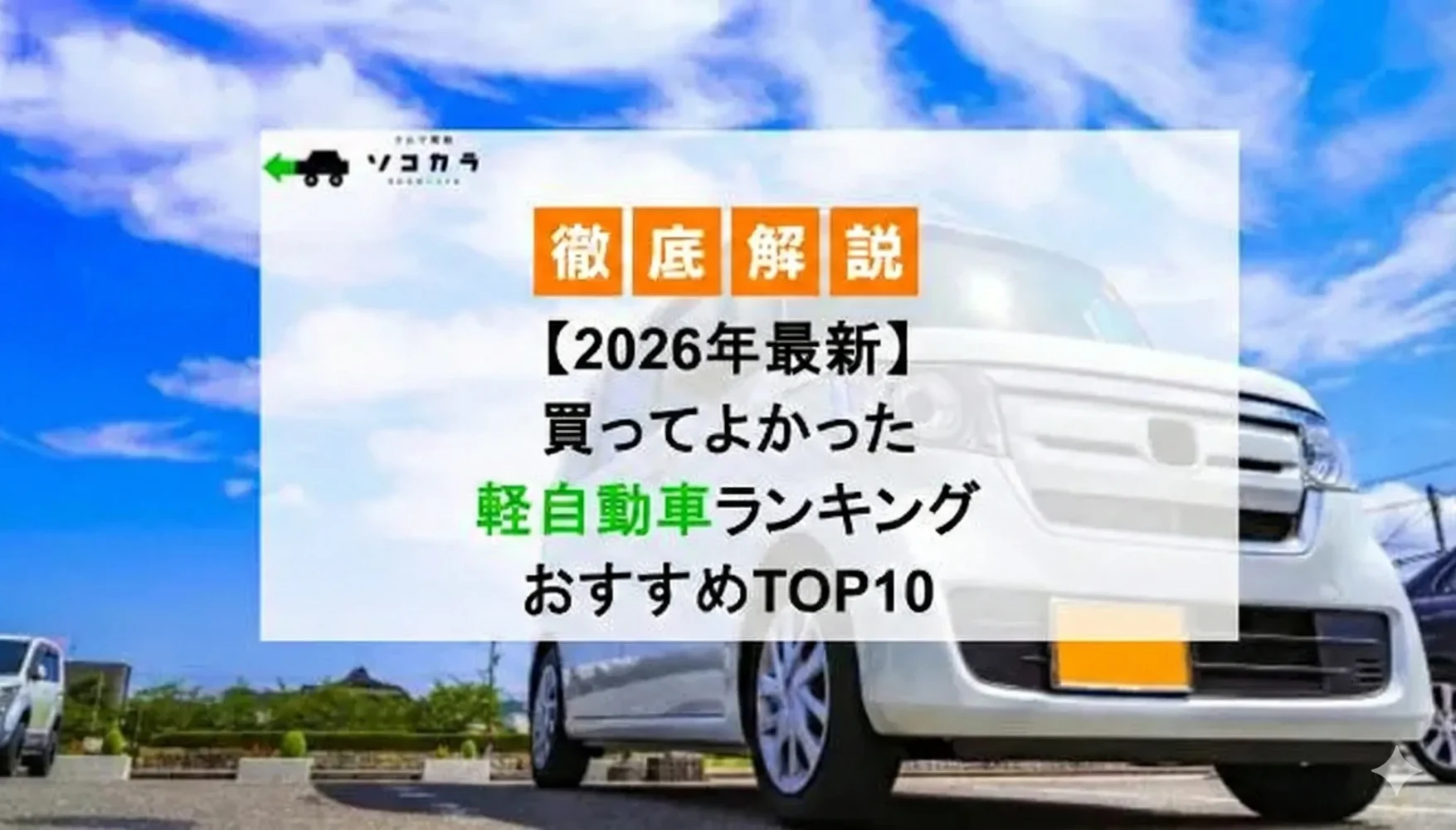


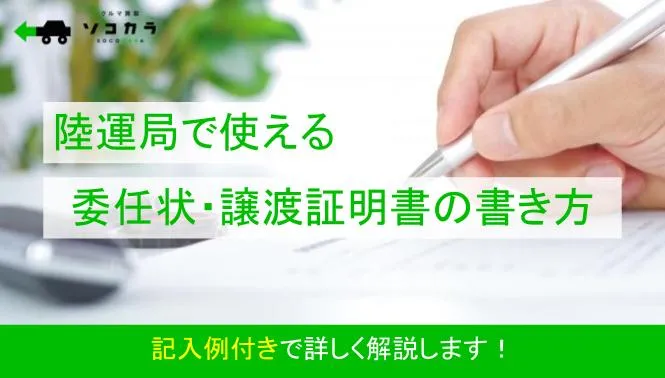
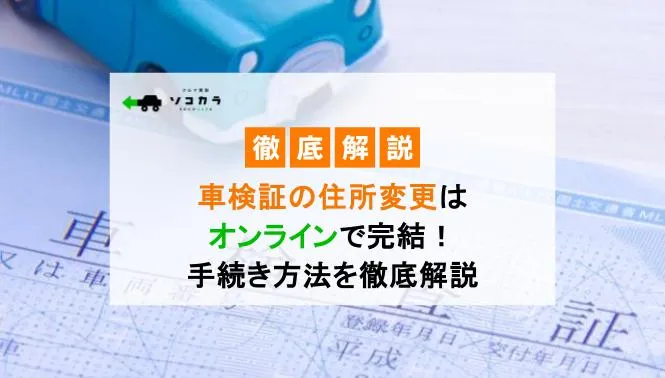
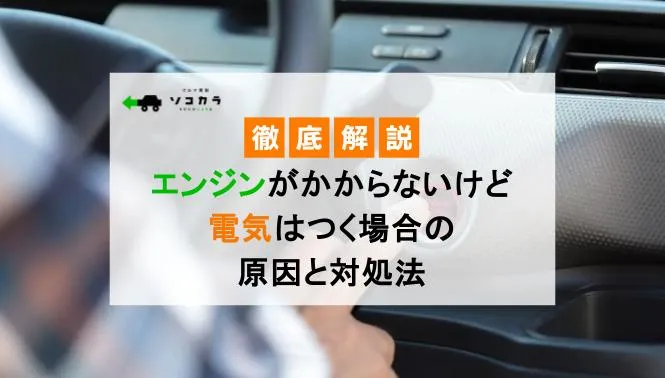

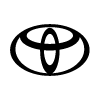
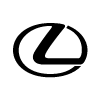
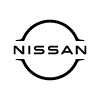

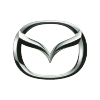


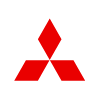









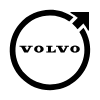

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870