- 2021.02.03
自動車業界の歴史と今後の展開
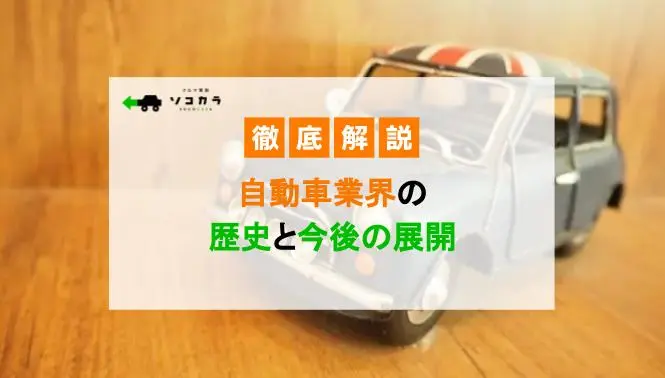
近年、若者の車離れが進み、自動車業界が落ち込んでいると言われていましたが、2020年の新型コロナウイルス感染症の流行により、再び需要を取り戻しました。
自動車業界は、世界情勢の移り変わりに深く関りがあります。これまでの自動車の歴史から今後の在り方について解説します。
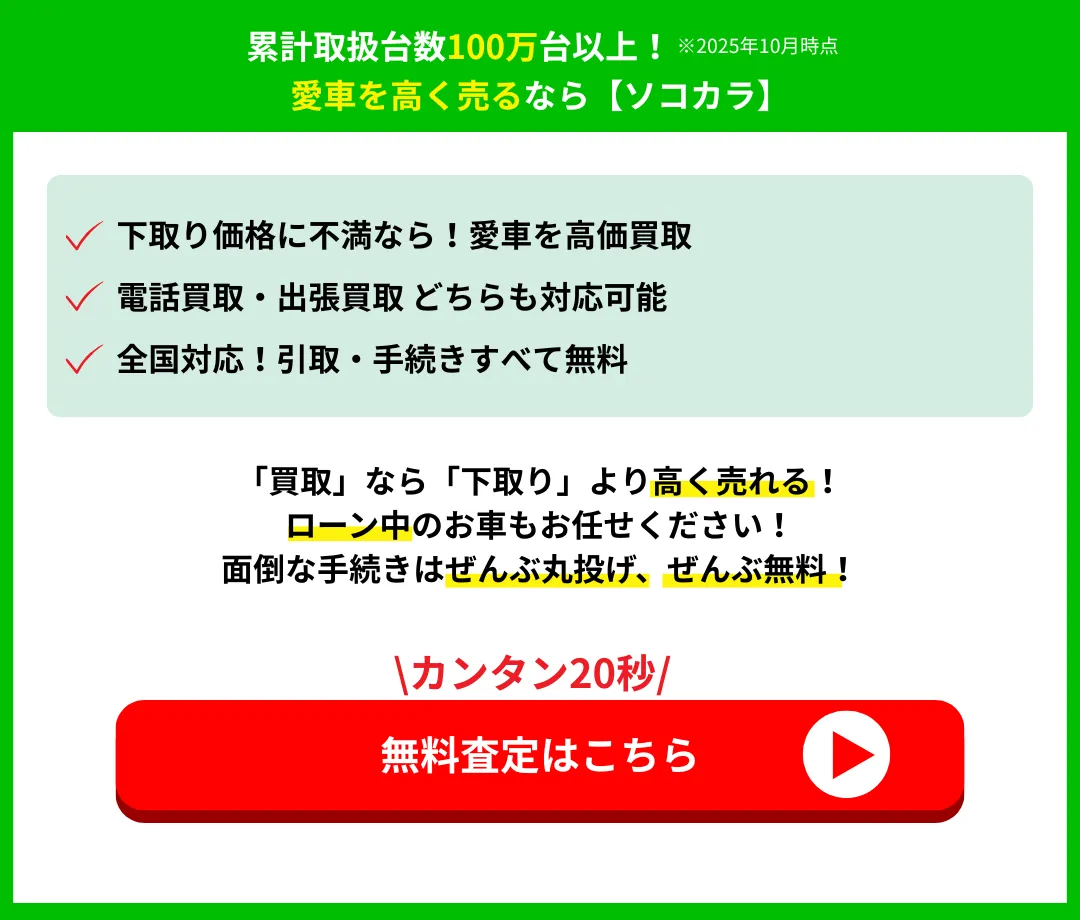
自動車の誕生から大衆化するまで
自動車がいつどこで誕生し、日本人にとって身近なものになったかご存知ですか?
今でこそ身近な存在である自動車ですが、初めから誰でも所有できたわけではありません。
まずは、意外と知られていない自動車の誕生から大衆化するまでの歴史をご紹介しましょう。
自動車の誕生
自動車が誕生したのは1769年、日本でいうと江戸時代です。フランスの軍事技術者の二コラ・ジョセフ・キュニョーが国王ルイ15世から依頼され、大砲を運ぶために開発したと言われています。
日本に初めて自動車が持ち込まれたのは1898年、明治時代に入ってからです。
しかし、その頃の日本は道路が整備されておらず、輸入にも多額の費用がかかることから、一部の富裕層や身分の高い人しか所有することができませんでした。
日本での需要の広がり
日本で自動車の需要が広がるきっかけとなったのは1923年に発生した関東大震災であり、鉄道が壊滅的な被害を受けたため、鉄道の代わりとなる輸送手段として自動車が活躍しました。
そこから、贅沢品だった自動車が実用品として扱われるようになりましたが、1939年から第二次世界大戦が起こり、1945年の終戦までは軍用トラックの大量生産が行われため、日本での乗用車の開発は少し遅れることになります。
国産車の大衆化
終戦後、米軍により大量の自動車が日本に持ち込まれました。当時の日本の自動車生産は、海外メーカーの部品を輸入し組み立てるという「ノックダウン生産」が主流でした。
そんな中、トヨタ自動車は国内生産にこだわり、1955年に国内初の純国産車であるクラウンを発表しました。
海外メーカーの自動車は大排気量で頑丈な大型車ばかりでしたが、トヨタ自動車は国内での市場調査の結果を用いて日本の道路状況や使用状況に応じた開発を行い、クラウンは月に1,000台を生産する大ヒット商品となりました。
高度経済成長期の突入
1964年の東京オリンピックや1970年の大阪万博開催などもあって、1955年から1973年まで日本は世界に類をみないほどの経済成長を遂げ、高度経済成長期と呼ばれる時代へ突入しました。
乗用車の需要がさらに高まると考えたトヨタ自動車は工場を新設し、1966年にまさに日本の自動車の代表格と言えるカローラを発表しました。
カローラの販売台数は1968年には16万台、その翌年には24万台となり、大衆車市場の首位を独占し、自動車が人々の生活に身近なものとなりました。
そして、1980年に日本の自動車生産台数は1000万台を突破し、アメリカを抜いて世界一位となりました。
日本国内での時代や考え方の変化
絶頂期を迎えていた日本車ですが、1990年頃からバブルが崩壊し時代が大幅に変化し、同時に自動車に対するニーズも大型・高級志向から個性や機能を重視する志向に変化したり、安全性や環境汚染の問題が重要視されるようになったりしました。
そんな日本国内における時代や考え方の変化の歴史をご紹介します。
安全性の重視
日本では、自動車の保有台数の増加とともに交通事故も増加し、2004年には過去最多の事故件数である95万件を記録しました。
そこで、シートベルト着用の義務化(1994年)や、危険運転致死傷罪の制定(2001年)など、違反の厳罰化が進んだことにより各メーカーが安全性を重要視するようになりました。
環境問題への取り組み
安全性だけでなく自動車の排気ガスによる大気汚染も大きな社会問題として浮上してきたため、CO2を抑えるエコカーの開発も進みました。
1997年に誕生した世界初のハイブリッドカーであるトヨタのプリウスがヒットし、日産のノートやホンダのフリードなど各企業がガソリン以外の燃料で走行する自動車を開発し始めました。
若者の車離れ
2000年代半ば頃から、都市部における公共交通機関の発展、自動車所有率の減少、若者の憧れや興味の対象が自動車からスマホやゲーム、アニメなどに移行したことにより、若者の車離れが深刻化していきました。
コロナ社会の突入
2019年に世界中でパンデミックを起こした新型コロナウイルス感染症。日本でも2020年4月に緊急事態宣言が発令され、人々の移動が大幅に制限されました。
そんな長引くコロナ社会の中で、他者との接触を避けられるという理由から、再び自動車の有用性が注目されるようになりました。
コロナ社会に備えて免許を取得しようとする人が増え教習所に行列ができたり、イベントや映画がドライブインフェス・ドライブインシアターと呼ばれる自動車を有効活用したものに発展したり、公共交通機関ではなく自動車を利用して旅行に出かけたり、これまでとは違う形で自動車が注目されるようになりました。
まとめ
日本国内で自動車が普及してからまだ100年あまりですが、歴史を紐解いていくと日本の経済成長とともに自動車業界も繁栄し、様々な変化や進化をとげながら、廃れることなく人々の生活に寄り添ってきたことが分かりましたね。
2019年に行われたモーターショーでは、ドライバーの趣味嗜好に合わせてドライブルートを案内したり、音楽を流したりできる自動車や、スマートフォンだけで出庫からすべての操作ができる軽自動車、運転席が存在しない自動車など、完全自動運転が想定されたデザインまで発表されました。
日本はすでに超高齢者社会に突入しており、この先自動車を運転できない人が増える可能性も十分に考えられますが、自動運転や充電式の自動車が開発されると自動車が移動手段として一番身近なものとして発展していけるのではないでしょうか。
渋滞も交通事故もなく、好きな時に好きなところへ行ける社会がもうそこまできているのかもしれません。
こちらもおススメ|運送・物流業界向けオンラインマガジン|トラッカーズマガジン


この記事の監修者
浅野 悠
中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.26
【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.30
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.07.03
車検証の住所変更はオンラインで完結!手続き方法を徹底解説
- 住所変更
- 車検証
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2024.09.10
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-
-

-
- 廃車のお役立ちコラム
- 2024.08.09
トラブル回避!陸運局で使える委任状・譲渡証明書の書き方【記入例付き】
-






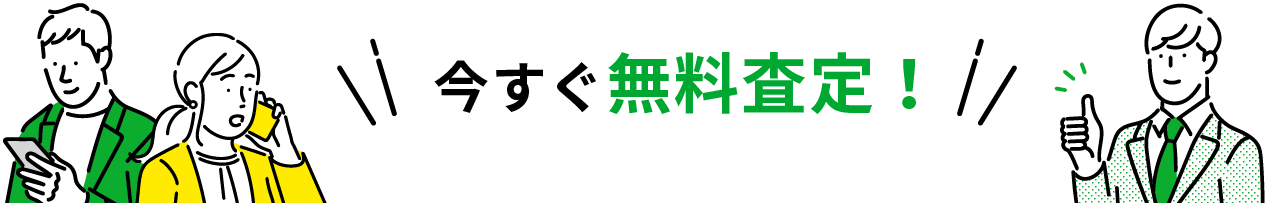




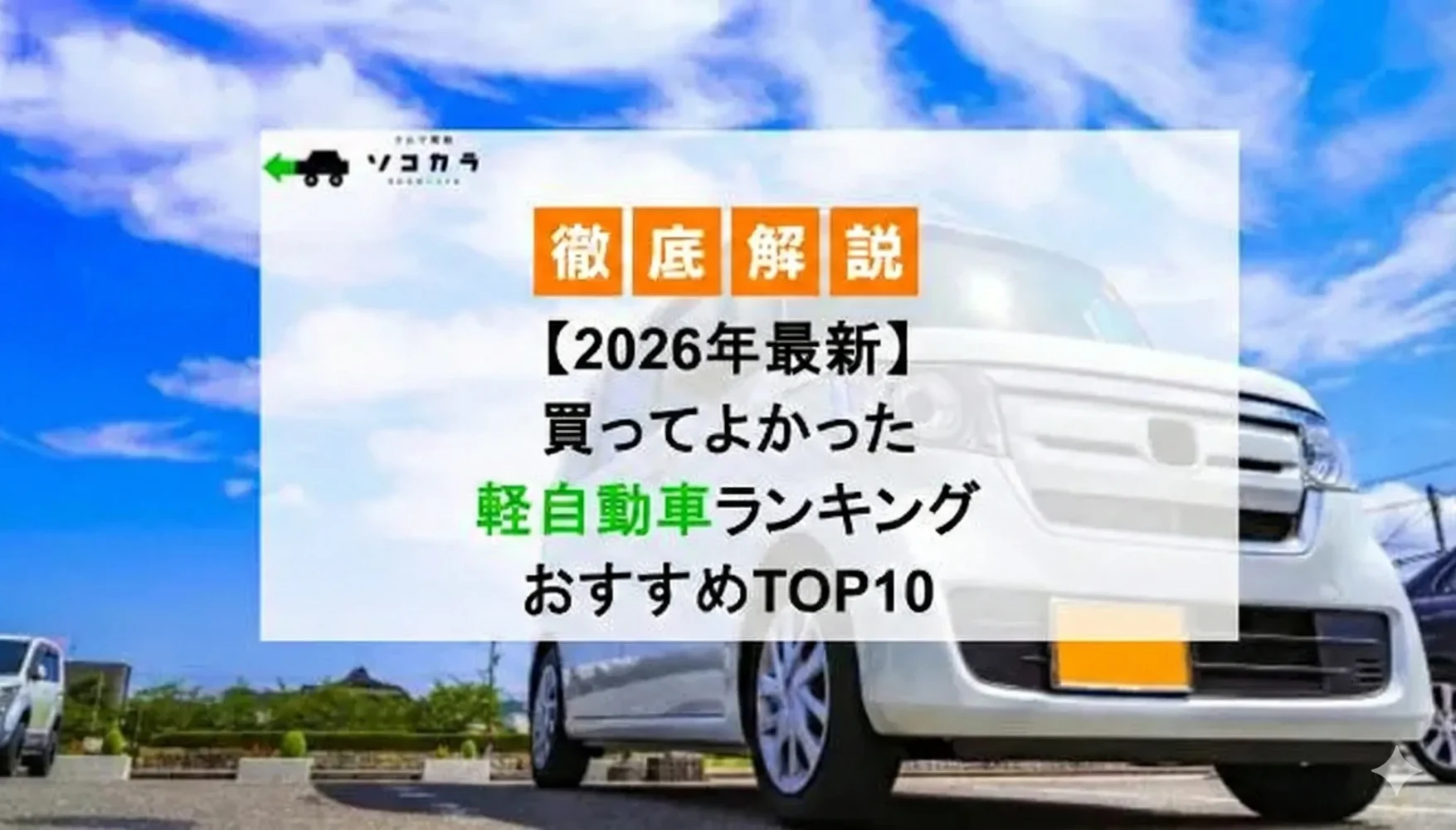


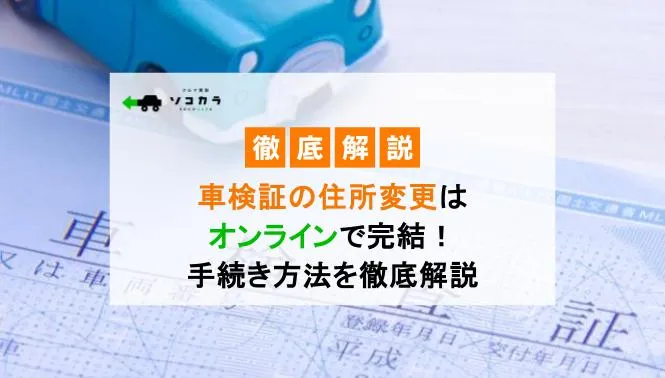
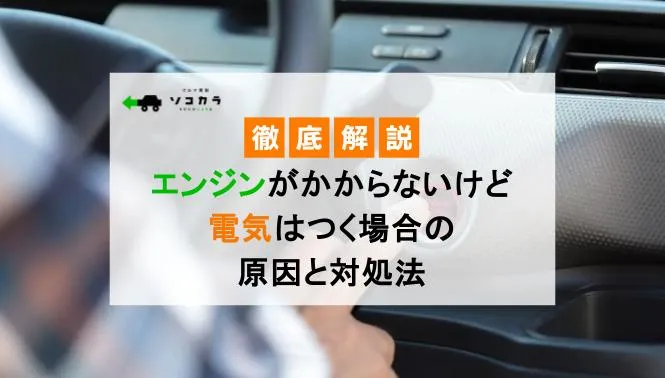
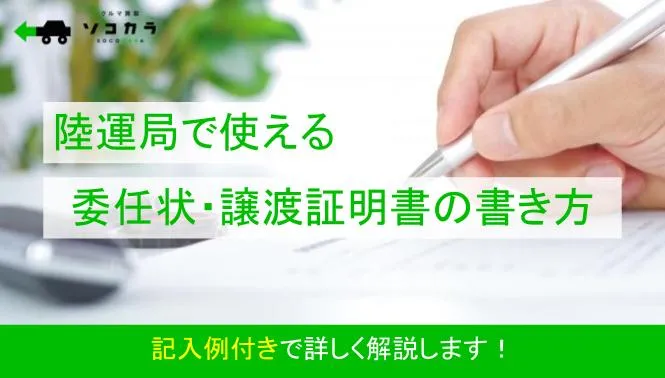

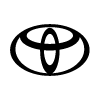
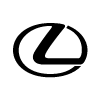
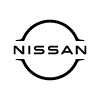

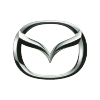


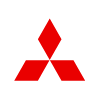









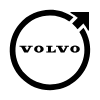

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870