- 2024.03.29
故障車を牽引する方法とは?基本的な手順や注意点について解説

車の走行中にトラブルが発生し、自走しなくなったときには、安全を確保するための適切な対処が必要になります。
故障車と周囲の状況によっては、牽引して安全を守ることも考えられるでしょう。
本記事では、緊急時に故障車を牽引する方法と注意点について解説します。
故障車のその後の取り扱いについても解説するので、万が一を考慮して詳細を確認してみてください。
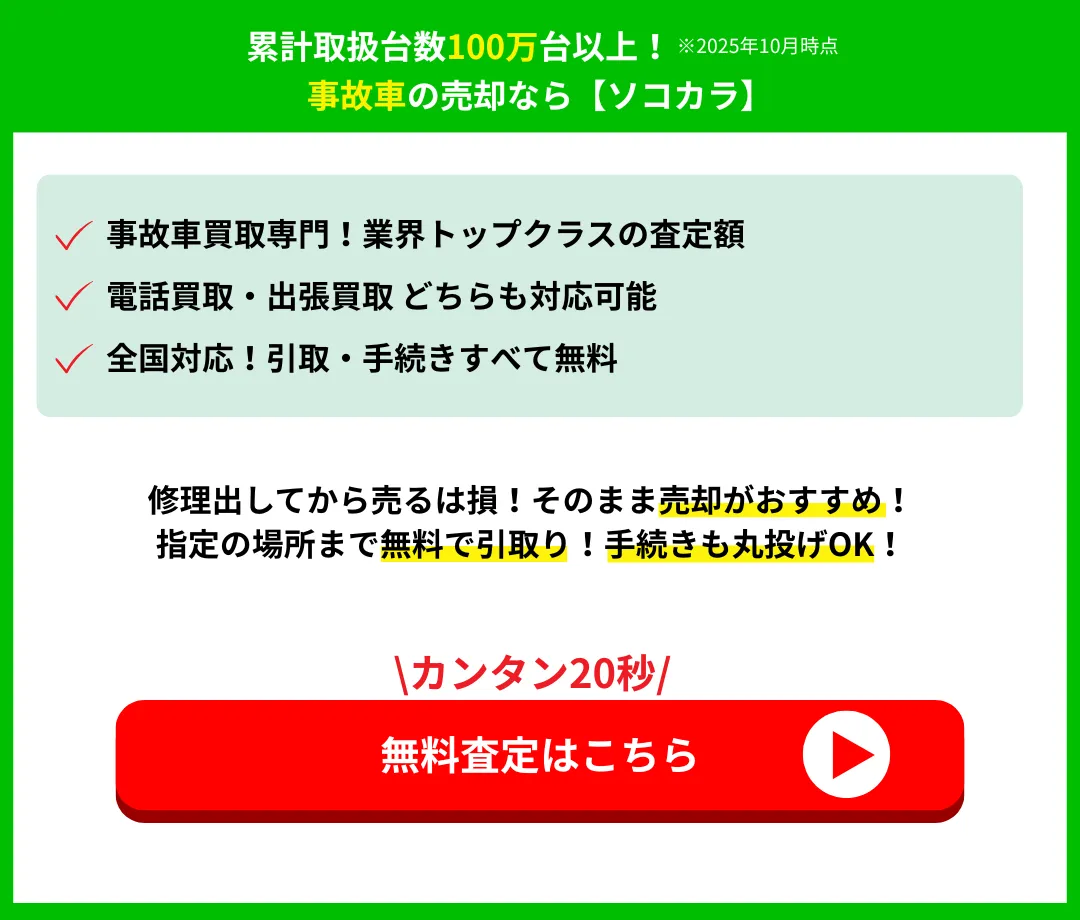
車が動かなくなったときの対処法
車が突然動かなくなったときには、とにかく安全を確保するための行動を起こす必要があります。
きちんと対処ができないと事故につながる可能性もあるため、事前に車が故障したときの流れを確認しておくのは重要です。
以下では、車が動かなくなったときに行うべき行動について解説します。
まずは安全な場所に車を移動させる
車が故障して自走できなくなったら、まずは安全な場所に移動することを考えましょう。
道路であれば路肩に駐車できるように、ゆっくりと車を動かします。
施設の駐車場などの場合にも、走行する車の邪魔にならない場所を探し、焦らずゆっくりと移動を試みます。
安全な場所に移動できたら、車を停止させて状況を確認します。
故障時にはすぐに車の外に出ず、周囲の状況をきちんとチェックするのも重要です。
車が故障すると冷静さを失ってしまい、慌てて危険な行動を取ってしまうケースもあります。
まずは冷静になって、自分自身の安全を確保するのもポイントです。
夜間は停止表示器材などを使って周囲に危険を知らせる
車が夜間など視認性の悪い時間帯に故障した場合、安全な場所に移動させたつもりでも、周囲から認識されずに事故につながる可能性があります。
周囲が暗いときには車に積んである停止表示機材を設置し、後続車に危険を知らせる必要があります。
ハザードランプも点灯させて 、車が停止していることが一目でわかるようにしましょう。
万が一のことを考えて、運転手は車から距離を取った場所で待機するのも重要です。
状況によってはJAFや自動車保険会社などに連絡する
車の故障状況や周囲の環境によっては、JAFや加入している自動車保険会社に連絡して対応を依頼しましょう。
例えば高速道路で故障した場合、自分の手ではどうしようもない状況となります。
事故が発生する前に、すぐにJAFや自動車保険会社に連絡して対応を任せましょう。
故障車を牽引するための手順
車が故障した場所によっては、牽引してより安全な場所に移動することも考えられます。
家族や友人に車を出してもらい、故障車の牽引を依頼するのも1つの方法です。
しかし、故障車の牽引はきちんと手順を踏まないと、危険な行為になる可能性もあります。
以下では、故障車を牽引する際の基本的な手順を解説します。
故障車のエンジンが動くか確認する
故障車を牽引する際には、まずエンジンが動くか確認しましょう。
エンジンが故障して動かない場合、ハンドルが重くなって操作が困難となります。
また、ブレーキも利きづらくなるため、牽引車との衝突事故につながるリスクもあります。
まともに走行させるのが難しいため、エンジンに問題がある場合には自分で牽引せずに、専門業者に依頼することを推奨します。
牽引するロープを装着する
エンジンが動き、走行中のコントロールが可能であるなら、故障車を牽引するロープを装着して準備を進めます。
牽引車の後方と故障車の前方にロープを引っ掛けて、外れないことを何度も確認しましょう。
牽引に使うロープには、 0.3m平方以上の白い布を装着する必要があります。
これは車を牽引していることを周囲に知らせるためのものであり、法律によって定められている方法です。
事故車の牽引中に周囲との事故を防ぐことにもつながるため、ロープに白い布をつけることは忘れないように注意しましょう。
牽引車と故障車のそれぞれで運転の準備をする
ロープで牽引車と故障車をつないだら、それぞれの車に運転手が乗り込みます。
お互いに声を掛け合い、故障車をゆっくり動かすように牽引車を発進させましょう。
牽引車の動きに合わせて、故障車もハンドルを動かして運転する必要があります。
下り坂や急カーブなどでは、より安全を意識して牽引するのがポイントです。
下り坂で牽引車が急ブレーキをかけると、故障車の対応が間に合わずに衝突する恐れがあります。
急カーブも牽引車の動きが早すぎると、故障車が引っ張られて事故につながるリスクがあるでしょう。
道路に合わせて安全な走行を実践し、事故を起こさない意識を持つことも大切です。
牽引車と5m以内の間隔を保ちながら運転する
牽引車と故障車の車間距離は、5m以内の間隔を保つことが義務付けられています。
5m以上の距離になると、牽引車で引っ張りきれずに故障車が事故を起こす可能性があります。
逆に車間距離が短すぎると、少しの動きで牽引車と故障車が衝突するケースが懸念されます。
故障車は途中で正常なコントロールができなくなる可能性もあるため、5m以内の間隔を意識してあらゆる状況に対応できるように備えましょう。
安全運転を心がけて目的の場所まで移動させる
牽引車で故障車を動かす準備ができたら、安全運転を心がけて目的の場所まで移動させます。
故障車の状況を考慮して、牽引車はいつも以上に安全を確保する運転が求められます。
スピードはなるべく落とし、故障車がついてこれているかこまめに確認するのがポイントです。
目的とする場所まで距離がある場合には、途中で休憩を挟みつつ運転するのもコツです。
休憩時に故障車の状態を改めてチェックしたり、ロープがきちんとついているか確認したりすることで、より安全な運転を実現できます。
故障車を牽引する際に注意すべきこと
故障車を牽引する際には、事前に注意すべきことがいくつかあります。
牽引時に事故を引き起こさないためにも、注意点を把握した運転が求められます。
以下では、故障車を牽引する際の注意点について解説します。
総重量750kg以上の車は牽引免許が必要になる
故障車を牽引する際には、基本的に特別な資格は必要ありません。
先の手順通りに準備をして、安全な運転を心がけることができれば、牽引を行っても問題ありません。
一方で、総重量が750kg以上の車を牽引する場合には、基本的に牽引免許を取得している必要があります。
故障車などを動かすやむをえない状況では、牽引免許がなくても問題ありませんが、それ以外の場合では免許が必要になることを覚えておきましょう。
牽引時の法定速度は時速30kmになる
故障車を牽引する際には、法定速度が時速30kmに制限されます。
仮に制限速度が50kmの道路でも、牽引の際には30kmの速度を守る必要があります。
故障車の牽引には技術が必要になるため、速度が早すぎると事故の可能性が高まります。
そのため時速30kmを基準に、速度を落として走行することを意識しましょう。
牽引車と故障車の長さは25m以内に調整する
牽引時には車両間の距離を5m以内に抑えるほか、牽引車の前端から故障車の後端までの長さを25m以内にする必要もあります。
1台の故障車を牽引する際には問題ない長さですが、複数台で牽引する場合には、25m以内という数値に注意が必要です。
また、牽引できる台数は大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車が2台まで、大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車は1台までとなっています。
故障している部分によっては牽引以外の方法を考える
車が故障した原因や部位によっては、牽引以外の方法を考える必要があります。
先の解説通りエンジンにトラブルがあり、正常にかからない状態の場合には、牽引時のコントロールが難しくなるため別の方法が推奨されます。
そのほか、タイヤがパンクしているなど、正常な走行が困難だと想定される場合にも、牽引は避けるべきです。
故障車の状態は可能な限り細かくチェックし、故障箇所に合わせて対策を考えるのがポイントです。
無理に牽引して事故を起こしては元も子もないので、安全性を重視して故障車を操作するようにしましょう。
ハイブリッドカーや電気自動車は車両火災のリスクがある
ハイブリッドカーや電気自動車が故障した場合、無理な牽引によって車両火災が発生するリスクがあります。
ハイブリッドカーや電気自動車は、4輪が設置した状態で動かしてしまうと、火災を引き起こすリスクがあると注意喚起されています。
ハイブリッドカーや電気自動車が故障し、タイヤが回らない状態になったときには、牽引ではなくメーカーが指定する方法で対応するようにしましょう。
牽引が難しい場合には無理をせず専門家に依頼する
故障車の牽引は、簡単な作業ではありません。
運転に慣れていない人が対応する場合、大きな事故につながる可能性もあります。
特に牽引する距離が長いときや、複雑な道路を運転する必要があるときには、牽引のリスクが高まります。
少しでも牽引に不安を覚えるときには、無理をせずに専門家や各種サービスに依頼しましょう。
任意保険のロードサービスやJAF(日本自動車連盟)に連絡することで、故障車の牽引を対応してくれます。
JAFなどは牽引する距離によって費用がかかりますが、安全性を考慮するのなら積極的な利用がおすすめです。
故障車を牽引したらその後の対応を考える
故障車の牽引を無事に終えたら、その後の対応についても考える必要があります。
故障車をその後どうするべきなのか、どんな対応が適切なのかを考えて、早めに対処するのが望ましいです。
以下では、故障車を牽引した後の対応方法について解説します。
故障車の状態を詳しく確かめる
故障車の牽引を終えたら、まず故障の原因や状況を詳しくチェックしましょう。
なぜ故障したのか、どこが故障したのかがわかれば、その後の対応策を考案しやすくなります。
素人目では故障の原因がわからないことも多いため、専門家に見てもらうのが基本となるでしょう。
故障車が走行不能な場合には、状態を確認してもらうために再度牽引することも考えられます。
自動車工場やカー用品店など、自動車整備士のいる場所まで距離がある場合には、レッカー車を使うことが検討されるでしょう。
安全な状態で車を保管する
牽引した故障車は、安全な状態で保管するのも重要です。
故障の状況によっては、その後さらなるトラブルに発展する可能性もあります。
なるべく周囲に問題が飛び火しないように、安全を重視して保管場所を選びましょう。
すぐに故障車に手をかけられない場合、時間が経って自然とそのまま放置してしまうケースも多いです。
しかし、故障車でも廃車の手続きをしないと、自動車税などのコストが発生します。
野晒しになるとサビなどによって車が痛み、より故障箇所が増えるリスクもあるでしょう。
安全かつ適切に保存できる環境を用意するのが、故障車への対処法の1つです。
修理・廃車といった対応が選択肢になる
一般的に故障車は、修理や廃車といった対応が選択肢に入ります。
修理して直る程度の故障であれば、再び運転できる可能性があります。
自動車整備士などの専門家に見てもらい、修理が可能か判断してもらうとよいでしょう。
修理が難しい場合には、廃車手続きを行うことが考えられます。
車を廃車にするには所定の手続きが求められるため、基本となる流れや必要書類を確認することから始めましょう。
忙しくて廃車の手続きをする時間が取れない場合には、廃車買取の専門業車などに代行を依頼することも可能です。
廃車にする際には廃車買取の専門業者に依頼する
故障車を廃車にする際には、廃車買取の専門業者に依頼して買取できないか査定してもらうのがおすすめです。
走行できなくなった故障車でも、廃車買取の専門業者であれば高価買取ができるケースがあります。
そのまま廃車にするよりも、まずは故障車の状態を見てもらい、買取できるか判断してもらうとよいでしょう。
廃車買取の専門業者に依頼することで、故障車の買取と廃車手続きの代行を同時に任せられます。
故障車の処理にかかる手間を削減できるため、スムーズに車の買い替えなどを計画できるでしょう。
故障車を廃車にする際には「ソコカラ」での査定がおすすめ!
故障車の買取を依頼する際には、多くの実績を持つ「ソコカラ」でぜひ査定をお試しください。
「ソコカラ」はどんな車でも買取ができる廃車買取業者として、多数のノウハウを持っています。
故障車だけでなく、10年以上乗った車や10万km以上走った車なども買い取れるため、他業者では値がつかなかった車の買取も実現可能です。
運転できない故障車でも、無料で引取りを行うので、コストを気にせず査定・買取をご依頼いただけます。
手続きの費用も無料となっているため、金銭的な負担に悩むことはありません。
365日受付をしているので、故障してすぐに買取を実行することも可能です。
車の査定はホームページやLINEから簡単に行えるので、この機会にぜひ査定価格をチェックしてみてください。
まとめ
故障車を安全な場所に移動させる際には、牽引が1つの選択肢となります。
牽引するためのルールや注意点を確認し、安全を確保できるように備えることで、故障車をスムーズに移動させることも可能です。
この機会に故障車を牽引する方法を確認し、万が一の故障に備えておきましょう。
故障車を廃車にするのなら、「ソコカラ」での買取をぜひご利用ください。
「ソコカラ」は「自社オークション」と「自社物流ネットワーク」を持つため、中間コストをカットしてその分を買取価格に還元できます。
そのためさまざまな状態の車を、高価買取できる環境が整っているのです。
まずは無料査定から、お気軽に「ソコカラ」の買取をお試しください。


この記事の監修者
澤井 勝樹
「株式会社はなまる」監査役。1975年生まれ。10年近く会計事務所で経理総務全般の経験を積みながら、税理士、行政書士登録。その後、IT系ベンチャー企業のIPOの準備に携わるなど活動。現在はインターネットとクルマの可能性を世の中に伝えたいとソコカラコラムを執筆中。家族・食べること・愛車のセレナが大好き。おもに廃車の手続きや税金に関するコラムを執筆している。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.16
【2025年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.19
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2024.09.10
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2025年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.01.16
【図説】バッテリー上がり時の適切な充電方法
-
-

-
- 故障車のお役立ちコラム
- 2024.11.01
ハンドルを切ると異音がする原因と対処法について詳しく解説!
- ハンドル
- 異音
-






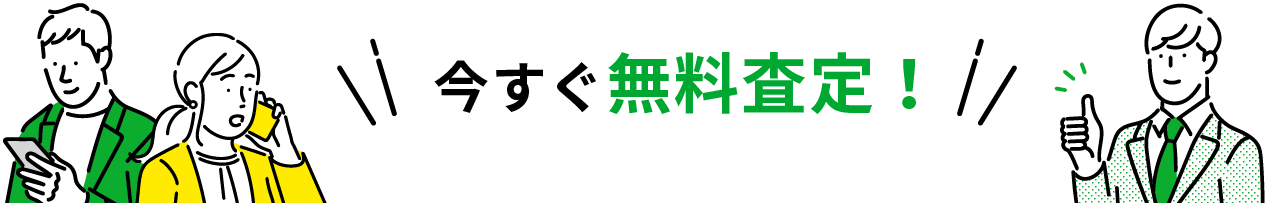




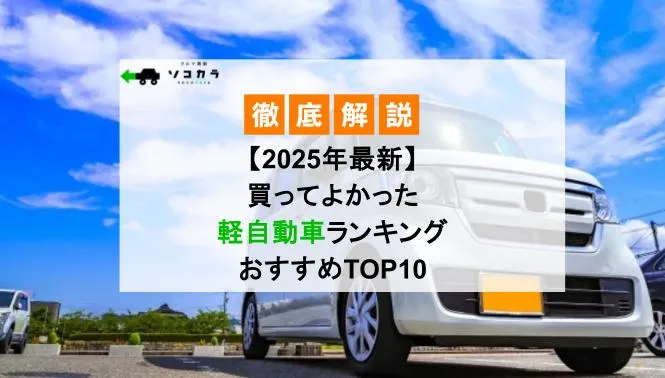

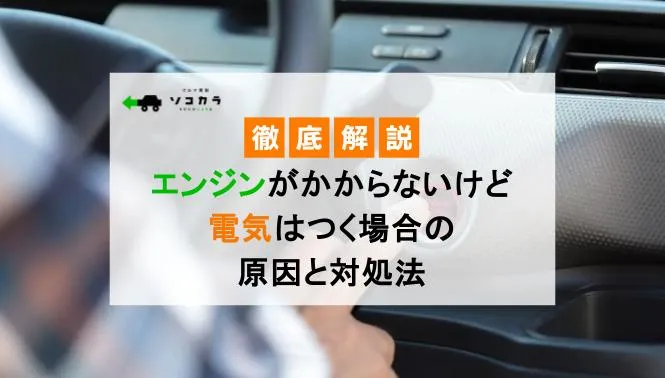




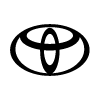
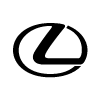
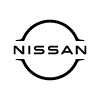

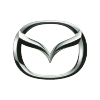


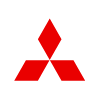









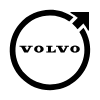

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870