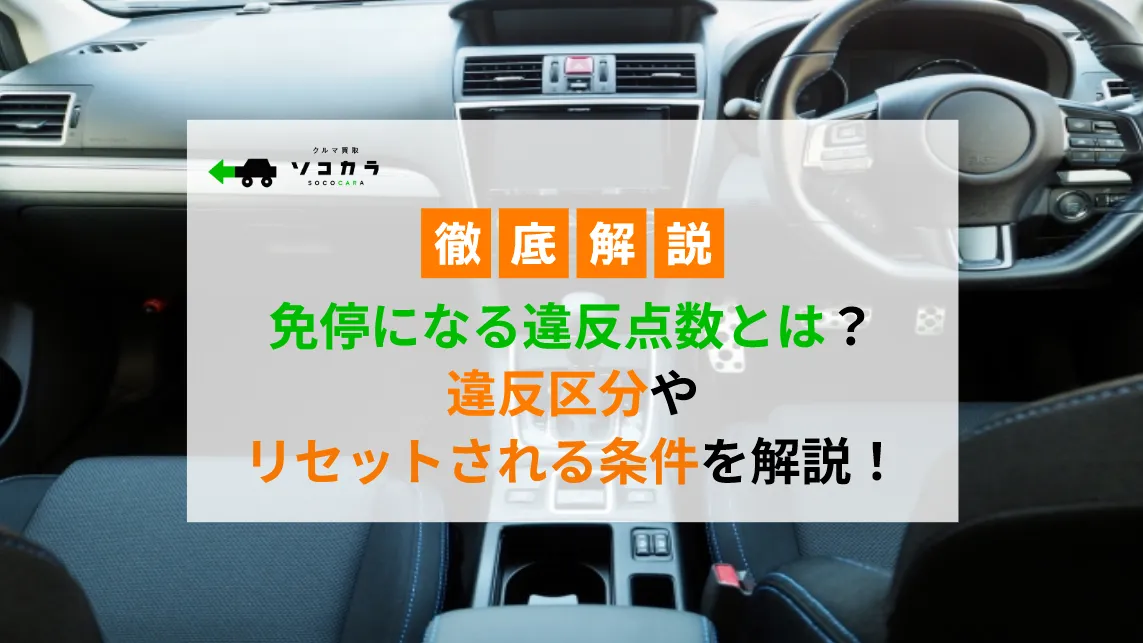
「うっかり違反をしてしまったけど、免停になるのは避けたい…」
「自分の違反点数ってどのくらい?」「点数はどうやったらリセットされるの?」
車の運転中に交通違反をしてしまうと、免許停止になる可能性があります。
免停になる点数は、過去の違反歴の有無によって基準が変動します。
この記事では、免停になる基準や違反点数の仕組み、点数がリセットされる条件、そして実際に免停処分が決定した際の流れについて詳しく解説します。
万が一の事態に備え、正しい知識を身につけておくことが重要です。
あなたの運転免許を守るための基礎知識を身に着けるために、ぜひ本記事を最後までお読みください。
この記事でわかること
- 免停処分と免許取消の違い
- 交通違反の点数一覧
- 免停から免許が返還されるまでの流れ
- 違反点数がリセットされる3つの条件とは?
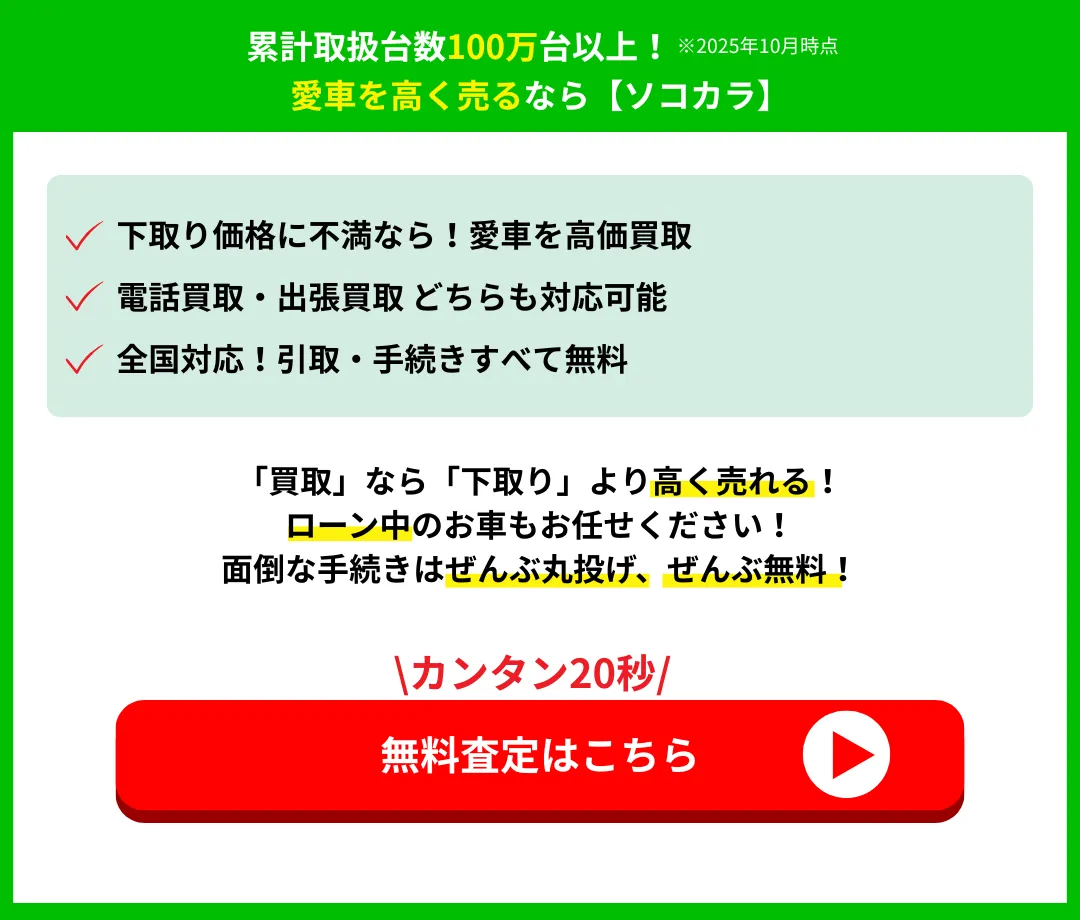
免許停止(免停)処分とは?免許取消との違い
免許停止(免停)とは、交通違反や交通事故によって累積した違反点数が一定の基準に達した際に、一定期間運転免許の効力が停止される行政処分です。
免停期間中は車の運転が一切できなくなります。
一方、免許取消はさらに重い処分で、運転免許そのものが失効します。
免許取消処分を受けると、再度免許を取得するためには、定められた欠格期間を経過した後に改めて運転免許試験を受けなければなりません。
(参考)免許取り消しや再取得、期間について。飲酒運転についても解説。

免停になる違反点数の仕組みを解説
免許停止処分は、交通違反や交通事故の際に付与される違反点数の累積によって決まります。
この制度は、過去の違反行為を点数化し、その累積点数に応じて行政処分を科すことで、危険な運転者を道路から排除し、交通安全を確保することを目的としています。
累積違反点数は過去3年間のものが合算され、さらに過去の行政処分歴(前歴)の回数によって、免停になる基準となる点数が変動する仕組みです。
免停処分は累積6点から!違反点数は過去3年分が合算される
交通違反の点数は、過去3年間のものが合算されて計算されます。
初めて免許停止処分を受ける場合、つまり前歴が0回の場合、累積点数が6点に達した時点で免停になります。
例えば、2点の違反を3回繰り返したり、3点の違反を2回犯したりすると合計6点となり、30日間の免許停止処分を受けます。
ただし、後述する点数のリセット条件を満たしている場合は、それ以前の点数は加算されません。
そのため、自身の過去の違反履歴と現在の点数を把握しておくことが重要です。
| 違反点数(点) | 免許日数(日) |
|---|---|
| 6~8点 | 30日 |
| 9~11点 | 60日 |
| 12~14点 | 90日 |
| 15点~ | 免許取消(1年~10年) |
前歴の回数に応じて免停になる点数が変動する
免許停止や免許取消といった行政処分を受けた経歴を「前歴」と呼びます。
この前歴の回数が増えるほど、より少ない累積点数で再び免許停止処分を受けることになります。
例えば、前歴が1回ある場合は累積4点で60日間の免許停止となり、前歴が2回になると累積2点で90日間の免許停止となる場合があります。
このように、違反を繰り返し、前歴の回数が増えるほど処分基準は厳しく設定されています。
前歴も違反点数と同様に、最後の行政処分から1年間無事故・無違反で過ごすことでリセットされます。
知っておきたい主な交通違反の点数一覧
交通違反は、その内容によって「一般違反行為」と「特定違反行為」の2種類に大別されます。
一般違反行為は信号無視や速度超過など、比較的発生頻度の高い違反を指します。
一方、特定違反行為は飲酒運転や危険運転致死傷など、特に悪質・危険性が高いと判断される重大な違反です。
当然ながら、特定違反行為には非常に重い違反点数が科せられ、一度の違反で免許取消となるケースも少なくありません。
スピード違反や信号無視などの「一般違反行為」
一般違反行為には日常的に起こりうる多くの違反が含まれます。
例えば信号無視(赤色等)は2点、駐停車違反(駐停車禁止場所等)も2点です。
速度違反は超過した速度に応じて点数が異なり、一般道で時速20km未満の超過は1点ですが、20km以上25km未満では2点、25km以上30km未満では3点と上がっていきます。
また携帯電話使用等(交通の危険)は6点であり、これだけで免許停止の対象となる場合があります。
交通違反の点数は、違反の種類や程度によって細かく設定されています。
飲酒運転や危険運転致死傷などの「特定違反行為」
特定違反行為は、交通社会に重大な危険を及ぼす悪質な違反行為を指し、極めて高い点数が設定されています。
例えば、酒酔い運転は35点、酒気帯び運転でも呼気中のアルコール濃度に応じて13点または25点です。
無免許運転も25点、危険運転致死傷罪にあたる行為は最大で62点が科されます。
これらの違反は、一度犯しただけで免許取消処分となるだけでなく、厳しい刑事罰の対象にもなります。
交通ルールの中でも、特に遵守が求められる重大な項目です。
一度の違反で処分対象となる「一発免停」のケース
「一発免停」とは、それまでに違反点数が全くない状態でも、一度の違反で免許停止処分の基準である6点以上に達してしまうケースを指します。
例えば、一般道で時速30km以上50km未満の速度超過をすると、違反点数は6点となり、即座に30日間の免許停止処分が科されます。
同様に、高速道路で時速40km以上50km未満の速度超過も6点です。
違反点数が7点、8点、9点となる違反も存在し、これらは当然ながら免停になる確率が極めて高い違反です。
重大な違反は一回で処分対象となるリスクを常に認識する必要があります。
【4ステップ】免停処分が決定してから免許証が返還されるまでの流れ
交通違反の累積点数が免許停止の基準に達した場合、自動的に処分が開始されるわけではありません。
まず、公安委員会から通知が届き、指定された場所へ出頭して手続きを行う必要があります。
この手続きを経て初めて免許停止期間が開始され、期間が満了すると免許証が返還されます。
また、免停期間は停止処分者講習を受けることで短縮できる可能性があります。
この一連の流れを事前に把握しておくことで、落ち着いて対応を進めることが可能です。
ステップ1:自宅に「行政処分出頭通知書」が届く
違反点数が免許停止の基準に達すると、後日、住民票に登録されている住所地へ「行政処分出頭通知書」という書類が普通郵便またはハガキで届きます。
この通知書には、免許停止処分を受けるために出頭すべき日時と場所(主に運転免許センターなど)が記載されています。
長期の免許停止や免許取消処分の対象となる場合は、「意見の聴取通知書」が届き、処分の前に意見を述べる機会が与えられます。
通知書は必ず確認し、指定された手続きに応じる必要があります。
ステップ2:指定場所へ出頭し免許証を預ける
通知書に記載された指定日時に、運転免許センターや警察署などの指定場所へ出頭します。
その際、運転免許証を持参し、窓口で返納(提出)手続きを行います。
この免許証を預けた日から、免許停止の期間が開始されます。
したがって、出頭する際に自分で車を運転していくことはできません。
公共交通機関を利用するか、誰かに送ってもらうなどの移動手段を確保しておく必要があります。
手続き自体は短時間で終了し、免許停止期間が正式にスタートします。
ステップ3:任意で「停止処分者講習」に参加する
免許停止処分を受けた人は、任意で「停止処分者講習」を受講できます。
この講習は、交通ルールや安全運転に関する講義、運転適性検査などを行い、受講後の試験の成績に応じて免許停止期間が短縮される制度です。
講習は出頭した当日に受講の申し込みができる場合が多く、受講を希望する場合は、講習料金を準備して出頭する必要があります。
受講は義務ではありませんが、停止期間を一日でも短くしたい場合には有効な選択肢となります。
ステップ4:免停期間が終わると免許証が戻ってくる
免許停止期間が満了すると、預けていた運転免許証が返還されます。
停止処分者講習を受けて期間が短縮された場合は、その短縮後の期間が満了した日に返還手続きが可能となります。返還場所は、免許証を預けた運転免許センターや、地域の警察署を選択できる場合があります。
受け取りの際には、運転免許停止処分書が必要となりますが、もし紛失した場合は、本人確認ができる書類(健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持参すれば手続きが可能です。
事前に各都道府県警察のウェブサイトなどで、必要なものを確認しておくことをお勧めします。
この手続きをもって、再び車の運転が可能になります。

免停期間を短縮できる「停止処分者講習」の詳細
免許停止処分を受けた場合でも、「停止処分者講習」を受講し、その後の考査で一定の成績を収めることで処分期間を短縮できます。
この講習は任意参加ですが、日常生活や仕事で車が不可欠な人にとっては重要な制度です。
講習は元の免停期間に応じて内容や日数が異なり、短縮される期間も考査の成績によって変動します。
受講することで、より早く運転を再開できる可能性があります。
免停期間によって異なる講習の種類と料金
停止処分者講習は、免停日数に応じて3つの種類に分けられます。
免停期間が30日の場合は「短期講習」、60日の場合は「中期講習」、90日以上の場合は「長期講習」がそれぞれ設定されています。
講習時間も異なり、短期講習は1日(6時間)、中期講習は2日間(10時間)、長期講習は2日間(12時間)です。
受講料金も講習の種類によって異なり、それぞれ1万円台から2万円台後半の費用がかかります。
受講を希望する場合は、該当する講習の種類と料金を確認しておく必要があります。
| 講 習 | 概 要 |
|---|---|
| 短期講習の対象(30日以下) | 比較的軽微な違反や、過去の違反歴が少ない場合に該当します。 |
| 中期講習の対象(31日~90日) | 違反点数が一定程度蓄積している場合や、悪質な違反があった場合に該当します。 |
| 長期講習の対象(90日以上) | 重大な違反を繰り返した場合や、非常に多くの違反点数が加算された場合に該当します。 |
講習の考査成績で短縮日数が決まる
講習の最後には、内容の理解度を測るための筆記試験(考査)が行われます。
この考査の成績は「優」「良」「可」の3段階で評価され、その結果によって実際に短縮される日数が決定します。
例えば、30日間の免停処分(短期講習)の場合、成績が「優」であれば最大29日間、「良」で25日間、「可」で20日間の短縮となります。
成績が「不可」の場合は短縮されません。
つまり、ただ講習を受けるだけでなく、真剣に取り組み、良い成績を収めることが、停止期間を最大限に短縮するための鍵となります。
累積された違反点数がリセットされる3つの条件
一度累積された交通違反の点数は、永久に残るわけではなく、特定の条件を満たすことでリセットされ、0点に戻ります。
このリセットの仕組みを理解しておくことは、将来の免許停止処分を避ける上で非常に重要です。
主な条件は、一定期間無事故・無違反で過ごすことや、特定の講習を受講することなどがあります。
特に、軽微な違反をしてしまった後、3ヶ月間無事故・無違反を継続することで点数が加算されなくなる特例は知っておくと良いでしょう。
条件1:最後の違反から1年間を無事故・無違反で過ごす
最も基本的なリセットの条件は、最後の交通違反日を起算日として、そこから1年間を無事故・無違反で過ごすことです。
この条件を達成すると、それまでに累積されていた違反点数はすべて0点として扱われ、その後の違反点数計算には加算されません。
また、この場合、免許停止などの行政処分の経歴である「前歴」もカウントされなくなります。
日頃から安全運転を心がけ、1年間違反をしないことが、点数制度上のペナルティを解消する最も確実な方法です。
条件2:2年以上無事故無違反の人が軽微な違反後3ヶ月間無事故無違反を貫く
運転免許を取得してから2年以上、無事故・無違反を継続している人には特例措置が設けられています。
このような人が、点数が3点以下である軽微な違反行為をした場合、その違反の後、3ヶ月間を無事故・無違反で過ごすことができれば、その3点の違反点数は累積計算から除外されます。
これは、日頃から安全運転を心がけている優良運転者に対する救済措置と位置付けられています。
万が一、軽微な違反をしてしまった場合でも、その後の3ヶ月間は特に慎重に運転することが求められます。
条件3:違反者講習を受ける
累積点数が6点に達した場合でも、その内容が軽微な違反(1点、2点、3点)の積み重ねであり、かつ過去に行政処分や違反者講習を受けた経歴がないなどの一定条件を満たすと、「違反者講習」の対象となります。
この講習を受講すると、累積されていた6点はリセットされ、免許停止処分を回避できます。
さらに、行政処分ではないため前歴もつきません。
ただし、この講習の通知を受け取ったにもかかわらず受講しなかった場合は、通常の行政処分として30日間の免許停止処分が科されます。
免停期間と運転への影響
ここからは、運転免許停止処分(免停)を受けた場合の具体的な期間や、その期間中にどのような点に注意すべきか、そして処分終了後に運転を再開する際に知っておくべきことについて解説します。
免停期間は、違反行為の内容や前歴によって異なりますが、その期間を正しく理解し、適切に過ごすことが、再び安全な運転を始めるために非常に重要なポイントです。
免停期間中の過ごし方
免停期間中は、文字通り運転免許が停止されているため、絶対に運転することはできません。
この期間は、違反行為の重大さや過去の違反歴(前歴)によって決定されます。
例えば、一時停止違反で1点の加算であれば免停になることはありませんが、一定期間内に複数の違反を重ねたり、悪質な違反を犯したりすると、30日、60日、90日といった免停期間が科せられます。
この期間中は、運転免許証の効力が停止していることを常に意識し、日常生活においても運転を伴わない移動手段を確保する必要があります。
また、免停期間中に運転が発覚した場合、さらに重い処分が科せられるため、絶対に運転は避けてください。
この期間は、自らの交通違反を深く反省し、今後の安全運転について考える貴重な機会と捉えることが大切です。
免停後の運転
免停期間が終了し、運転を再開する際には、いくつか注意すべき点があります。
まず、運転免許証が停止されていた期間が終了したことを、運転免許証の有効期限や、場合によっては警察署などで確認することが推奨されます。
免停処分を受けたという事実は、運転経歴に記録として残ります。
これは、将来的に再び違反を犯した場合に、免停期間や処分が重くなる「前歴」として影響を与える可能性があります。
そのため、免停期間終了後は、これまで以上に交通ルールを遵守し、安全運転を心がけることが不可欠です。
違反者講習を受講した場合は、その内容を忘れずに実践し、二度と免停処分を受けないように努めましょう。
もし不安がある場合は、安全運転に関する講習などを改めて受講することも有効な手段です。

5. よくある質問(FAQ)
こちらでは、免停や違反点数に関する様々な疑問に、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
読者の皆様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
専門用語は避け、平易な言葉で解説しますので、ご安心ください。
Q:「うっかり違反をしてしまったけど、免停になるのは避けたい…」という場合、どうすれば良いですか?
A:免停を回避するためには、まずご自身の違反点数と、過去の違反歴(前歴)を確認することが重要です。
違反点数が免停基準に達していない場合は、そのまま運転を続けることができます。
もし免停基準に近づいている、あるいは達してしまった場合は、違反者講習の受講を検討しましょう。違反者講習は、一定の条件を満たせば、免停期間を短縮したり、点数を軽減したりする効果があります。
また、今後の違反を避けるために、安全運転を心がけ、交通ルールを再確認することも大切です。違反点数が加算されるような違反は、極力避けるようにしましょう。
Q:自分の違反点数や前歴は、どのように確認できますか?
A:ご自身の違反点数や前歴を確認するには、いくつかの方法があります。
- 運転免許試験場または警察署での確認: 各都道府県の運転免許試験場や、最寄りの警察署の交通課で、運転免許証を提示することで確認できます。
即日発行される場合が多いですが、事前に電話で確認することをおすすめします。 - インターネット(「運転免許・車両情報管理システム」など)での確認: 一部の地域では、インターネットを通じて自分の違反記録や点数を確認できるシステムが導入されています。
お住まいの地域の交通安全協会のウェブサイトなどで、利用可能かどうか調べてみましょう。
これらの方法で、ご自身の現在の違反点数や前歴の有無を確認し、今後の運転に役立ててください。
Q:免停期間中に運転したらどうなりますか?
A:免停期間中の無免許運転は、非常に重い違反行為となります。具体的には、以下の罰則が科せられます。
- 罰則: 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点数: 25点(即時取り消し処分+1年間の欠格期間)
さらに、免停期間中に運転したことが発覚すると、当初の免停処分に加えて、さらに厳しい処分を受けることになります。
免停期間は、免許を安全に再取得するための重要な期間です。
この期間は絶対に運転をせず、免許停止処分を遵守することが、今後の安全なカーライフのために不可欠なことです。
Q:違反者講習を受けないと、免停期間は長くなりますか?
A:はい、違反者講習を受けるかどうかは、免停期間の長さに大きく影響します。
違反者講習には、「初回講習」「違反者講習」「優良運転者講習」の3種類がありますが、免停処分を受けた方が対象となるのは主に「違反者講習」です。
この違反者講習を 受講した場合、違反点数や前歴に応じて、免停期間が短縮されることがあります。
例えば、6ヶ月の免停処分を受けるところ、講習を受けることで期間が30日に短縮されるといったケースがあります。
一方、違反者講習を 受講しなかった場合 は、免停期間が短縮されることはなく、本来の期間(例えば6ヶ月)そのままとなります。
したがって、免停期間を短くしたいのであれば、指定された期間内に講習を受けることが非常に重要になります。
まとめ
免許停止は、前歴がない場合、過去3年間の累積違反点数が6点に達すると対象となります。
この基準は前歴の回数が増えるほど厳しくなり、より少ない点数で処分が科されます。
違反点数は、最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごすなどの条件を満たすことで0点にリセットされます。
万が一、免許停止処分を受けた場合でも、停止処分者講習を受講し、良い成績を収めることで期間の短縮が可能です。
交通違反の点数制度を正しく理解し、日頃から安全運転を心がけることが、免許を守るための基本となります。
車を売却するなら高価買取の「ソコカラ」がおすすめ
本田圭佑さんのテレビCMでおなじみソコカラなら、ピカピカの中古車はもちろん、年式10年以上、10万キロ以上走行、事故車・故障車などどんな車も高価買取いたします!
電話か、出張か高い方の査定を提案するソコカラ独自の2WAY査定で愛車をどこよりも高く買取ります。さらに査定・引取・手続きぜんぶ丸投げ、ぜんぶ無料!
ぜひお気軽に「ソコカラ」(TEL:0120-590-870)にご相談ください。


この記事の監修者
澤井 勝樹
税理士・行政書士 【法律と税務のプロが、クルマの手続きをわかりやすく解説】 1975年生まれ。約10年間の会計事務所勤務を経て、税理士・行政書士登録。IT系ベンチャー企業のIPO(新規上場)準備に携わるなど、企業法務・財務の第一線で活躍。現在は「株式会社はなまる(クルマ買取ソコカラ)」の監査役として、経営の適正性をチェックする立場にある。 複雑になりがちな「廃車手続き」や「自動車税・重量税」などの法律・行政手続きについて、専門家の知見を活かした正確かつ噛み砕いた解説に定評がある。プライベートでは愛車の日産セレナでドライブを楽しむ、家族想いのパパドライバーでもある。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.26
【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.30
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.22
【2026年最新】軽自動車を白ナンバーにする全知識!今選べる種類・費用・手続き・デメリットまで徹底解説
-
-

-
- 故障車のお役立ちコラム
- 2024.11.01
ハンドルを切ると異音がする原因と対処法について詳しく解説!
- ハンドル
- 異音
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.02.05
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-






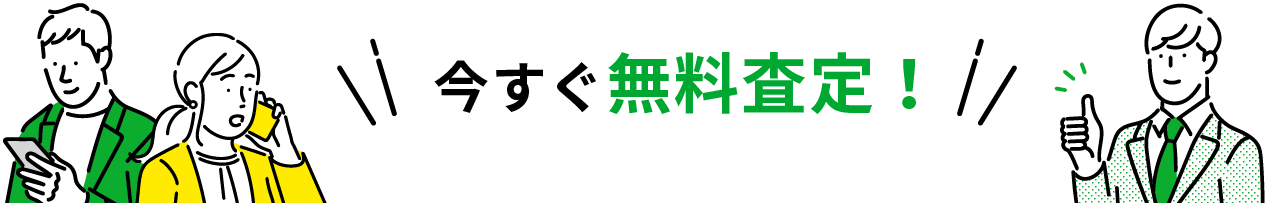




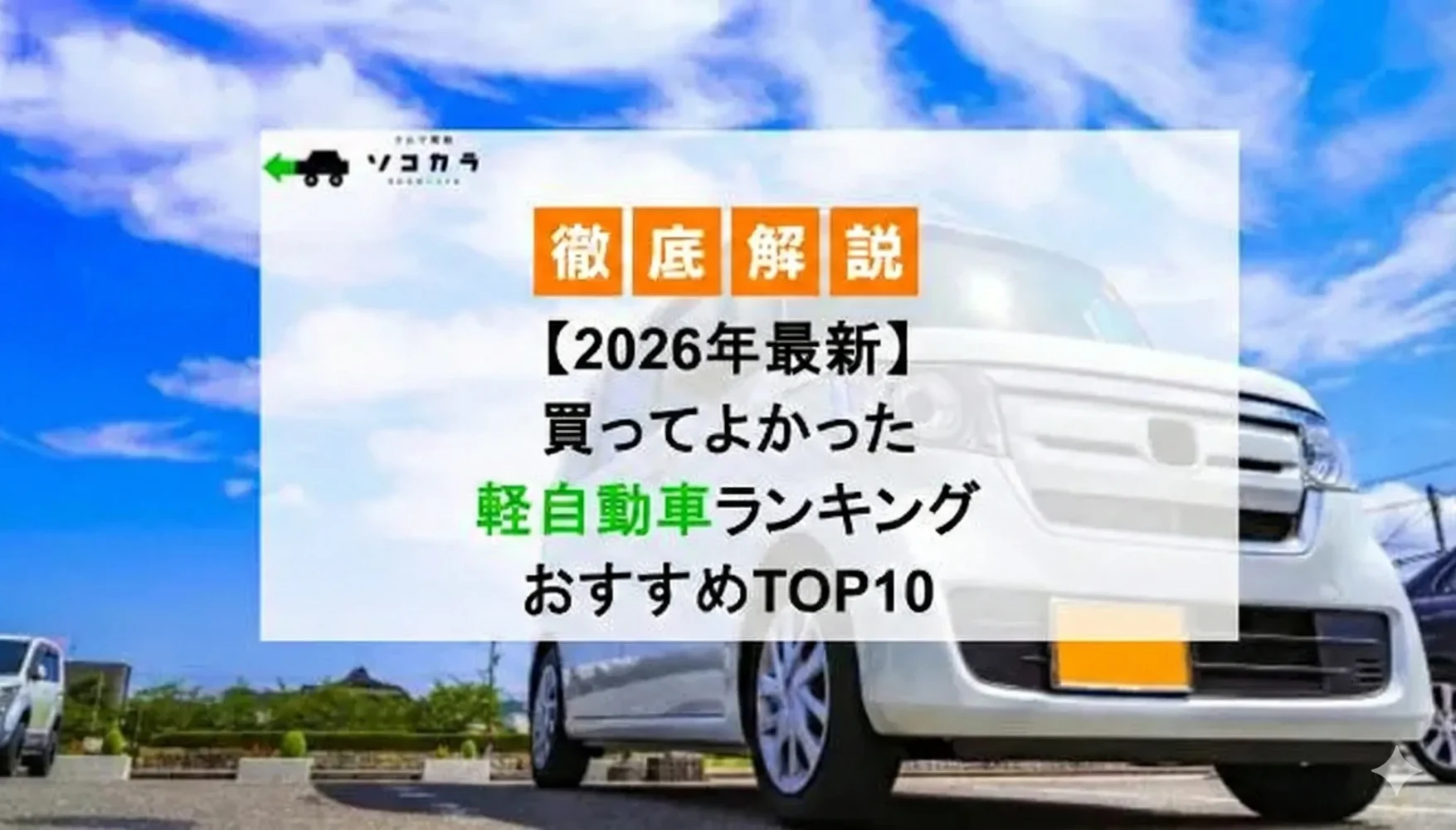


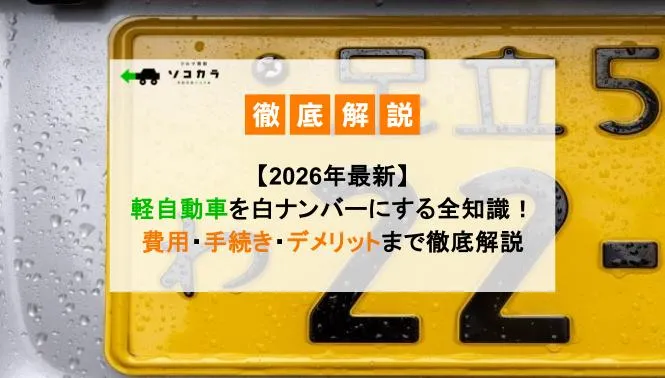

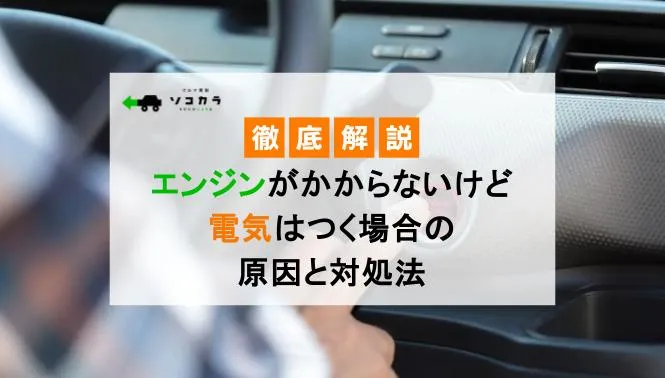

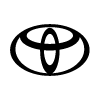
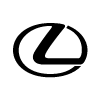
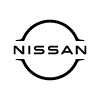

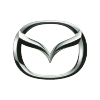


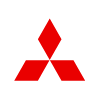









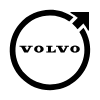

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870