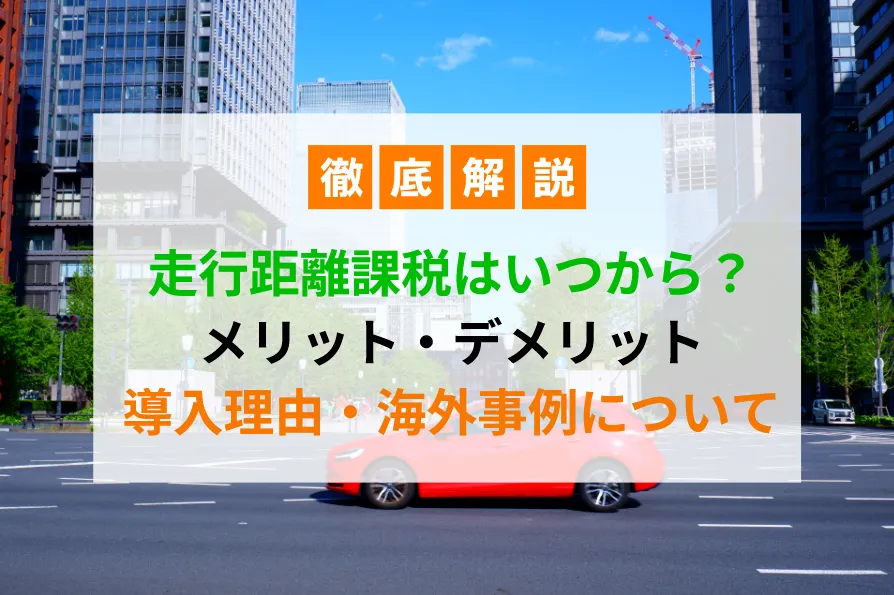
日々自動車を利用されている方にとっては、今話題の「走行距離課税」について大きな関心があるのではないでしょうか。
走行距離課税(走行距離税)は、自動車の利用実態に合わせて税負担の公平性を確保する目的で議論されている新しい税の仕組みです。
電気自動車(EV)の普及など、車を取り巻く環境が変化する中で注目されていますが、導入時期はまだ決まっていません。※2025年11月現在
この記事では、走行距離課税がいつから導入される可能性があるのか、そのメリット・デメリット、そしてなぜ今検討されているのかという理由について、わかりやすく解説します。
ガソリン代の高騰による燃費の悪化によって最新のお車に買換えをご検討中の方もいらっしゃると思います。
ソコカラなら電話か、出張か高い方の査定を提案するソコカラ独自の2WAY査定で愛車をどこよりも高く買取ります。
さらに査定・引取・手続きぜんぶ丸投げ、ぜんぶ無料!
愛車の査定ならお気軽に「ソコカラ」(TEL:0120-590-870)までご相談ください。
この記事のポイント
- 走行距離課税の仕組み
- 走行距離課税の現状と見通し
- 走行距離課税が導入された場合のメリットとデメリット
- 海外での導入事例
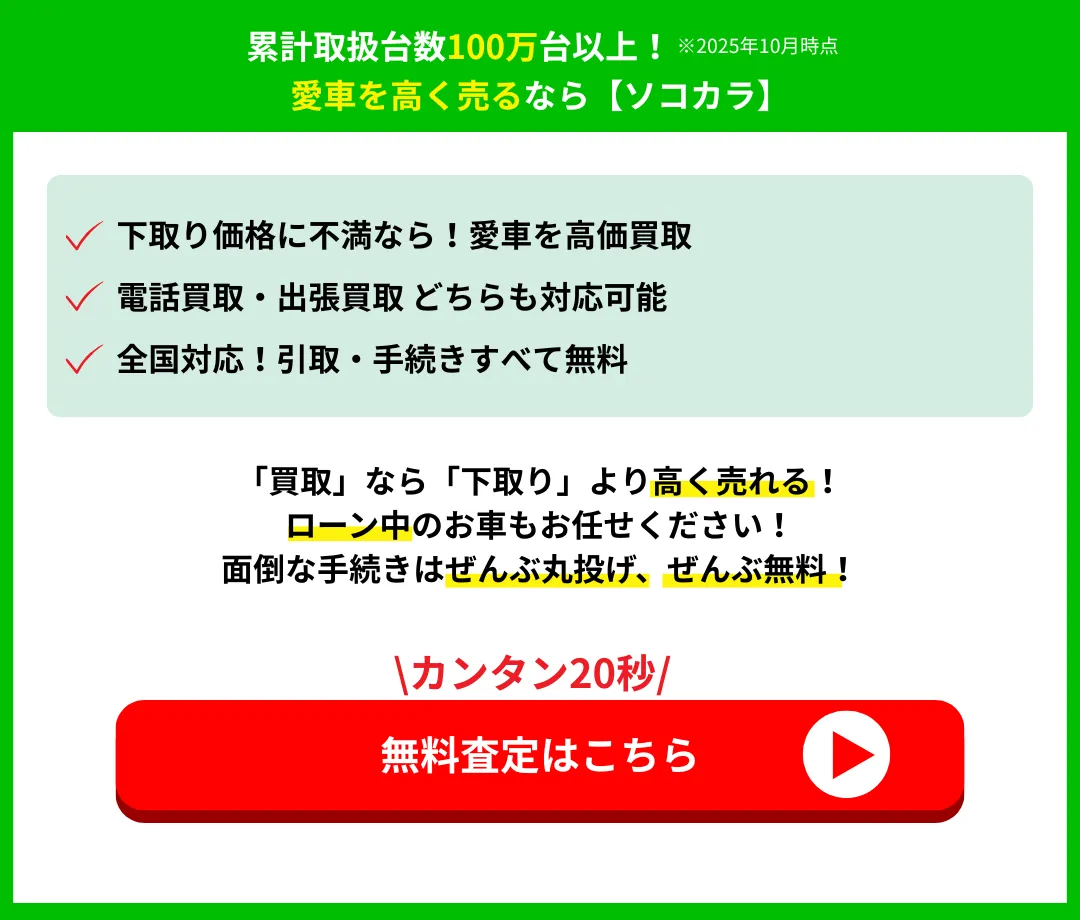
走行距離課税とは?走った分だけ税金を払う新しい仕組み
走行距離課税(走行距離税)とは、その名の通り自動車が走行した距離に応じて課税される税金のことです。
現在の自動車関連の税金は、排気量に応じて課税される「自動車税」や、車検時に納める「自動車重量税」、ガソリン価格に含まれる「ガソリン税」など、主に車の所有や燃料の消費に対して課されています。
これに対し、走行距離課税は「車の利用」そのものに着目した仕組みであり、道路を多く利用する人ほど多くの税金を負担するという考え方に基づいています。

走行距離課税の導入はいつから?現時点での議論の状況
走行距離課税の具体的な導入時期は、現時点では決まっていません。
2022年度の政府税制調査会などで議論の俎上に上りましたが、まだ検討段階にあります。
なぜ導入が検討されているかというと、その背景には電気自動車(EV)の普及という大きな社会変化があります。
ガソリン税に代わる新たな財源確保や、利用実態に応じた公平な税負担の実現が主な理由です。
しかし、国民生活への影響が大きいため、導入には多くの課題があり、慎重な議論が進められている状況です。
走行距離課税の導入が検討される2つの主な理由
走行距離課税の導入が検討される背景には、主に2つの大きな目的があります。
一つは、電気自動車(EV)の普及によって減少が見込まれるガソリン税収入を補うための代替財源の確保です。
もう一つは、現行の排気量で税額が決まる自動車税とは異なり、実際に道路をどれだけ利用したかに応じて負担を求めることで、より公平な税制を目指すという目的です。
これらは、将来の自動車社会を見据えた税体系の再構築を目指す動きといえます。
EV普及によるガソリン税収入の減少を補うため
現在、道路の整備や維持管理費の主な財源は、ガソリンの購入時に支払うガソリン税によって賄われています。
しかし、近年は電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)が普及し、ガソリンの消費量は減少傾向にあります。
特にガソリンを一切使わないEVは、道路を利用しているにもかかわらずガソリン税を負担していません。
このままEVの普及が進むと、道路インフラを維持するための税収が大幅に減少してしまう恐れがあります。
そこで、ガソリン車とEVのユーザー間で生じている税負担の不公平を是正し、新たな財源を確保する手段として走行距離課税が検討されています。
車の利用実態に応じた公平な税負担を実現するため
現行の自動車税(種別割)は、エンジンの排気量によって税額が決められているため、車を所有しているだけで課税されます。
そのため、週末に少し運転するだけの人も、毎日長距離を運転する人も、同じ排気量の車であれば同じ税額を負担しています。
これに対して、走行距離課税は「道路を多く利用する人が、その分多くの維持費を負担すべき」という「応益負担」の考え方に基づいています。
この仕組みが導入されれば、車の利用が少ない人の税負担は軽くなる一方で、利用が多い人の負担は重くなり、より実態に即した公平な税負担が実現できると期待されています。
ただし、地方在住者のように生活のために長距離移動が不可欠な人々の負担が増えることから、反対意見も多く存在します。
カンタン20秒! 愛車の買取なら【ソコカラ】
- 下取りよりも30万円以上お得になる場合も!
ソコカラはダイレクトな海外販路と自社物流網があるので買取価格が高いのが特徴! - ソコカラ独自の「2WAY査定」
電話か出張査定、高く買える方法をおススメするから愛車の価値をしっかり査定! - 査定、引取り、手続き費用は全て無料!
出張査定もレッカー費用も全て無料!査定額が納得いかなければ売らなくてもOKです。
走行距離課税が導入された場合の3つのメリット
走行距離課税の導入は、いくつかのメリットをもたらす可能性があります。
最大の利点は、車の動力源にかかわらず、走行距離という公平な基準で課税できる点です。
これにより、電気自動車とガソリン車の間の税負担の差が是正されます。
また、車を所有していてもあまり乗らない人にとっては、現在の所有ベースの課税から利用ベースの課税に変わることで、負担が軽減される可能性も考えられます。
さらに、既存の税体系の見直し次第では、特定の車種の税負担が変わることもあり得ます。
電気自動車(EV)とガソリン車の税負担が公平になる
現状では、電気自動車(EV)のユーザーはガソリンを消費しないため、道路の維持管理費の主要財源であるガソリン税を負担していません。
一方で、ガソリン車のユーザーは走行するたびに燃料を補給し、間接的に税金を納めています。
走行距離課税が導入されると、動力源の種類に関係なく、すべての車が走行した距離に応じて課税されることになります。
これにより、道路という公共インフラを利用するすべてのユーザーが、その利用度合いに応じて公平に費用を負担する仕組みが実現します。
自動車の電動化が加速する社会において、持続可能な財源を確保し、利用者間の公平性を保つ上で重要なメリットとされています。
日常的にあまり車に乗らない人は税金の負担が軽くなる
現在の自動車税は、車の所有そのものに対して課税されるため、年間の走行距離が極端に短い人でも、毎日通勤で長距離を走る人と同じ税金を支払う必要があります。
例えば、主に週末の買い物にしか車を使わない人や、セカンドカーとして保有しているがほとんど乗らないといったケースです。
走行距離課税は、走った分だけ支払う仕組みであるため、このような車の利用頻度が低いユーザーにとっては、現在の税制度よりも負担が軽減される可能性があります。
所有していることへの負担から、実際に利用した分への負担へとシフトすることで、より個々のライフスタイルに合った合理的な税負担になることが期待されます。
排気量の大きい車は税負担が減る可能性がある
現行の自動車税は、エンジンの排気量が大きくなるほど税額が高くなる仕組みです。
このため、大排気量のスポーツカーや高級セダンなどは、たとえ走行距離が短くても高額な税金が課せられています。
走行距離課税が導入され、それに伴って現在の自動車税が廃止または減額されることになれば、状況は変わる可能性があります。
例えば、趣味で大排気量車を所有し、週末に短距離のドライブを楽しむだけといったユーザーの場合、年間の総走行距離が短ければ、現在の自動車税額よりも納税額が少なくなることが考えられます。
ただし、これは走行距離課税が既存の税金をどう置き換えるかという制度設計に依存するため、あくまで一つの可能性です。

注意したい走行距離課税導入による4つのデメリット
走行距離課税には、メリットがある一方で多くのデメリットや懸念点も指摘されています。
特に、車が生活に不可欠な地方在住者や長距離通勤者にとっては、税負担が現在よりも大幅に増加する可能性があります。
また、物流業界のコスト増を通じて、私たちの生活に関わるさまざまな商品やサービスの価格に影響が及ぶことも懸念されます。
さらに、既存のガソリン税などが存続した場合、二重課税になるのではないかという問題も考えなければなりません。
通勤や生活で長距離移動が必要な人の負担が増加する
公共交通機関が限られている地方や郊外では、多くの人々が通勤、買い物、通院といった日常生活のあらゆる場面で自動車に頼っており、一人当たりの走行距離が長くなる傾向にあります。
これらの地域に住む人々にとって、自動車は贅沢品ではなく生活必需品です。
走行距離課税が導入されると、走行距離が長いほど税負担が重くなるため、こうした人々の家計を直接圧迫する結果となります。
個人の意思や努力で走行距離を減らすことが困難な状況にある人々にとって、この税制は大きな負担増につながり、地域間の経済格差をさらに広げる可能性があるという深刻なデメリットが指摘されています。
物流コストが上がり、さまざまな商品の価格に影響する懸念
日本の物流は、その大半をトラック輸送に依存しており、トラックは業務の性質上、極めて長い距離を走行します。
走行距離課税がトラックなどの事業用車両にも適用された場合、運送会社の税負担は大幅に増加することが避けられません。
この増加したコストは、運送料金に上乗せされる可能性が非常に高いです。
運送料金が上昇すると、生産者から小売店までの輸送コストがかさみ、最終的には食料品、日用品、衣料品といったあらゆる商品の販売価格に転嫁されることが懸念されます。
結果として、国民全体の生活費が上昇し、経済活動全体に悪影響を及ぼす恐れがあります。
タクシーやバス、レンタカーなどの料金が値上げされる可能性
物流業界のトラックと同様に、タクシーや路線バス、高速バス、レンタカーといった旅客運送事業や自動車貸渡事業で使われる車両も、日々の業務で長距離を走行します。
走行距離課税がこれらの事業用車両にも適用されると、事業者の運営コストが直接的に増加します。
このコスト増を吸収するために、タクシーの初乗り運賃や距離加算料金、バスの運賃、レンタカーの利用料金などが値上げされる可能性があります。
これにより、日常的に公共交通機関を利用する人や、旅行・出張で移動サービスを利用する人々の経済的負担が増えることになり、特に自動車を所有していない層の移動の自由を制約する結果にもつながりかねません。
ガソリン税との二重課税になる恐れがある
走行距離課税を導入する上で最も懸念される点の一つが、既存の税金との関係性です。
現在、ガソリン車のユーザーは給油のたびにガソリン税(揮発油税および地方揮発油税)を支払っています。
もし、このガソリン税を維持したまま、新たに走行距離課税が追加されると、ガソリン車のユーザーは「燃料」と「走行距離」という二つの要素で課税されることになり、実質的な二重課税の状態に陥ります。
このような負担増は、納税者の強い反発を招くことが予想されます。
そのため、走行距離課税を導入するのであれば、自動車税や自動車重量税、ガソリン税といった既存の税体系をどのように見直し、廃止または減税するのかをセットで議論し、明確に示すことが不可欠です。

走行距離課税の導入を実現するための3つの課題
走行距離課税の導入は、概念としては公平性があるものの、その実現には多くの技術的・制度的な課題を乗り越える必要があります。
全国に数千万台ある自動車の走行距離を、いかにして正確かつ公平に把握するのかという技術的な問題が最大のハードルです。
また、走行データを収集することによる個人のプライバシー保護の問題や、新たなシステムを構築・運用するための膨大なコストをどう賄うのかといった点も、解決すべき重要な課題として挙げられます。
全国の自動車の走行距離をどうやって正確に把握するのか
走行距離課税を実現するための最大の技術的課題は、全国約8,000万台ともいわれる自動車の走行距離を、いかにして漏れなく公平に、そして不正が行われないように把握するかという点です。
最も簡単な方法としては、車検時にオドメーター(総走行距離計)の数値を記録する方法が考えられますが、これでは車検から次の車検までの2年間(新車は3年)の走行距離しか把握できません。
より正確な課税のためには、GPS機能を備えた専用の車載器(OBD2ポートに接続するタイプなど)を全車両に取り付け、リアルタイムでデータを収集するシステムが必要になると考えられます。
しかし、その設置をどう義務付けるか、またメーターの改ざんといった不正行為をどう防ぐかなど、解決すべき問題は山積しています。
個人の移動データに関するプライバシーをどう保護するのか
GPSなどの技術を用いて走行距離を正確に把握しようとすると、「誰が、いつ、どこからどこへ移動したか」という極めてプライベートな個人の行動履歴データが収集されることになります。
このような詳細な移動情報が、国や関連機関に集約・管理されることに対して、多くの国民がプライバシー侵害の懸念を抱くのは当然のことです。
収集したデータが本来の課税目的以外に利用されたり、外部へ流出したりするリスクも考えられます。
そのため、走行距離課税を導入するには、収集するデータの範囲を必要最小限に留め、厳格な管理体制と強固なセキュリティ対策を法的に整備することが絶対条件となります。
国民の理解を得るためには、プライバシー保護に関する明確なルール作りが不可欠です。
新しいシステム導入や運用にかかる莫大なコスト
全国の自動車の走行距離を管理するための新しいシステムを構築するには、膨大な初期投資と継続的な運用コストが発生します。
例えば、全車両に搭載する専用端末の開発・製造・配布にかかる費用や、全国から送られてくる走行データを収集・処理・管理するための大規模なサーバーや通信インフラの整備費用が必要です。
さらに、導入後もシステムのメンテナンス、データの保守管理、国民からの問い合わせに対応するためのコールセンターの運営など、ランニングコストもかかり続けます。
これらの莫大なコストが、新たに得られる税収を上回ってしまう可能性や、最終的に国民の別の負担増につながる可能性も否定できず、費用対効果の観点から慎重な検討が求められます。

すでに走行距離課税を導入している海外の事例
走行距離課税の検討は日本特有のものではなく、海外ではすでに導入、あるいは試験運用されている国や地域があります。
| 国 | 導入・試験運用の事例 |
|---|---|
| ニュージーランド | ディーゼル車などを対象に「道路利用者料金(RUC)」という形で走行距離に応じた課税制度を導入済みです。 |
| ドイツ | 大型トラックを対象に高速道路の走行距離に応じて課金するシステムが運用されています。 |
| アメリカ | オレゴン州など一部の州では、ボランティア参加による走行距離課税の試験プログラムが実施されており、日本が制度設計を考える上での参考事例となっています。 ユタ州では、EV所有者に対し、「高額な年間登録料(フラットな固定額)」を払うか、「走行距離に応じた課税(従量制)」を払うか、ユーザーが選択できるようにしています。あまり走らない人にとっては距離課税の方が安くなる設計です。 |
海外のトレンドを見ると、「まずはEVや大型車から導入し、GPSやアプリを使ってコストを抑えつつ徴収する」という流れが明確です。
日本でも同様の議論(特にEVに対する課税の公平性)が始まっていますが、プライバシーの保護や地方在住者(走行距離が長い人)への配慮が大きな課題となっています。
カンタン20秒! 愛車の買取なら【ソコカラ】
- 下取りよりも30万円以上お得になる場合も!
ソコカラはダイレクトな海外販路と自社物流網があるので買取価格が高いのが特徴! - ソコカラ独自の「2WAY査定」
電話か出張査定、高く買える方法をおススメするから愛車の価値をしっかり査定! - 査定、引取り、手続き費用は全て無料!
出張査定もレッカー費用も全て無料!査定額が納得いかなければ売らなくてもOKです。
走行距離課税についてのよくある質問と答え
走行距離課税の導入時期は、現時点では未定です。2022年度の政府税制調査会で議論が開始されましたが、まだ具体的な導入には至っておらず、検討段階にあります。
この課税制度は、電気自動車(EV)の普及によるガソリン税収入の減少に対応し、かつ自動車の利用実態に応じた公平な税負担を実現することを目的としています。
導入にあたっては、長距離移動が不可欠な地方住民の負担増、物流コストの上昇、プライバシー保護、走行距離を正確に把握するためのシステム構築費用など、多くの課題が指摘されています。
特に、全国の膨大な数の車両の走行距離をどのように公平かつ正確に計測するのか、またそのデータ管理に伴うプライバシー侵害のリスクをどう低減するのかといった点は、技術的および社会的に大きな問題として挙げられます。
政府はこれらの課題を認識しており、国民生活に与える影響が甚大であることから、非常に慎重な議論を続けています。具体的な制度設計や、これらの課題を解決するための道筋が示されれば、導入時期が明確になる可能性もありますが、現時点では今後の議論の進展を注視する必要があります。
走行距離課税はいつから導入されますか?
走行距離課税の具体的な導入時期は、現在のところ決まっていません。
2022年度の政府税制調査会で議論が開始されましたが、まだ検討段階にあり、具体的な導入時期は未定です。電気自動車(EV)の普及によるガソリン税収入の減少を補うことや、車の利用実態に応じた公平な税負担を実現することが主な目的とされています。
しかし、この制度は国民生活に大きな影響を与えるため、多くの課題が指摘されており、慎重な議論が続けられています。
特に、全国の自動車の走行距離をどのように正確に把握するのか、またそれに伴うプライバシー保護の問題、新しいシステム導入にかかる莫大なコストなどが課題として挙げられます。
これらの課題を解決するための具体的な道筋が示されるまで、導入時期が明確になることは難しい状況です。
走行距離課税は全ての車に適用されますか?
走行距離課税が導入された場合、基本的に「すべての車」が課税対象となる可能性が高いと考えられています。
電気自動車(EV)の普及に伴うガソリン税収の減少を補うことが導入検討の大きな理由の一つであるため、ガソリン車だけでなくEVやハイブリッド車(HV)も含め、すべての動力源の車両が対象となることで、税負担の公平性が確保されるという考え方です。
現行の自動車税は排気量で課税されるため、走行距離の短い大型車は税負担が大きいという不公平感がありましたが、走行距離課税は車両の種類や排気量に関わらず、道路の利用実態に応じて課税される点が特徴です。
しかし、自家用車だけでなく、タクシーやバスといった公共交通機関、あるいは事業用トラックなど、その利用目的によって走行距離が大きく異なる車両への適用については、さらなる議論が必要になります。
例えば、業務上長距離を走らざるを得ない事業用車両に対しては、税負担の急激な増加が避けられないため、料金転嫁による物価上昇や国民生活への影響を考慮し、減免措置や特別な税率を設定するといった配慮が求められるでしょう。
自家用車についても、地方在住者など生活のために長距離移動が不可欠な人々への影響も懸念されており、導入の際にはこれらの例外や緩和策について詳細な検討が必要となります。
まとめ
走行距離課税は、EVの普及といった社会の変化に対応し、税負担の公平性を目指す新しい税の仕組みとして検討されています。
導入されれば、車の利用頻度が低い人の負担が減るなどのメリットがある一方で、地方在住者や物流業界の負担が増加するデメリット、さらには走行距離の把握方法やプライバシー保護といった多くの課題が存在します。
現時点で導入時期は未定であり、国民生活への影響が非常に大きいため、今後も慎重な議論が続けられていく見込みです。
愛車の買換えをご検討中なら「ソコカラ」にご相談ください!
走行距離の多い方にとってはガソリン代や課税の問題は大きな関心があると思います。
最新の燃費の良い車への買換えの検討中であれば、本田圭佑さんのテレビCMでおなじみソコカラにお任せください!
ピカピカの中古車はもちろん、年式10年以上、10万キロ以上走行、事故車・故障車などどんな車も高価買取いたします!
電話か、出張か高い方の査定を提案するソコカラ独自の2WAY査定で愛車をどこよりも高く買取ります。さらに査定・引取・手続きぜんぶ丸投げ、ぜんぶ無料!
愛車の査定ならお気軽に「ソコカラ」(TEL:0120-590-870)までご相談ください。


この記事の監修者
浅野 悠
「株式会社はなまる」小売事業部 事業部長。1987年東京都生まれ。小学生から大学生までの間レーシングドライバーを目指し数多くの大会に出場。20代で飲食店経営に携わったのち、野菜配達の仕事に就くも、幼少期からの車への魅力を忘れられず自動車業界へ。中古車査定士の資格を取得し、自動車に関する豊富な知識をもとに、おもに車に起きるトラブルの対処法や車の豆知識に関するコラムを執筆。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.16
【2025年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.19
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2025年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 故障車のお役立ちコラム
- 2024.10.17
ウォッシャー液が出ないときのための7つのチェックリスト
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2024.09.10
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-
-

-
- 故障車のお役立ちコラム
- 2024.11.01
ハンドルを切ると異音がする原因と対処法について詳しく解説!
- ハンドル
- 異音
-






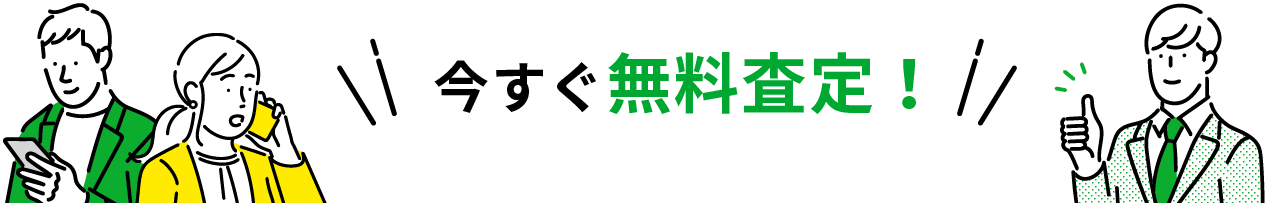




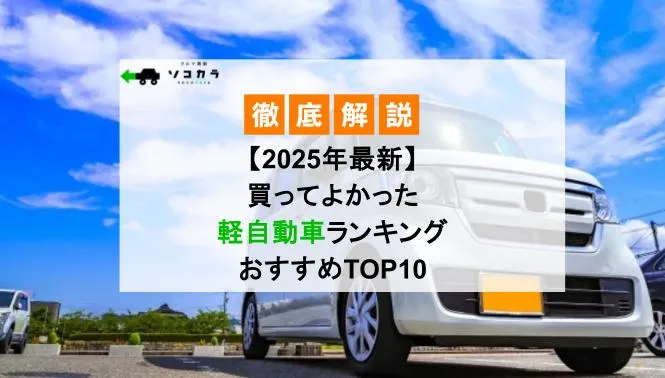


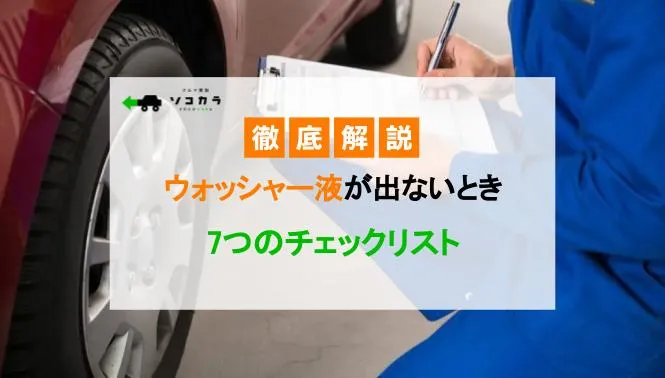
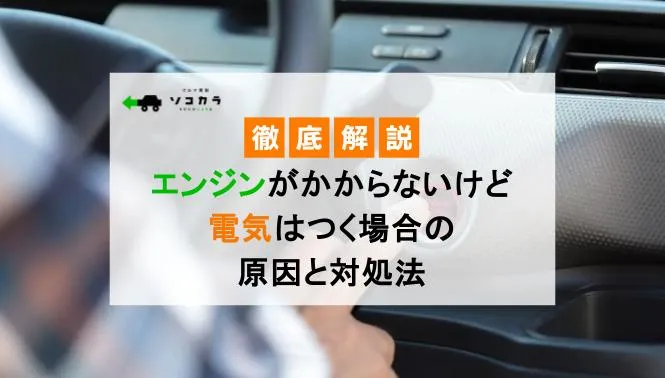


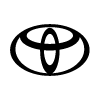
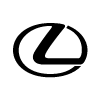
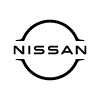

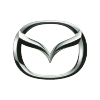


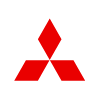









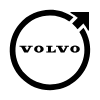

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870