- 2025.09.26
オーバーフェンダーは車検に通る?構造変更と選び方の全て

自分の車を格好よく改造したい、という人も多いでしょう。
タイヤやホイールを大きなサイズに変更することは、手軽にできる改造のひとつです。
その際、オーバーフェンダーが必要になることも多いでしょう。
この記事では、オーバーフェンダーの役割や取り付ける際の注意点、車検を受けるときのポイントなどを解説します。取り付けた後で後悔しないよう、しっかりとチェックしておきましょう。
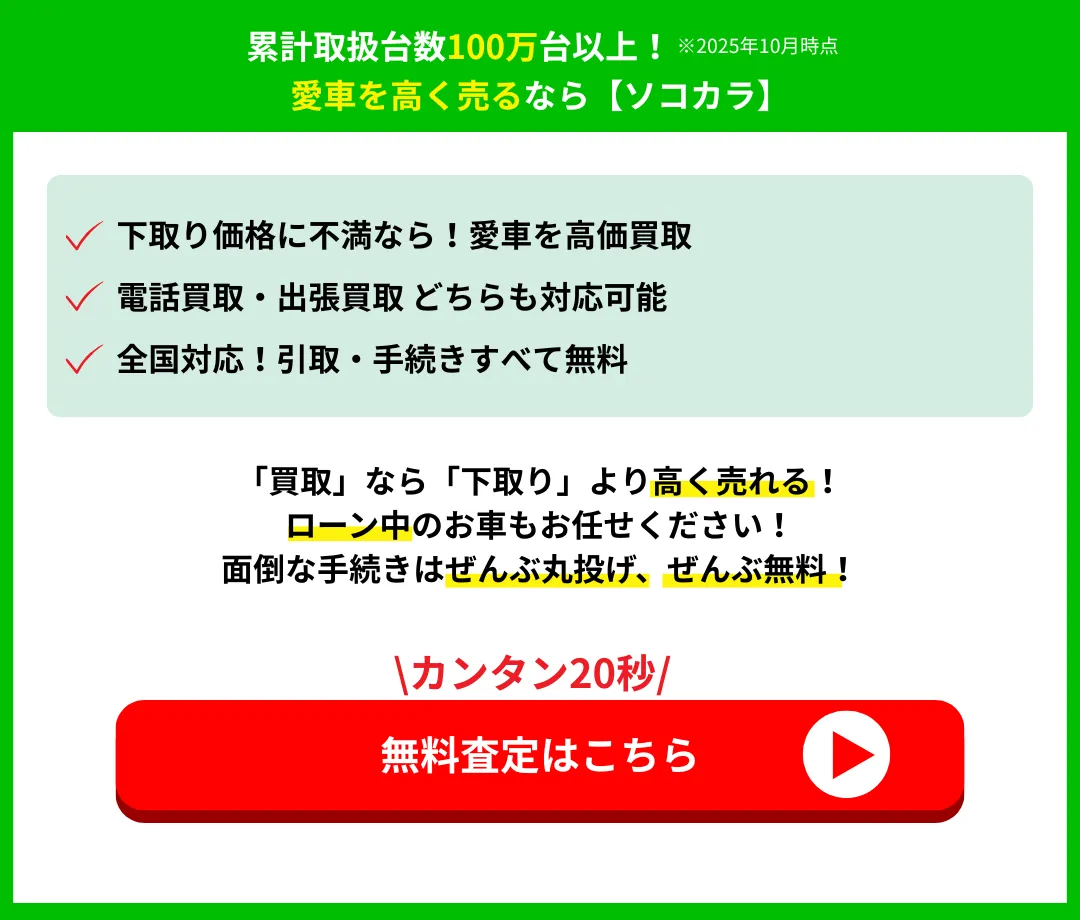
オーバーフェンダーとは
車のタイヤを覆っている泥除け部分、それがフェンダーです。
フェンダーには、タイヤが巻き上げる砂や小石からボディを守り、歩行者との接触を防ぐといった重要な役割があります。(前輪側がフロントフェンダー、後輪側がリアフェンダーです。)
そしてオーバーフェンダーとは、その名の通り、純正フェンダーの上から取り付けてボディをワイドにするためのカスタムパーツです。
より太いタイヤやホイールに交換すると、タイヤがボディからはみ出してしまうことがあります。
日本の保安基準では「タイヤはフェンダーの内側に収めること」が定められているため(※)、この「ハミタイ」状態を解消し、合法的にカスタムを楽しむためにオーバーフェンダーが必要になるのです。
※2017年の基準改正により、タイヤのサイドウォール部(ゴム部分)のみであれば10mm未満のはみ出しは許容されています。
<参考>国土交通省/道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

オーバーフェンダーのメリット・デメリット
オーバーフェンダーの装着を検討するなら、知っておきたいメリット・デメリットを簡潔にまとめました。
【メリット】
- 見た目に迫力が出る
ボディにワイド感が生まれ、どっしりとした力強いスタイリングになります。 - 太いタイヤやホイールが履ける
フェンダーからはみ出すサイズのタイヤ等が装着可能になり、フェンダーとの干渉も防ぎます。 - 泥はねを防ぐ効果
ワイドタイヤが巻き上げる泥や水しぶきから、ボディ側面が汚れるのを軽減します。
【デメリット】
- 運転に注意が必要になる
車幅が広がるため、狭い道でのすれ違いや駐車場では車両感覚に慣れが必要です。 - 構造変更の手間がかかる場合がある
出幅が規定値(合計20mm)を超えると、車検を通すために構造変更申請が必須となります。 - 追加コストがかかる
パーツ代の他に、ボディカラーに合わせた塗装代や取り付け工賃が発生します。
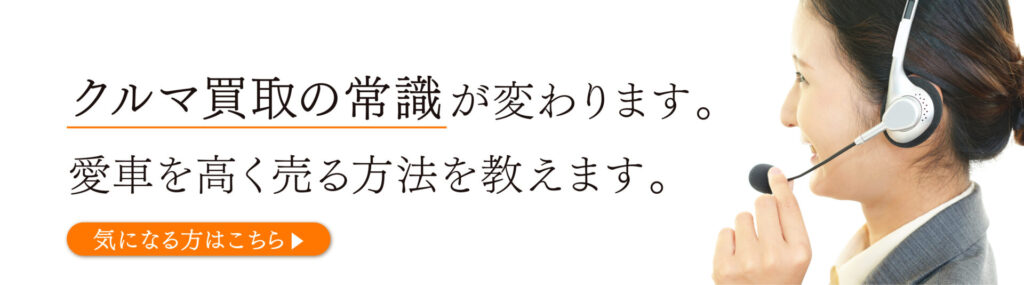
オーバーフェンダーと車検・税金の4つの注意点
オーバーフェンダー付きで車検を受ける場合は、全幅が広がりすぎていないか、固定方法に問題はないか、といったポイントに注意することが大切です。ここでは、4つの注意点を紹介しますので、スムーズに車検を終えられるようチェックしておきましょう。
②拡幅を片側10mm(合計20mm)以内にとどめる
オーバーフェンダーを取り付けることによって、車検証に記載された全幅より20mm以上広げてしまうと車検に通りません。
前述のとおり、タイヤやホイールがフェンダーよりも外側に出てしまうことも避ける必要があるのですが、フェンダーを広げすぎることにも注意しなければならないのです。
車検をスムーズに通すためには、全幅を広げすぎないよう、タイヤやホイール、オーバーフェンダーのサイズに注意しましょう。
仮に、車検証の全幅より20mm以上広げる場合は、後述する構造変更申請が必要です。
②車検証の全幅から20mm以上広げる場合は構造変更申請が必要
オーバーフェンダーの装着などにより、自動車の寸法や重量が一定の範囲を超えて変更された場合、運輸支局などで「構造変更検査」を受ける必要があります。
これを怠ると不正改造となり、公道を走行できなくなります。
申請に必要な書類
構造変更検査を受けるには、以下の書類が必要です。事前にしっかりと準備しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
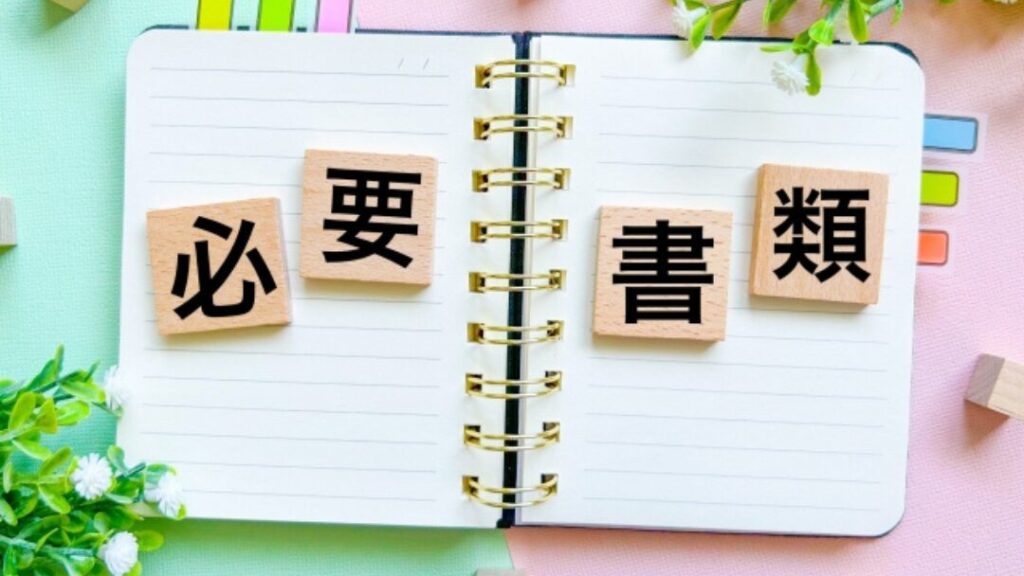
【ご自身で用意・記入が必要な主な書類】
- 自動車検査証(車検証)
原本が必要です。 - 申請書(OCRシート第1号様式など)
運輸支局の窓口で入手できます。
ダウンロードはコチラ:国土交通省 OCR申請書第2号様式のダウンロード - 自賠責保険証
新しい車検の有効期間をすべて満たすものが必要です。 - 記録簿(点検整備記録簿 )
ユーザー車検の場合はご自身で記入が必要です。 - 使用者の委任状
代理人が申請する場合に必要です。本人の認印を押印してください。
【運輸支局で入手・記入する書類】
- 自動車検査票
検査手数料分の印紙を貼り付けます。 - 自動車重量税納付書
重量税分の印紙を貼り付けます。 - 手数料納付書
【場合によって必要な書類】
- 自動車税(種別割)納税証明書
電子的に納税確認ができない場合に必要となることがあります。 - 事業用自動車等連絡書
運送業などで使用する事業用自動車の場合に必要です。
申請時の注意点
構造変更を申請する際は、いくつか注意点があります。
まず、検査に合格した日から新たな車検期間(2年間)が始まるため、元の車検の残存期間は無効になります。
そのため車検満了日が近いタイミングで申請するのが最も効率的です。
また、車両の寸法や重量の変更により、自動車重量税が高くなったり、ナンバーが5ナンバーから3ナンバーへ変更になったりするケースもあります。
当日は通常の車検より審査に時間がかかるため、時間に余裕をもって手続きしましょう。
ご自身での申請が不安な場合は、カスタムショップなどの専門業者に相談することをおすすめします。
関連記事:改造車で事故を起こしてしまった場合の保険、修理、処分費用、事故車買取について解説
③オーバーフェンダーの固定方法に注意する
車検を通すためには、オーバーフェンダーを車体にしっかりと固定しなければなりません。
走行中に外れてしまうような中途半端な取り付け方では、車検は通りません。リベットやビスなどを用いて、正しい方法で固定することが重要です。

④【重要】軽自動車は「普通車扱い」になり、維持費が上がる
ここまでの注意点は普通車と軽自動車に共通しますが、軽自動車の場合はさらに重大な注意点があります。
軽自動車の車幅は1,480mm以内と法律で厳密に定められており、オーバーフェンダーの装着でこの幅を1mmでも超えてしまうと、もはや「軽自動車」としては認められません。
その場合、「構造変更」ではなく、軽自動車(黄ナンバー)から普通車(白ナンバー)への登録変更の手続きが必須となります。これを怠ればもちろん不正改造です。
普通車扱いになると、毎年の軽自動車税がより高額な自動車税に変わるなど、維持費全体に大きな影響が出ます。
軽自動車のカスタムを検討する際は、この「1,480mmの壁」を必ず念頭に置いてパーツを選びましょう。
オーバーフェンダー装着後の注意点
オーバーフェンダーは、スタイリングに大きな変化をもたらす魅力的なパーツですが、装着後はその状態を維持し、安全に走行するために日常的な点検とメンテナンスが欠かせません。
ここでは、装着後に特に気をつけたいポイントを解説します。
定期的な「緩み・ガタつき」のチェック
走行中の脱落は重大な事故につながるため、最も重要なチェック項目です。
洗車時などに手で軽く揺すり、ビス止めなら緩みがないかも目視で確認する習慣をつけましょう。
「割れ・ヒビ」など損傷の確認
縁石への接触や飛び石などで、オーバーフェンダーは意外と傷つきやすい部分です。
小さなヒビを放置すると、走行中の振動で亀裂が広がり、パーツが破損・落下する原因になります。
見つけたら早めに補修しましょう。
タイヤとの干渉がないか
大きな段差を乗り越えたり、ハンドルを大きく切ったりした際に、タイヤと干渉していないか注意が必要です。
「ゴリゴリ」という異音や、フェンダー内部の擦れ跡は干渉のサインです。
洗車時のポイント
高圧洗浄機を接着面に強く当てると剥がれの原因になるため、少し離して使いましょう。
また、ボディとの隙間に溜まった砂や泥は、塗装傷やサビの原因になるため、優しく洗い流すことが大切です。
変化した車幅感覚に慣れる
片側数センチでも車両感覚は大きく変わります。
装着直後は特に、狭い道でのすれ違いや駐車場の白線を意識するなど、広がった車幅に慣れるまで慎重な運転を心がけてください。
これらの日常的なチェックを習慣づけることで、トラブルを未然に防ぎ、愛車を安全かつ良いコンディションで長く楽しむことができます。
オーバーフェンダーの選び方

購入後に後悔しないために以下の点をチェックしましょう
まずは「車検対応」かを確認
最も重要なポイントです。車検証の幅から片側10mm(合計20mm)以内の出幅であれば、構造変更の申請は不要です。これを超える製品は構造変更が必要になるため、購入前に必ず確認しましょう。
愛車のスタイルに合う「デザイン」を選ぶ
ワイルドな「ビス止め風」や、ボディに自然に馴染む「純正風」など、デザインは様々。
ご自身のカスタムの方向性に合ったものを選ぶのが成功の秘訣です。
用途に合わせた「素材」を選ぶ
デザインの自由度が高い「FRP製」や、衝撃に強くフィッティング精度が高い「ABS樹脂製」が主流です。
価格や耐久性のバランスを見て選びましょう。
「トータルコスト」で予算を考える
パーツ本体の価格だけでなく、塗装代や取り付け工賃も忘れずに予算に含めましょう。
安価な製品は、取り付けに別途加工費がかかる場合もあるので注意が必要です。
オーバーフェンダーの取り付け方法
取り付けはDIYでも可能ですが、プロに依頼すれば確実で美しい仕上がりになります。
DIYで挑戦する場合
コストを抑えられますが、ボディへの穴あけなど後戻りできない作業が伴うため慎重さが必要です。
基本的な流れは、マスキングテープで入念に位置を決めてからドリルで穴をあけます。
この際、穴の断面にタッチアップペンなどで防錆処理を施すのが、サビを防ぐ重要なポイントです。
その後ビス等で確実に固定し、ボディとの隙間をコーキング剤で防水処理して完成です。
左右のズレは非常に目立つため、丁寧な作業を心がけましょう。
プロに依頼する場合
工賃の相場は30,000円~100,000円前後(塗装代別途)が目安ですが、パーツの精度や加工の有無で大きく変動します。
依頼する際は、エアロパーツの取り付け実績が豊富なカスタムショップや板金塗装工場に相談するのがおすすめです。
料金や作業内容(防水・防錆処理の有無など)を比較するため、複数の店舗で見積もりを取ると良いでしょう。
最後に:オーバーフェンダーを楽しむための3つのポイント
オーバーフェンダーカスタムを成功させるため、最後に重要なポイントを3つに絞ってご紹介します。
①車検のルールは必ず守る
合計20mm以上の拡幅には「構造変更」が必要です。知らずに違法改造とならないよう、事前の確認を徹底しましょう。
②費用は「トータル」で考える
パーツ代だけでなく、塗装や取り付け工賃を含めた総額で予算を組むのが失敗しないコツです。
③ 装着後も「点検」を習慣にする
走行中の脱落などを防ぐため、緩みや損傷がないか定期的なチェックが欠かせません。
これらのポイントを押さえて、安全で楽しいカスタムライフをお送りください!
本田圭佑さんのテレビCMでおなじみソコカラなら、ピカピカの中古車はもちろん、年式10年以上、10万キロ以上走行、事故車・故障車などどんな車も高価買取いたします!電話か、出張か高い方の査定を提案するソコカラ独自の2WAY査定で愛車をどこよりも高く買取ります。さらに査定・引取・手続きぜんぶ丸投げ、ぜんぶ無料!ぜひお気軽に「ソコカラ」(TEL:0120-590-870)にご相談ください。


この記事の監修者
浅野 悠
中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.16
【2025年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.19
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2025年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 故障車のお役立ちコラム
- 2024.11.01
ハンドルを切ると異音がする原因と対処法について詳しく解説!
- ハンドル
- 異音
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2024.09.10
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.06.24
車のシート汚れを自分で落とす!素材別・プロ直伝の洗浄方法を徹底解説
- メンテナンス
-






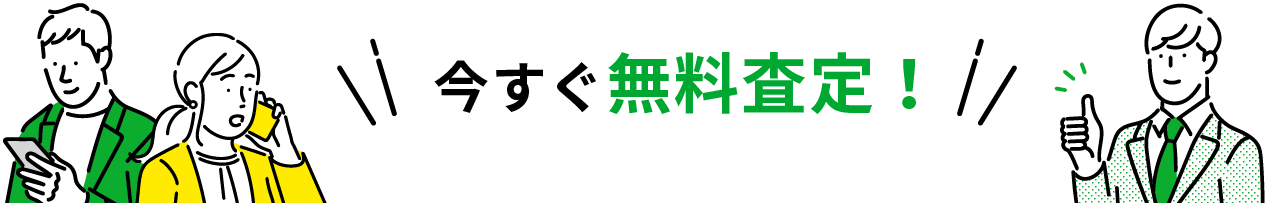




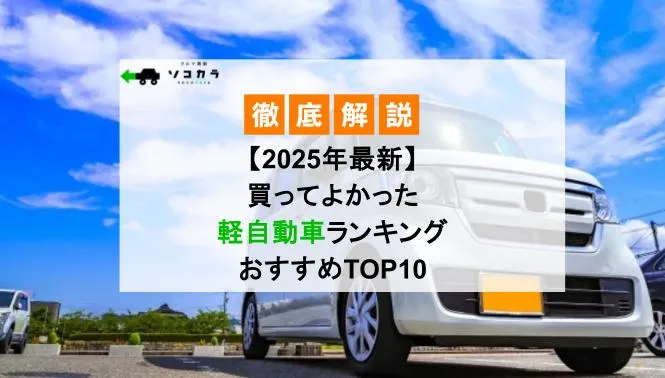



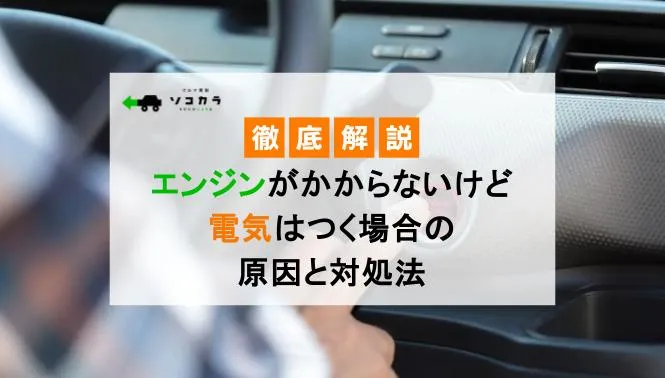
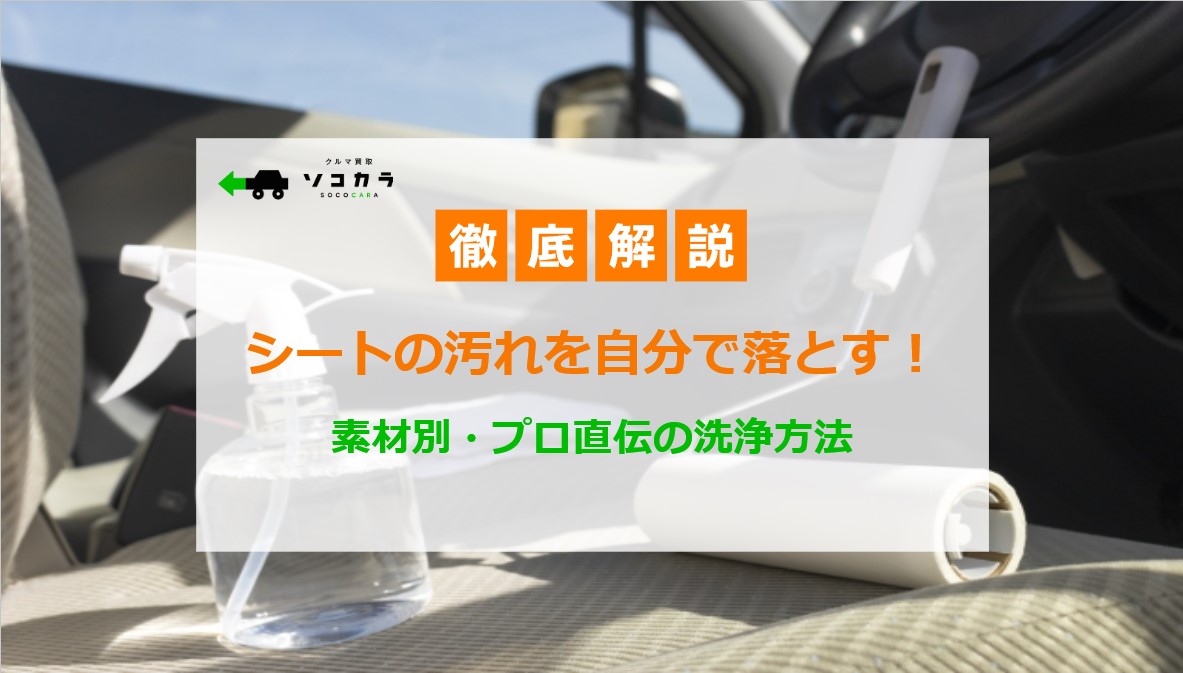

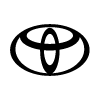
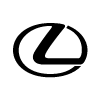
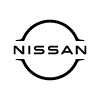

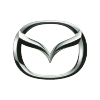


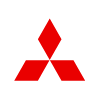









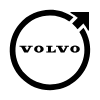

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870