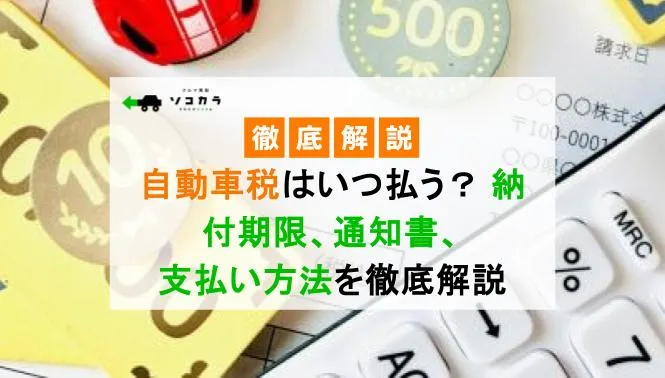
自動車を所有しているあなた。「自動車税、また払う時期か…」と、少し憂鬱な気持ちになったことはありませんか? 納付期限をうっかり忘れてしまったり、支払い方法がよく分からなかったり、と何かと不安を感じる方もいるでしょう。
この記事では、自動車税の納付期限や通知書、支払い方法、滞納してしまった場合のリスクまで、知っておくべき情報を分かりやすく解説します。この記事を読めば、自動車税に関する不安を解消し、スムーズに納付できます。
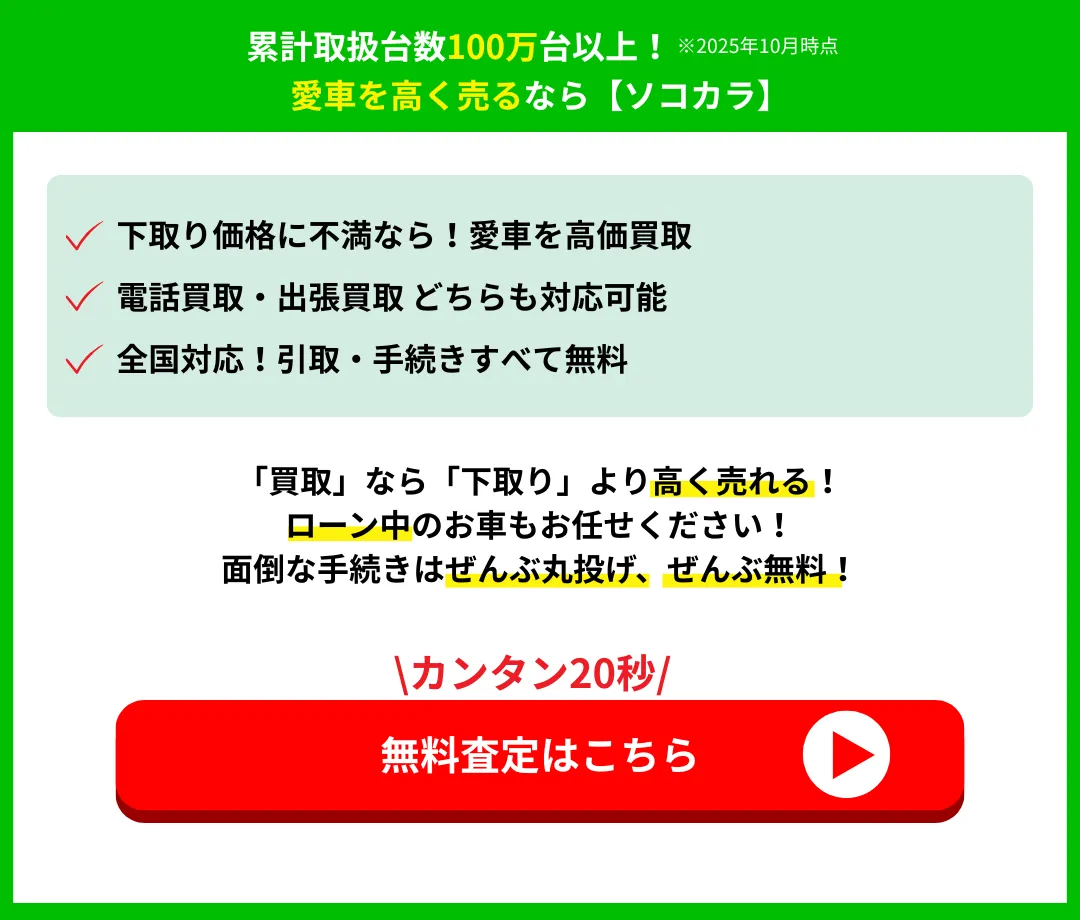
自動車税とは? 基本的な情報をおさらい
自動車税の対象となる車
自動車税は、4月1日時点で車を所有している人にかかる税金です。対象となるのは、道路運送車両法に定められた、主に以下の車両です。
- 自動車(普通車)
セダン、クーペ、ステーションワゴンなど - 軽自動車
軽乗用車、軽貨物車など - 小型二輪車
排気量250ccを超えるバイク
これらの車両は、その用途や排気量などに応じて税額が異なります。自家用車だけでなく、事業用車も対象となります。
自動車税の税額
自動車税の税額は、車の排気量や用途によって異なります。税額は各都道府県によって定められており、見直しが行われる場合があります。
税額は、車の排気量や用途だけでなく、その時の社会情勢や税制改正によって変動します。過去には、エコカー減税の導入や、ガソリン車の税率変更など、様々な見直しが行われてきました。
具体的な見直しの頻度は、税制改正のタイミングによりますが、数年に一度程度、あるいはそれ以上の頻度で見直されることもあります。
一般的に、排気量が大きいほど、税額も高くなります。また、車の種類(自家用・事業用など)によっても税額が変わることがあります。
2019年10月以降に車を購入した場合は新税額で課税され、2019年9月までに購入した場合は今後も今まで通りの税額で課税されます。
| 排気量 | 2019年9月までに購入 | 2019年10月以降に購入 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 1万800円 | 1万800円 |
| 1000cc以下 | 2万9500円 | 2万5000円 |
| 1000cc超~1500cc以下 | 3万4500円 | 3万500円 |
| 1500cc超~2000cc以下 | 3万9500円 | 3万6000円 |
| 2000cc超~2500cc以下 | 4万5000円 | 4万3500円 |
| 2500cc超~3000cc以下 | 5万1000円 | 5万0000円 |
| 3000cc超~3500cc以下 | 5万8000円 | 5万7000円 |
| 3500cc超~4000cc以下 | 6万6500円 | 6万5500円 |
| 4000cc超~4500cc以下 | 7万6500円 | 7万5500円 |
| 4500cc超~6000cc以下 | 8万8000円 | 8万7000円 |
| 6000cc超 | 11万1000円 | 11万0000円 |
エコカー減税の対象となる車は、この税額が軽減される場合があります。詳細は、後述の「自動車税に関する減税制度」で解説します。
自動車税の納税通知書について
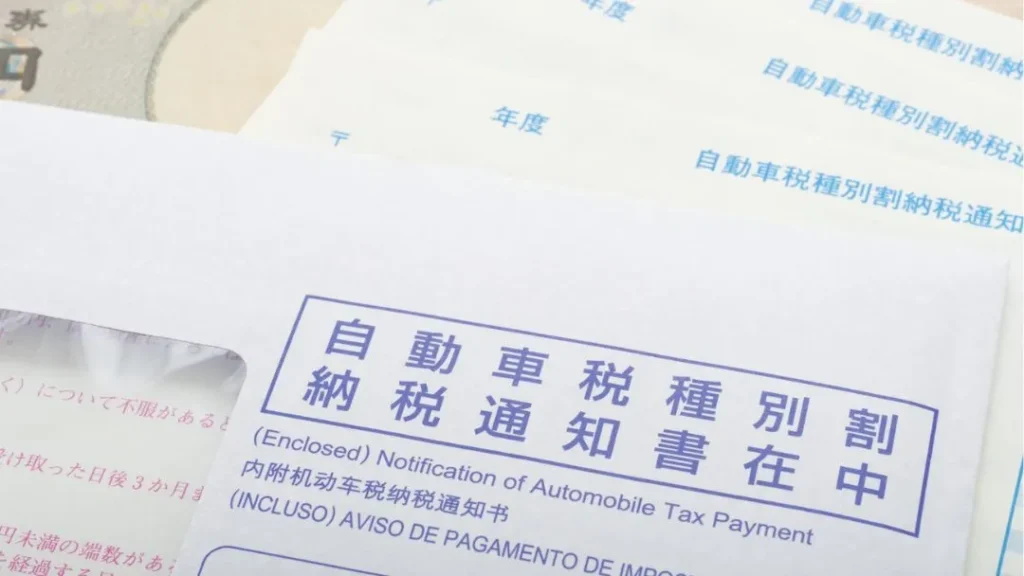
納税通知書はいつ届く?
自動車税の納税通知書は、通常、5月上旬から中旬にかけて、車の所有者の住所に郵送されます。この通知書には、自動車税の金額、納付期限、納付方法などが記載されています。
もし、5月中旬を過ぎても通知書が届かない場合は、まず以下の点を確認しましょう。
- 転居の有無
最近引っ越しをした場合は、住所変更の手続きが済んでいるか確認してください。 - 郵便物の確認
郵便受けを確認し、他の郵便物に紛れていないか確認してください。 - 税事務所への問い合わせ
上記を確認しても通知書が見つからない場合は、お住まいの都道府県の税事務所に問い合わせましょう。問い合わせる際には、車検証を手元に用意しておくとスムーズです。
納税通知書の確認事項
納税通知書が届いたら、まず記載内容に間違いがないか確認しましょう。特に以下の点に注意が必要です。
- 車の情報
車名、登録番号、車台番号などが正しいか確認します。もし、記載事項に誤りがある場合は、税事務所に連絡して訂正してもらいましょう。 - 税額
自動車税の金額が、自分の車の排気量や種類に合っているか確認しましょう。減税制度の対象となっている場合は、その旨が記載されているか確認してください。 - 納付期限
納付期限を必ず確認し、期限内に納付するようにしましょう。納付期限を過ぎると、延滞金が発生する可能性があります。 - 納付方法
納付方法が記載されています。自分の都合の良い方法で納付しましょう。
納税通知書は、自動車税の納付に関する重要な情報源です。記載内容をしっかりと確認し、不明な点があれば、税事務所に問い合わせて疑問を解消するようにしましょう。
自動車税の納付期限と支払い方法

納付期限はいつ?
自動車税の納付期限は、通常、5月31日です。ただし、都道府県によって異なる場合があるため、納税通知書に記載されている期日を必ず確認してください。
もし、5月31日が土日祝日の場合は、次の平日が納付期限となります。期日を過ぎると、延滞金が発生する可能性がありますので、注意が必要です。
納付方法の種類
自動車税の納付方法は、多岐にわたります。自分に合った方法を選び、期日内に納付しましょう。
- 金融機関
銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関の窓口で納付できます。現金での支払いが可能です。 - コンビニエンスストア
納税通知書を持参し、コンビニのレジで納付できます。24時間営業の店舗が多いので、自分の都合に合わせて納付できます。 - クレジットカード
地方税お支払サイトなどを利用して、クレジットカードで納付できます。ポイントが貯まるなどのメリットがあります。 - Pay-easy
銀行ATMやインターネットバンキングから、Pay-easy(ペイジー)を利用して納付できます。 - スマートフォン決済
スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINE Payなど)を利用して納付できます。自宅や外出先から手軽に納付できるのがメリットです。 - 口座振替
事前に口座振替の手続きをしておけば、自動的に口座から引き落としされます。納付の手間が省けるので便利です。
これらの納付方法の中から、自分に合った方法を選びましょう。それぞれの方法には、メリットとデメリットがありますので、比較検討することをおすすめします。
関連記事:自動車税の計算方法と仕組みについて
自動車税を滞納するとどうなる?

滞納によるペナルティ
自動車税を滞納すると、様々なペナルティが発生します。まず、納付期限の翌日から延滞金が発生します。この延滞金は、滞納期間に応じて加算され、最終的な税額を大きく押し上げる可能性があります。
さらに、滞納を続けると、督促状が送付されます。督促状にも従わずに滞納を続けると、最終的には財産が差し押さえられる可能性があります。車だけでなく、預貯金や給与なども差し押さえの対象となるため、注意が必要です。
また、自動車税を滞納している間は、車検を受けることができません。車検が切れた状態で公道を走行すると、法律違反となり、罰金や違反点数の加算、さらには免許停止処分となる可能性があります。
関連記事:自動車税を滞納すると差し押さえもされる!いつからか、解除の要件などを徹底解説
滞納した場合の対応
万が一、自動車税を滞納してしまった場合は、速やかに対応することが重要です。まず、お住まいの都道府県の税事務所に連絡し、滞納している自動車税の金額を確認しましょう。延滞金を含めた正確な金額を確認し、納付方法について相談してください。
納付の意思を示し、速やかに納付を行うことで、差し押さえなどの事態を避けることができます。分割払いや納付猶予などの相談にも応じてもらえる場合がありますので、まずは相談してみましょう。
もし、納付が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討してください。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応策を見つけることができるかもしれません。滞納してしまった場合でも、諦めずに、できる限りの対応をとることが大切です。
自動車税に関する減税制度
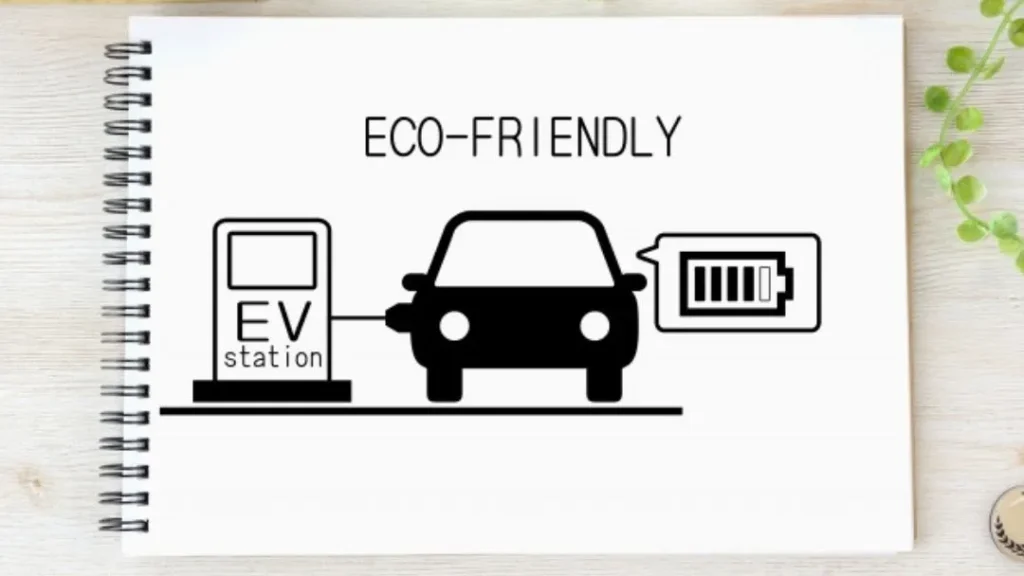
エコカー減税とは
エコカー減税は、環境性能に優れた自動車に対して、自動車税や自動車取得税を減税する制度です。この制度は、地球温暖化対策や大気汚染防止を目的としており、自動車の普及促進と環境負荷の低減を両立させることを目指しています。
エコカー減税の対象となる自動車は、燃費性能や排出ガス性能に応じて区分されます。
具体的には、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、クリーンディーゼル車などが対象となります。これらの車両は、排出ガスが少なく、燃費性能に優れているため、税制上の優遇措置が受けられます。
エコカー減税の具体的な減税内容は、自動車の購入時期や車種によって異なります。自動車取得税は免税または軽減され、自動車税も概ね1年間減税されます。
減税額は、車両の性能やグレードによって異なり、最大で自動車税が75%減税されることもあります。
また、エコカー減税は、新車だけでなく、中古車にも適用される場合があります。中古車の場合は、車両の年式や燃費性能などによって減税の対象となるかどうかが判断されます。
参考:エコ発電本舗
エコ発電本舗では「太陽光発電」「蓄電池」「V2H」を販売しております。
特にV2Hの販売に注力しており、V2Hを導入することで充電コストや電気代の削減、EV・PHEVを停電時の非常用電源として活用できます。
その他の減税制度
自動車税には、エコカー減税以外にも、様々な減税制度が存在します。これらの制度は、自動車の用途や所有者の状況などに応じて適用され、税負担を軽減するものです。
例えば、一定の条件を満たす障害者の方が所有する自動車に対しては、自動車税が減免される制度があります。この制度は、障害者の移動の自由を確保し、社会参加を支援することを目的としています。
減免の対象となる自動車や減免額は、障害の種類や程度、自動車の使用目的などによって異なります。
また、自動車の用途によっては、自動車税が軽減される場合があります。例えば、特定の事業用車両や、福祉車両などは、税率が軽減されることがあります。
これらの制度は、特定の産業の発展を支援したり、社会的なニーズに対応するために設けられています。
さらに、2024年度の税制改正により、自動車税のグリーン化特例が見直されました。これは、環境負荷の少ない自動車に対する優遇措置であり、電気自動車や燃料電池自動車などの普及を促進するためのものです。
これらの減税制度は、自動車税の負担を軽減し、環境に配慮した自動車の普及を促進するためのものです。
関連記事:税金は排気量2500ccで変わる? 車にかかる税金のすべてを解説!
自動車税に関するよくある質問(FAQ)
自動車税を払い忘れた場合はどうすればいい?
自動車税を払い忘れてしまった場合、まずは落ち着いて、速やかに対応しましょう。まずは、納付書が手元にあるか確認してください。
もし、紛失してしまった場合は、お住まいの都道府県の税事務所に連絡して、再発行の手続きを行いましょう。再発行された納付書を使って、コンビニエンスストア、金融機関、クレジットカード、Pay-easyなど、利用可能な方法で納付できます。
もし、納付期限を過ぎてしまっていても、諦めずに納税するようにしましょう。未納の状態を放置すると、延滞金が発生したり、車検が受けられなくなるなどの不利益を被る可能性があります。
引っ越しをした場合、自動車税の手続きは?
引っ越しをした場合、自動車税に関する手続きが必要になる場合があります。まず、都道府県が変わる場合は、新しい住所を管轄する税事務所に、車検証や納税通知書を持参して、住所変更の手続きを行いましょう。
この手続きを行うことで、新しい住所に納税通知書が送付されるようになります。都道府県が変わらない場合は、原則として住所変更の手続きは不要です。
しかし、念のため、お住まいの税事務所に確認することをおすすめします。住所変更の手続きを怠ると、納税通知書が届かず、納付が遅れてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
自動車税に関する相談窓口は?
自動車税に関する疑問や不明な点がある場合は、専門の相談窓口に問い合わせてみましょう。まず、納税通知書に記載されている、お住まいの都道府県の税事務所に問い合わせることができます。
税事務所では、自動車税の仕組みや手続きについて、詳しく教えてもらえます。また、電話や窓口での相談だけでなく、ウェブサイトでよくある質問(FAQ)が公開されている場合もありますので、参考にしてみましょう。
さらに、自動車に関する専門家である、行政書士や税理士に相談することも可能です。これらの専門家は、個別の状況に応じたアドバイスをしてくれます。
まとめ
自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者にかかる税金です。対象となるのは、自動車(普通車)、軽自動車、小型二輪車などです。税額は車の排気量や用途によって異なり、エコカー減税の対象となる車は軽減される場合があります。
納税通知書は、通常5月上旬から中旬に車の所有者の住所に郵送されます。記載内容(車の情報、税額、納付期限、納付方法)を確認し、間違いがあれば税事務所に連絡しましょう。
納付期限は通常5月31日ですが、納税通知書で確認が必要です。納付方法は、金融機関、コンビニエンスストア、クレジットカード、Pay-easy、スマートフォン決済、口座振替などがあります。
自動車税を滞納すると、延滞金が発生し、督促状が送付され、最終的には財産が差し押さえられる可能性があります。また、車検も受けられません。滞納した場合は、税事務所に連絡し、納付方法を相談しましょう。
エコカー減税など、自動車税には様々な減税制度があります。エコカー減税は、環境性能に優れた自動車が対象で、自動車税や自動車取得税が減税されます。
自動車税に関する疑問がある場合は、税事務所や専門家に相談しましょう。引っ越しをした場合は、住所変更の手続きが必要になる場合があります。
クルマ買取はソコカラ
自動車税に関する疑問や不安は、この記事で解消できたでしょうか?
自動車税についてもっと知りたい方は、ぜひソコカラの「クルマ買取」サービスもチェックしてみてください。愛車を売却することで、自動車税の負担を軽減できる可能性があります。
廃車買取では、自動車税に関する相談はもちろん、廃車手続きに関する疑問にもお答えします。
あなたの愛車を高く売却し、自動車税の負担を軽減することも可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください!


この記事の監修者
浅野 悠
中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.26
【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.30
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2024.09.10
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 故障車のお役立ちコラム
- 2024.10.17
ウォッシャー液が出ないときのための7つのチェックリスト
-
-

-
- 廃車のお役立ちコラム
- 2024.08.09
トラブル回避!陸運局で使える委任状・譲渡証明書の書き方【記入例付き】
-






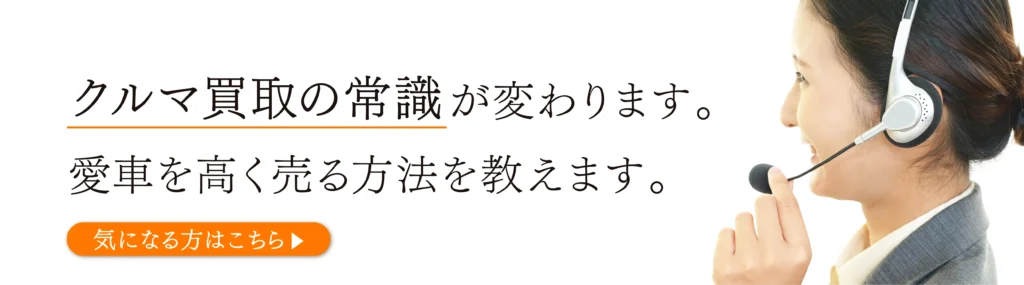
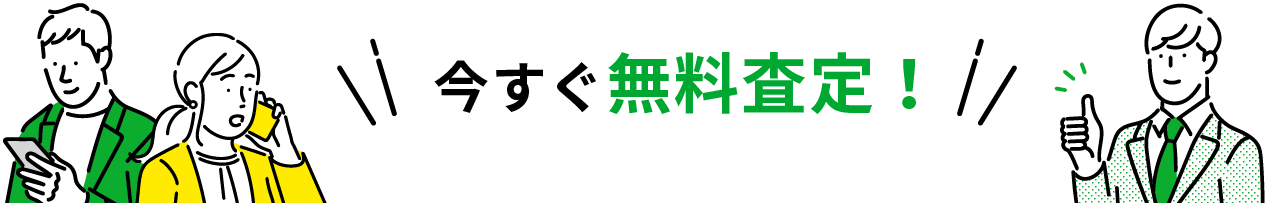




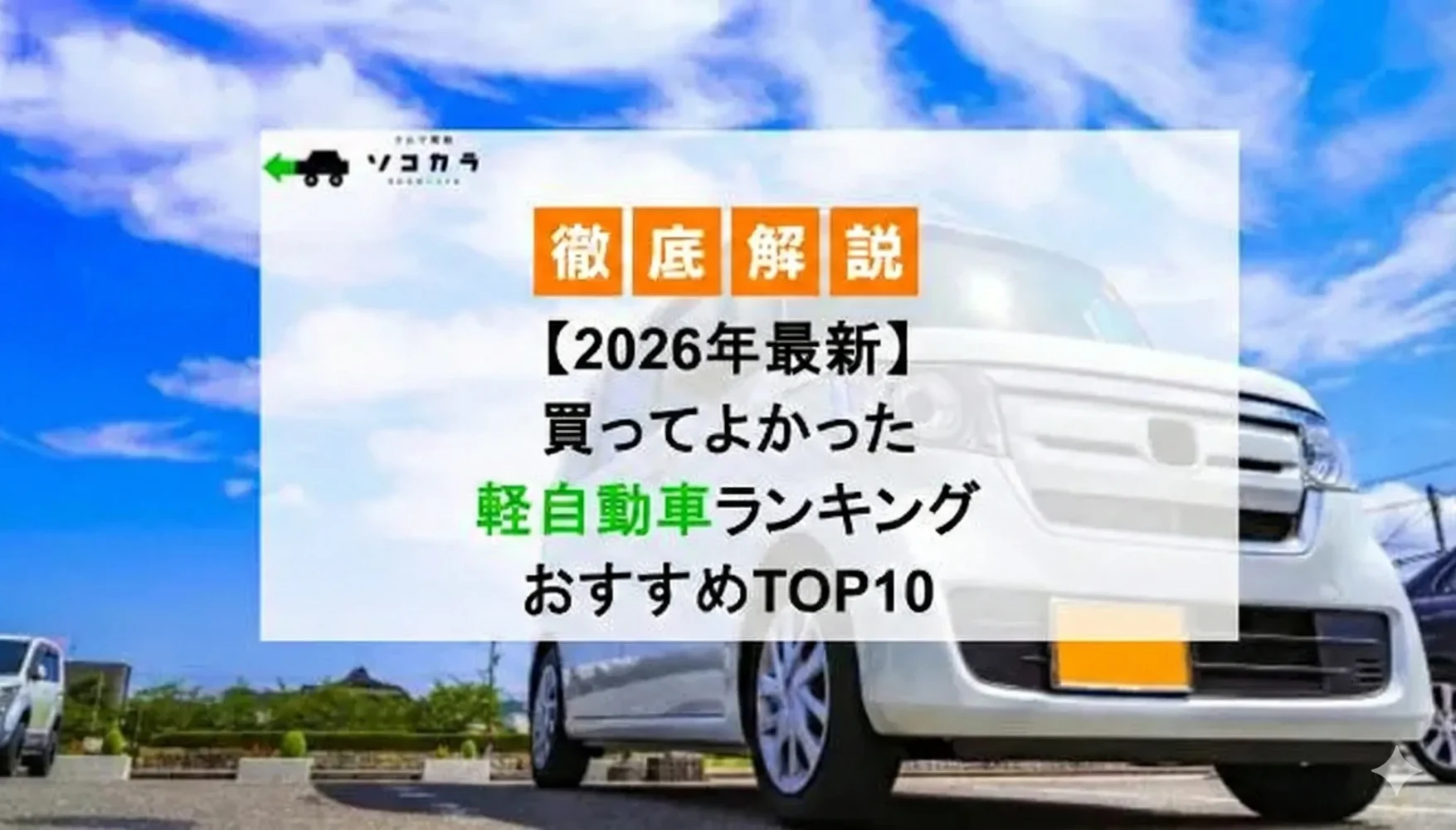


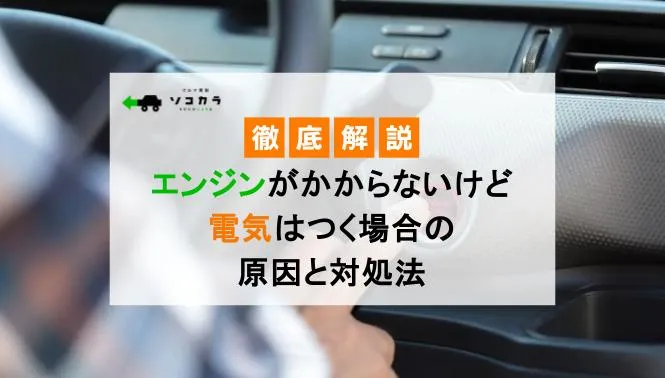
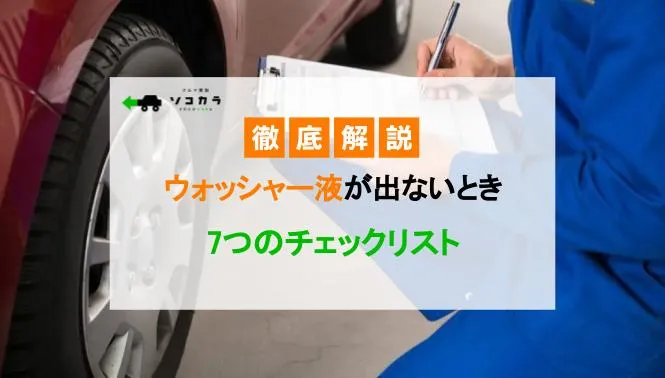
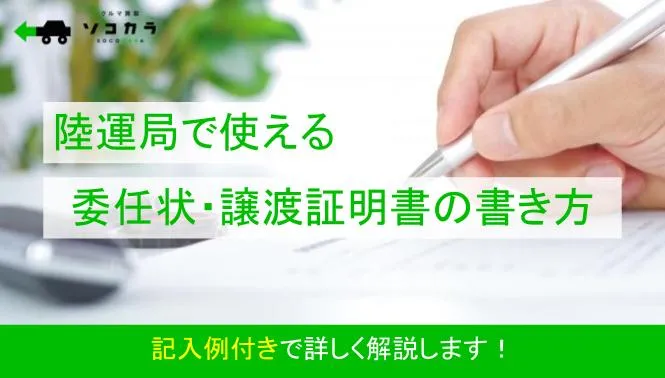

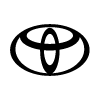
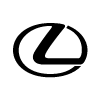
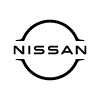

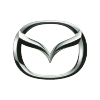


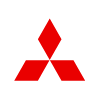









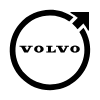

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870