- 2025.10.28
車のダッシュボードとは?インパネとの違いや名称と掃除方法について解説
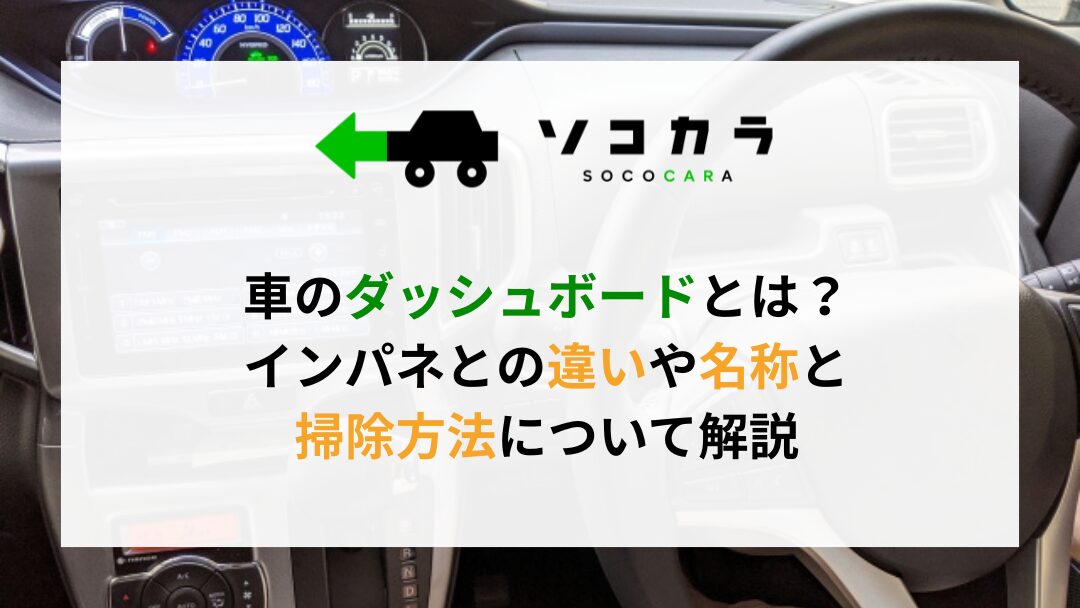
車のダッシュボードとは、運転席や助手席の正面、フロントガラスの下に広がる内装全般を指す部分です。
多くの人が「車のダッシュボードってどこ?」と尋ねられた際に、メーター類やカーナビが設置されたエリアを思い浮かべますが、それらを含む広範囲がダッシュボードにあたります。
この記事では、ダッシュボードが具体的にどの部分を指すのか、混同されやすい「インパネ」との違いとは何かを解説します。
さらに、各パーツの名称や役割、日常的な掃除方法から傷の補修方法まで、詳しく紹介していきます。
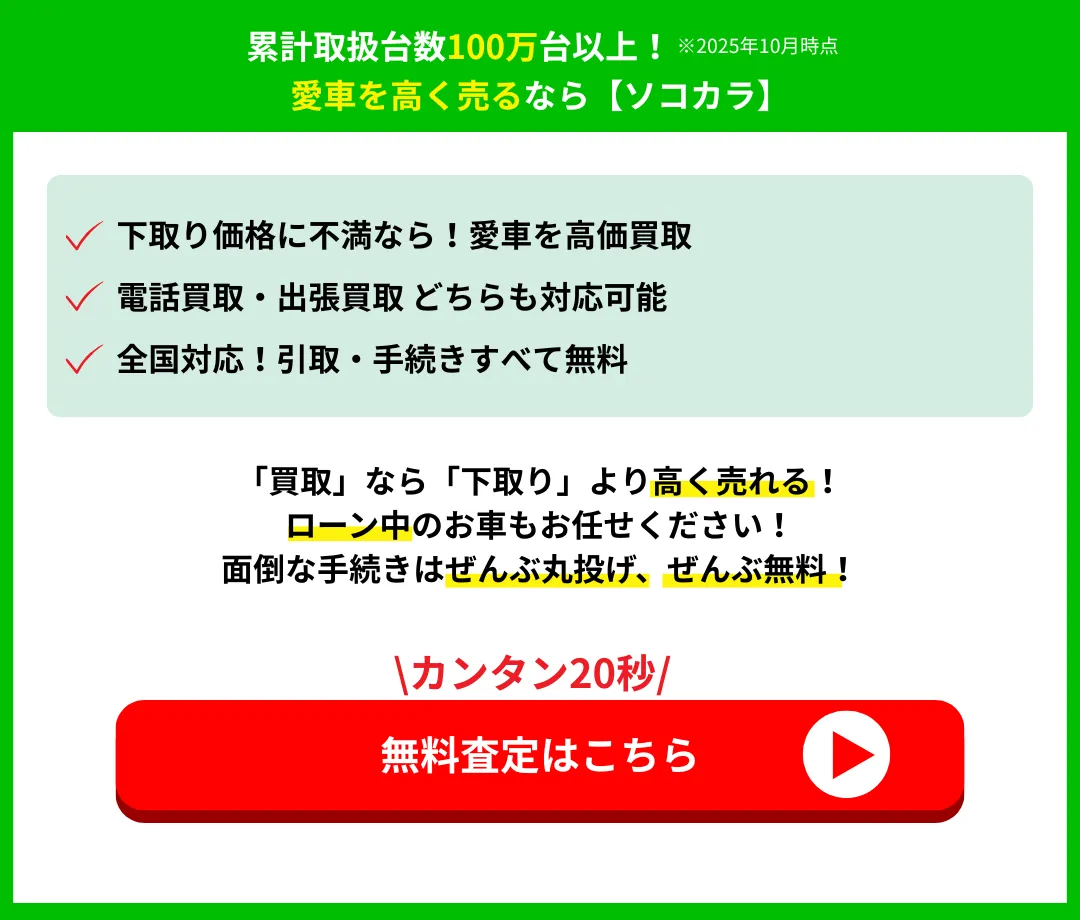
車のダッシュボードはフロントガラス下の内装全体を指す

車のダッシュボードの位置は、フロントガラスのすぐ下にある、運転席から助手席にかけて広がる内装パネル全体を指します。
一般的に「ダッシュボードに物を置く」と言う場合、この平らなスペースの上部をイメージすることが多いですが、本来はスピードメーターやカーナビ、エアコンの吹き出し口、グローブボックスといった計器類や装備品が組み込まれている領域全体がダッシュボードです。
単なる飾りや物置きのスペースではなく、運転に必要な情報を表示したり、車内環境を快適に保ったりするための重要な機能が集約された場所と言えます。
「インパネ」とは違う?混同しやすい用語との意味の違い
車の内装について話す際、「ダッシュボード」と「インパネ」は混同されやすい言葉ですが、厳密には指し示す範囲が異なります。
この二つの用語の違いを理解しておくと、車のパーツに関する説明などがより分かりやすくなります。
ダッシュボードがフロントガラス下の内装全体という広い範囲を指すのに対し、インパネは運転に必要な計器類がまとめられた、より限定的な部分を指します。
以下で、それぞれの用語が具体的にどの部分を指すのかを詳しく見ていきましょう。
インパネ(インストルメントパネル)が指す範囲
インパネという名称は、「インストルメントパネル(InstrumentPanel)」という英語を略した言葉で、日本語に訳すと「計器盤」となります。
その名前が示す通り、インパネが指すのは主に運転に必要な情報を表示する計器類が集中して配置されているパネル部分です。
具体的には、運転席のハンドルの奥にあり、スピードメーターやタコメーター、燃料計などがはめ込まれているエリアがインパネに該当します。
つまり、ダッシュボードという大きな領域の中に、計器盤としての機能を持つインパネというパーツが含まれている、と考えると関係性が分かりやすいでしょう。
ただし、自動車メーカーや会話の流れによっては、ダッシュボード全体を指してインパネと呼ぶこともあり、その使われ方は柔軟になっています。
スピードメーターなどが配置される計器盤
計器盤、すなわちインパネには、安全運転に不可欠な情報をドライバーに伝えるための様々なメーターやランプが集約されています。
最も代表的なものは、走行速度を示すスピードメーターやエンジンの回転数を表示するタコメーターです。
これらに加えて、燃料の残量計、エンジンの冷却水温計、総走行距離を示すオドメーターなども配置されます。
さらに、方向指示器の作動やライトの点灯状態を知らせる表示灯や、シートベルトの未装着、半ドア、エンジン系統の異常などを警告する各種警告灯もこの部分に備わっています。
これらの表示や警告を運転中に正しく認識することが、車両の状態を把握し、事故を未然に防ぐ上で極めて重要です。
意外と知らない?ダッシュボードにある各パーツの名称と役割
ダッシュボードは一見すると一体化したパーツに見えますが、実際にはそれぞれ異なる名称と役割を持つ複数の部品から構成されています。
普段何気なく目にしている部分にも固有の名前があり、その機能を知ることで、車の操作や理解がより深まります。
ここでは、運転席の正面にあるメーターパネルから、助手席前のグローブボックス、中央に位置するセンタークラスター、そして車内環境を整えるエアコンの吹き出し口まで、ダッシュボードを構成する主要なパーツの名称とその役割を分かりやすく解説します。
ハンドル奥にある「メーターパネル」
運転席のハンドルの奥に位置し、ドライバーが最も頻繁に確認する部分がメーターパネルです。
この部分は、前述したインパネとほぼ同じ意味で使われることが多く、運転に必要な情報が集約されています。
パネル上には、速度を示すスピードメーターやエンジン回転数を示すタコメーターを中心に、燃料計や水温計といった車両の状態を示す基本的なメーターが配置されています。
また、総走行距離や区間距離を示すオドメーターやトリップメーター、さらには各種警告灯や表示灯もこのエリアに集められており、車両からの情報をドライバーに即座に伝えるという重要な役割を担っています。
常に視界に入るため、ここに表示される情報をこまめに確認することが安全運転の基本となります。
助手席前の収納スペース「グローブボックス」

助手席の正面、膝のあたりに設けられた蓋付きの収納スペースは「グローブボックス」と呼ばれます。
この名前は、かつて車を運転する際に使っていた手袋(グローブ)を保管していたことに由来します。
現在では、車検証や自賠責保険証、車両の取扱説明書といった重要書類を保管する定位置として活用されるのが一般的です。
ダッシュボードの中に組み込まれているため、運転席からでも手が届きやすく、ティッシュ箱やCD、ウェットティッシュなど、車内に常備しておきたい様々な物を置くための便利なスペースとしても機能します。
車種によっては内部にETC車載器が格納されていたり、エアコンの冷風を引き込んで飲み物を冷たく保つ保冷機能が備わっていたりすることもあります。
カーナビやオーディオが収まる「センタークラスター」
ダッシュボードの中央、運転席と助手席の間に位置する操作パネルが集まった部分を「センタークラスター」と呼びます。
このエリアには、カーナビゲーションシステムのディスプレイやオーディオの操作部、ハザードランプのスイッチ、そしてエアコンのコントロールパネルなどが機能的に配置されています。
ドライバーだけでなく助手席の同乗者からも操作しやすいように設計されているのが特徴です。
近年では、物理的なスイッチを減らし、大型のタッチパネルディスプレイに多くの機能を集約するデザインが主流となっています。
このディスプレイ上で、ナビの地図を表示するだけでなく、オーディオの選曲、エアコンの温度設定、車両の各種設定などを一括して操作できるモデルが増えています。
空調の風が出る「エアコンの吹き出し口(デフロスター)」
ダッシュボードには、車内の空調をコントロールするためのエアコンの吹き出し口が複数設けられています。
運転席側、助手席側、そしてセンタークラスターなどに配置され、風向きや風量を個別に調整することで快適な室内環境を作り出します。
これとは別に、フロントガラスが曇った際に、乾燥した空気をガラス内側に直接吹き付けて視界を確保する重要な役割を持つ「デフロスター」という吹き出し口も存在します。
デフロスターはダッシュボードの上部、フロントガラスの付け根に沿って設置されています。
同様に、サイドウィンドウの曇りを取るための「サイドデフロスター」がダッシュボードの両端に備えられている車種も多く、これらは快適性だけでなく、安全な視界を確保するという大切な役割を担っています。
ダッシュボードをきれいに保つための掃除方法

ダッシュボードは車内で特に目につきやすく、ホコリや指紋が付着しやすい場所です。
この部分をきれいに維持することは、車内全体の見た目を向上させるだけでなく、運転中の快適さにも影響します。
また、樹脂や革といった素材は、汚れや紫外線の影響で劣化が進むことがあるため、定期的な手入れが長持ちさせる秘訣です。
ここでは、日頃からできる基本的な掃除の手順に加えて、直射日光による色あせやひび割れといったダメージを防ぐための対策についても紹介します。
ホコリや手垢を落とす基本的な掃除手順
ダッシュボードの掃除を始める際は、まずハンディモップや乾いたマイクロファイバークロスを使い、表面に積もったホコリを優しく拭き取ります。
メーター周りやスイッチの隙間といった細かい部分は、毛先の柔らかいブラシを使ってホコリをかき出すと効果的です。
ホコリが取れたら、次に手垢や皮脂汚れを落とします。
水で濡らして固く絞ったマイクロファイバークロスで全体を拭き上げましょう。
もし水拭きだけで落ちない頑固な汚れがある場合は、水で薄めた中性洗剤をクロスに少量含ませて拭き、その後、洗剤成分が残らないようにきれいな水で濡らしたクロスで再度拭き、最後に乾拭きで仕上げます。
アルコールなどの溶剤を含むクリーナーは素材を傷める可能性があるため、車内専用のクリーナーを使うか、目立たない場所で試してから使用すると良いでしょう。
定期的な手入れで、きれいな見た目を維持できます。
紫外線による色あせやひび割れを防ぐ対策
ダッシュボードはフロントガラスを通して直射日光を常に浴びるため、車内のパーツの中で最も紫外線によるダメージを受けやすい部分です。
長期間、強い紫外線に晒されると、樹脂パーツの色があせたり、表面に細かいひび割れが発生したりする原因となります。
こうした劣化を防ぐためには、日頃からの紫外線対策が欠かせません。
最も手軽で効果的な方法は、駐車時にサンシェードを利用することです。
サンシェードで直射日光を遮ることで、ダッシュボードの温度上昇を抑え、紫外線による素材へのダメージを大幅に軽減できます。
また、UVカット効果のあるダッシュボード専用の保護ツヤ出し剤を定期的に塗布することも有効です。
これにより紫外線から素材を守り、しっとりとした質感を保つことで、新品のような見た目と本来の色を長く維持できます。
傷や劣化からダッシュボードを守るための予防策
ダッシュボードは一度深い傷がついてしまうと修復が難しく、車内の見た目を大きく損ねてしまいます。
そのため、日頃から傷がつかないように予防策を講じることが重要です。
物を置く際の少しの工夫や、便利なアクセサリーを活用することで、デリケートなダッシュボードの表面を効果的に保護できます。
ここでは、誰でも簡単に実践できる予防策と、それらを行うことによる利点について解説し、きれいな状態を長く保つための方法を紹介します。
小物の滑り止めシートや置き場所に注意する
ダッシュボードの上にスマートフォンやコインケースなどの小物を直接置くことは、走行中の振動で滑り、表面に擦り傷をつける原因となります。
このような傷を防ぐためには、市販されている車用の滑り止めシートを敷くのが非常に効果的です。
シートを一枚敷いておくだけで、置いた物が安定し、ダッシュボードに直接触れることがなくなるため、傷のリスクを大幅に減らせます。
また、ダッシュボードの上に物を置く際は、鍵などの硬いものや角が鋭いものは避けるように心掛けることも大切です。
特に、液体タイプの芳香剤は、万が一中身がこぼれるとシミや素材の変質を引き起こす可能性があるため、設置場所や固定方法には十分注意が必要です。
安全のため、エアバッグが展開する場所には何も置かないようにしましょう。
専用のダッシュボードマットを敷くメリット
ダッシュボード全体を包括的に保護する方法として、車種専用に設計されたダッシュボードマットの使用が挙げられます。
マットを敷くことには多くの利点があります。
第一に、最大のメリットとして、直射日光による紫外線ダメージや熱による変形、ひび割れといった経年劣化を効果的に防止できる点です。
また、ホコリや汚れが直接ダッシュボードに付着するのを防ぐため、普段の手入れがマットをはたいたり、汚れたら洗濯したりするだけで済むようになり、掃除の手間が軽減されます。
さらに、日中の運転時にダッシュボードがフロントガラスに映り込む現象を抑え、ドライバーの視界をよりクリアに保つ効果も期待できます。
車種専用品であれば、エアコンの吹き出し口やスピーカー、センサー部分の穴が正確に開けられており、車の機能を損なうことなく設置可能です。
ついてしまったダッシュボードの傷を自分で補修する手順

どれだけ注意していても、荷物の出し入れや乗り降りの際に、ダッシュボードにうっかり傷をつけてしまうことはあります。
浅い擦り傷や小さなえぐれ傷であれば、専門の業者に高額な費用を払って依頼しなくても、自分で補修することが可能です。
カー用品店などで手に入るダッシュボード用の補修キットを使えば、手順に沿って作業することで傷を目立たなくし、車内の見た目を改善できます。
ここでは、自分でダッシュボードの傷を補修するための具体的なステップを分かりやすく解説します。
ステップ1:補修箇所の汚れをきれいに拭き取る
補修作業を成功させるための最初の重要なステップは、傷とその周辺を徹底的にきれいにすることです。
表面にホコリや手垢、油分などが残っていると、この後使用する補修剤がしっかりと密着せず、仕上がりの見た目が悪くなるだけでなく、補修箇所がすぐに剥がれてしまう原因にもなります。
まずは、水で濡らして固く絞ったきれいな布で、傷の周りの汚れを丁寧に拭き取ってください。
特に、ワックスやツヤ出し剤などの油分は補修剤の定着を妨げるため、必要であればシリコンオフなどの脱脂剤を使って慎重に除去します。
拭き掃除が終わったら、補修箇所が完全に乾くまで待ち、作業面が清潔で乾燥した状態であることを確認してから次の工程に進みましょう。
この下地処理が仕上がりの質を左右します。
ステップ2:傷の周りをマスキングテープで保護する
補修箇所の下地処理が完了したら、次に補修剤や塗料が傷のない部分にはみ出さないように、傷の周囲をマスキングテープで保護します。
この「マスキング」と呼ばれる作業を行うことで、作業範囲が明確になり、余計な部分を汚すことなくきれいに仕上げることが可能です。
傷の輪郭に沿って、数ミリの間隔を空けてテープを丁寧に貼り付けていきましょう。
テープとダッシュボードの間に隙間ができないように、指でしっかりと押さえて密着させることがポイントです。
この一手間を惜しまずに行うことで、補修箇所だけをピンポイントで作業でき、周囲との境界線がくっきりとするため、最終的な見た目が格段に向上します。
簡単な作業ですが、仕上がりの美しさに大きく影響する重要な工程です。
ステップ3:専用のパテや補修剤で傷を埋める
マスキングテープで周囲を保護したら、いよいよ傷を埋める作業に移ります。
ダッシュボードの素材(多くは樹脂製)に対応した専用の補修パテや充填剤を使用しましょう。
補修キットには、ダッシュボードの色に合わせられるように複数の色のパテが同梱されていることが多いです。
説明書を参考にパテを混ぜ合わせて色を調整し、付属のヘラなどを使って傷の中に少し盛り上がる程度に充填していきます。
傷が深い場合は、一度に厚く盛ると乾燥後に収縮してへこんでしまうことがあるため、数回に分けて薄く塗り重ねるのがきれいに仕上げるコツです。
パテを充填し終えたら、製品の指示に従って完全に乾燥するまで待ちます。
乾燥時間が不十分だと次の工程で崩れてしまうため、焦らずに時間を置くことが重要です。
ステップ4:表面を平らに整えて塗装で仕上げる
補修剤が完全に硬化したら、仕上げの工程に入ります。
まず、傷から少し盛り上がっている余分なパテを、付属のヘラや目の細かいサンドペーパー、カッターの背などを使って慎重に削り取ります。
周囲のダッシュボードの面と高さが同じになるように、少しずつ確認しながら表面を平らに整えていきましょう。
力を入れすぎると、傷のない部分まで削ってしまうので注意が必要です。
表面が滑らかになったら、補修箇所と周囲の色を合わせるために塗装を行います。
補修キットに含まれる塗料や、別途用意したダッシュボード用のスプレーを使い、一度に厚く塗らずに薄く数回に分けて塗り重ねるのがムラなく仕上げるコツです。
塗装が乾いたらマスキングテープを剥がし、見た目に違和感がなければ作業完了です。
まとめ
車のダッシュボードとは、フロントガラスの下部に広がる内装全体を指し、運転に必要な計器類が収められたインパネとは区別されるのが本来の意味です。
このエリアにはメーターパネルやグローブボックス、センタークラスターといった、それぞれに役割を持つ重要なパーツが機能的に配置されています。
ダッシュボードはホコリが溜まりやすく、紫外線の影響も受けやすいため、定期的な掃除やサンシェードの活用といった手入れをすることで、美しい見た目を長く保つことができます。
また、滑り止めシートや専用マットを利用すれば、傷の予防にもなります。
この記事で解説した各部の名称やメンテナンス方法は、初心者にも分かりやすい内容です。
これらの知識を深めることで、愛車への理解を深め、より快適なカーライフを送ることが可能になります。
本田圭佑さんのテレビCMでおなじみソコカラなら、ピカピカの中古車はもちろん、年式10年以上、10万キロ以上走行、事故車・故障車などどんな車も高価買取いたします!電話か、出張か高い方の査定を提案するソコカラ独自の2WAY査定で愛車をどこよりも高く買取ります。さらに査定・引取・手続きぜんぶ丸投げ、ぜんぶ無料!ぜひお気軽に「ソコカラ」(TEL:0120-590-870)にご相談ください。


この記事の監修者
浅野 悠
中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。
関連記事
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.26
【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2026.01.30
車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2025.12.04
【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!
- 燃費
- 維持費
- 軽自動車
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 2024.09.10
車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説
-
-

-
- 中古車のお役立ちコラム
- 故障車のお役立ちコラム
- 2024.10.17
ウォッシャー液が出ないときのための7つのチェックリスト
-
-

-
- 廃車のお役立ちコラム
- 2024.08.09
トラブル回避!陸運局で使える委任状・譲渡証明書の書き方【記入例付き】
-






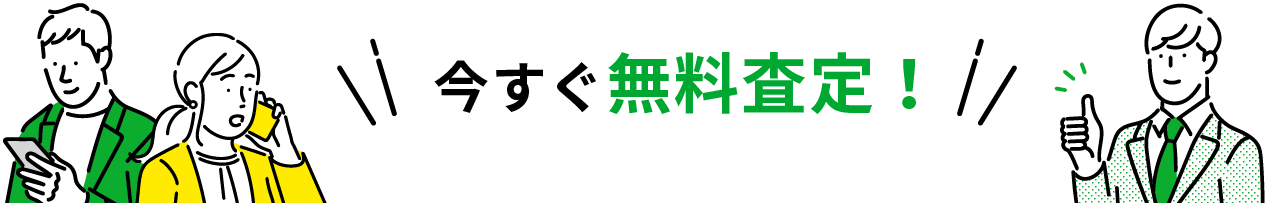




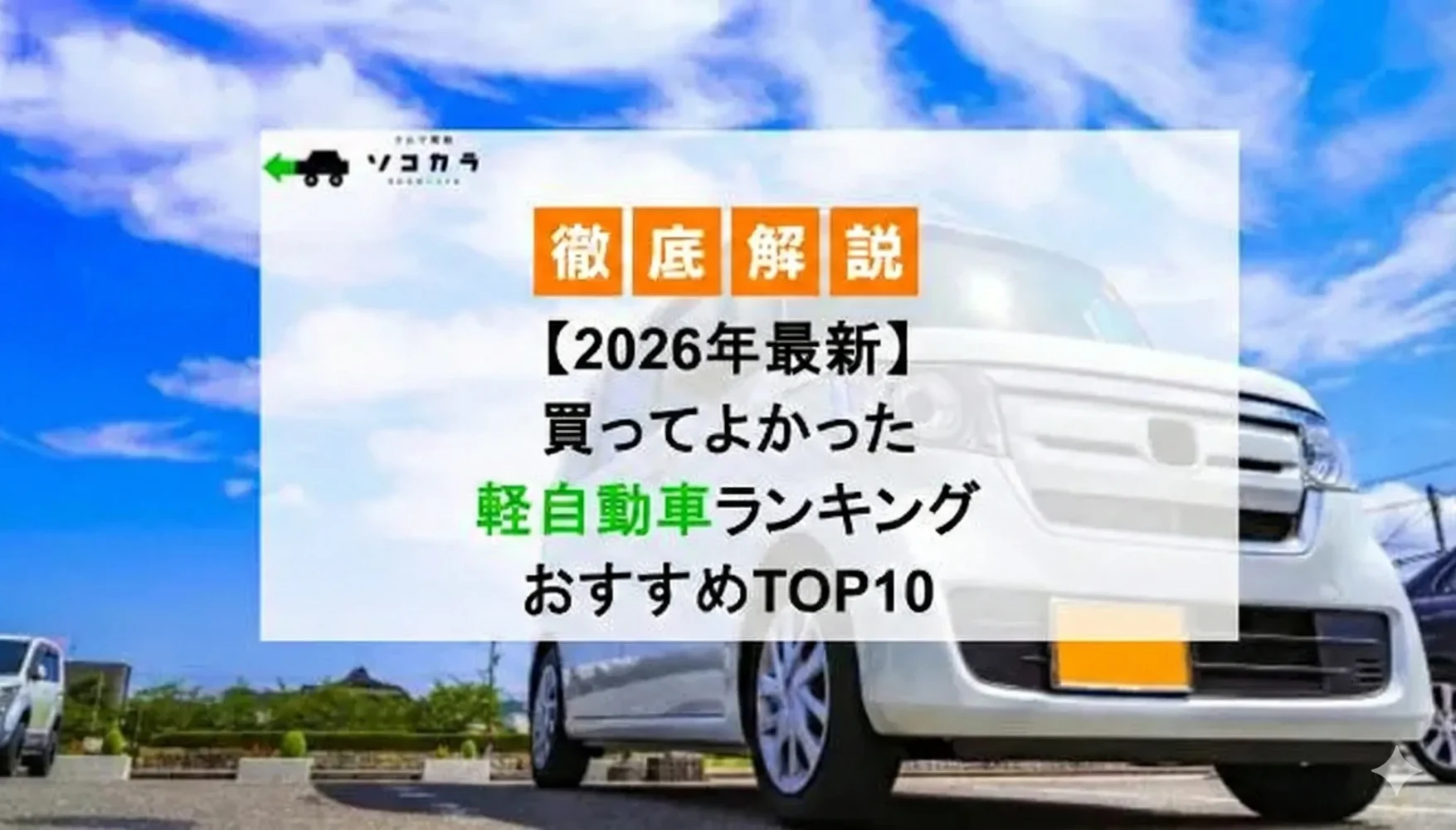


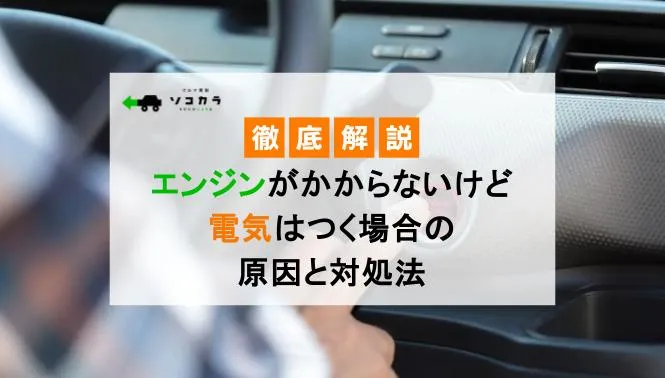
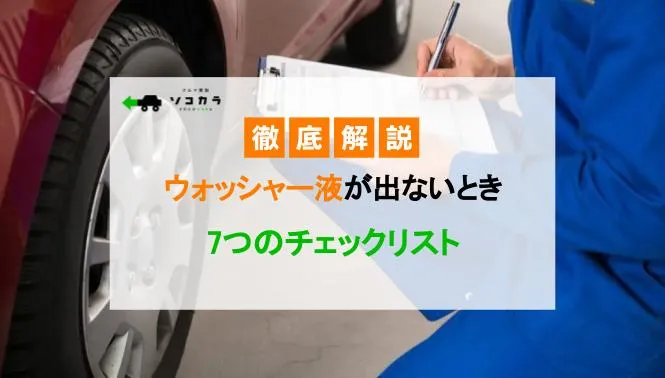
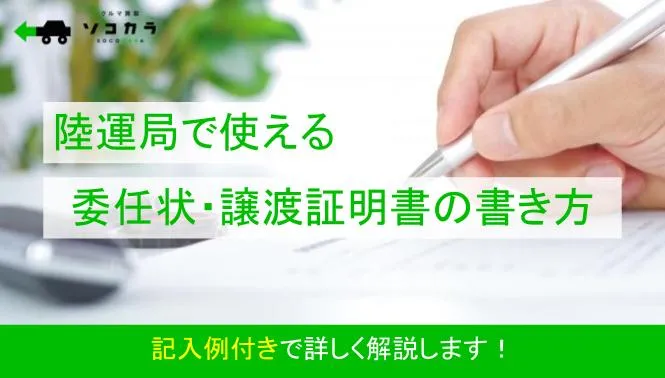

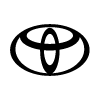
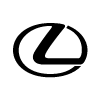
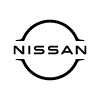

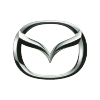


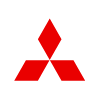









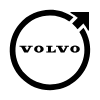

 ホワイト
ホワイト ブラック
ブラック シルバー
シルバー レッド
レッド オレンジ
オレンジ グリーン
グリーン ブルー
ブルー ブラウン
ブラウン イエロー
イエロー ピンク
ピンク パール
パール パープル
パープル グレー
グレー ベージュ
ベージュ ゴールド
ゴールド



 0120-590-870
0120-590-870